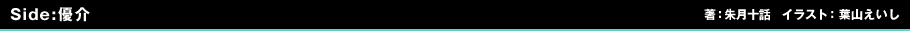コンテンツページ
神ヶ峰学園の指導学生として、学生兼教師となった俺の一日は、今日は生徒たちにどのような指導をするかという予定作りから始まる。
1年生の中でも成績が下位の生徒たちが集まるJクラス。前任の女性教師の代わりにそこに配属された俺には、まず生徒たち全員にクリアさせなくてはならない試験がある。
『能力制御試験』。自分の意思で能力をコントロールすることができれば突破できるのだが、俺と一緒にこの花住荘に下宿している三人の女子生徒は、揃って制御できる目途が立っていないのである。
「まずは……問題児ぶりが少し他の二人より際立つ、フレデリシアから……個人的な指導を……」
フレデリシアの資料を片手で見ながら、俺は左手だけで逆立ちをし、そのまま腕立て伏せをしていた。
学園に来るまではマンションで軟禁生活を送っていたので、身体がなまらないように動かしていた結果、これが最も負荷がかかり、ちょうどいい準備運動だと感じたのだが――。
「……優くん……す、すごいわね。どうやったらそんなことができるの?」
「ああ、紫苑さん、おはよう。もう少ししたら、俺も出かける準備をするよ」
俺は腕を入れ替え、今度は右手で腕立て伏せをする。使う筋肉を意識しつつ、とりあえず三人を体育館に呼び、そこで能力制御の練習をしようと考える。
「精神論では難しいかもしれないけど、まずは能力をコントロールしたいという意思を強く持つことだと思うんだ。今日の放課後は、そういう指導をしようと思ってる」
「え、ええ……それはいいけれど、優くん、どうしてそんな物凄いトレーニングをしながら指導計画を練っているの?」
「俺の能力で筋力を1・5倍に強化してるから、凄くはないよ。床に指がめり込まないように気をつけてはいるけど」
「そういうことだったのね。そこまで筋肉質でもないのに、そこまで凄い力を出し続けられるなんて……1・5倍って、やっぱり物凄いことよね」
五感を含めたあらゆる身体能力を、1・5倍に引き上げるというのが俺の特殊能力――『究極全能(パーフェクト・ヴァリアント)』だ。
基礎能力が高いほど1・5倍にした時の上限も高くなるので、皆を指導する立場としては常に最良のコンディションを保ち、力を維持しなくてはならない。
「でも……優くん、女の子だけの寮で、上半身裸でトレーニングするのは、ちょっと教育的指導上、私としては問題を感じるわね」
「え……部屋でやっててもダメかな? ごめん、見苦しかったかな」
「い、いいのよ、私はたまたま様子を見に来ただけで……でもね、生徒には刺激が強いと思うの。ほら、みんな思春期でしょう? そんな引き締まった異性の身体を見せられたら……特に観音寺さんが、色々と危険だわ」
「観音寺さんは大人しそうだし、どちらかというと異性は苦手そうだったから、慎重に接しなきゃいけないと思ってるけど……何か問題あるかな?」
逆立ちをやめて起き上がると、紫苑さんが目のやりどころに困っている――汗はかいてないんだけど、やはりシャツくらい着ておいたほうが良かったか。
「……これじゃ、私の方が思春期みたいね。優くんったら、無邪気なんだから」
「教師としては、もっと落ち着いた方がいいってことか?」
「そうね、女の子たちとの距離感については、特に注意しないとだめよ。優くんのクラスには、女子しかいないんだから」
「まあ、七人しかいないけどな。みんな無事に卒業させるためには、まず信頼を得ないとな……ありがとう紫苑さん、忠告してくれて」
礼を言うと、紫苑さんは少し迷うようなそぶりを見せたあと、俺に近づいてくる。そして、二の腕に触れてきた。
「ちょっと力を入れてみて。さっき、すごい負荷がかかっていたから、保健医として診てあげる」
「ん……こうか?」
腕に力を入れると、紫苑さんは真剣な顔をして触れつつも、顔が赤らんでいく。
何か思うところがあるということだろうか。意識するとドキドキしてくるが、紫苑さんは従姉なので、変なことを考えてはいけない。
「すごく硬い……若いって、すごいわね……いえ、若ければ誰でもいいというわけじゃないのよ」
「あ、ああ……分かってるよ。紫苑さん、くすぐったいんだけど……」
「だめよ、背中も見せてもらわないと。背筋の張り具合も診ておかないとね」
(紫苑さんはもしや、筋肉フェチなだけなのでは……朝から俺は何をしているんだ)
紫苑さんに背中を向けようとして、ふと俺は部屋のドアを見やり――開いている隙間からこちらを見ている、三人の女子生徒の姿に気が付いた。
「うわっ……い、いつから見てたんだ?」
「っ……あ、あなたたち。ドアが開いているからといって、覗いちゃだめよ? ほら、五条先生は着替え中だから」
三人の女子生徒――水乃亜さんと観音寺さん、そしてフレデリシア。中でもほんわかしている水乃亜さんだが、まじめな性格でもあるので、こういうことには厳しい。
「し、紫苑先生、私、こういうことはよくわからないですけど、ごまかしてるってことはわかるんですよ? 朝から五条先生とえっちなことして……お、おこです!」
「うちは二人が何も言ったらあかんって言うから、静かに見学してただけなんやけど……はぁ……五条せんせ、いい身体してはる……」
「な、何を色っぽい吐息をついてるんですの。朝から能力を発動させたりしたら、大変なことに……お、抑えてくださいませっ!」
ふわ、と観音寺さんから甘い香りが漂ってくる――彼女の特殊能力、『魅惑の芳香』が発動したのだ。これを嗅いでいると、俺の理性は見る間に怪しくなり、観音寺さんの三つ編みをほどき、眼鏡を外したらより美少女になるのではないかとか、体形を出さないようにしている制服の下に、どれほど魅力的な肢体が隠されているのかなど、抑えきれない関心が湧いてきてしまう。
「観音寺さん……朝からなんだけど、君のことが何というか、物理的に欲し……ふがっ」「ふぅ……これでしばらくは持ちそうね。観音寺さん、芳香が出ているうちは優くんに近づいてはだめよ」
紫苑さんに鼻をつままれ、俺の理性が戻ってくる。教師としてあるまじきことを考えていた気がするが、俺に限ってそんなことがあるわけがない。
「完全に翻弄されていますわね、五条先生。そんなことで、上手く指導をしていただけるんですの? もう少し信用させてくださいませ」
「す、すまない……面目ない。今日の指導はしっかりやるつもりだ」
フレデリシアは腕を組んで、俺を値踏みするように見つめる。金色のさらりとした髪にまさにお嬢様という容姿――彼女は音漏れしないノイズキャンセリングヘッドホンを常に身につけており、爆音を鳴らしているのだが、俺の話は唇の動きを読めばわかるという。
そのヘッドホンをつけている理由を聞くことも、指導の一環として必要なことだ。そのためには、彼女の言う通り信用を得なくてはならない。
「……まあ、いいですわ。あなたの教師としての熱意は、理解しているつもりですし」
「わ、私も、先生の真っすぐなところは好きです……あ、す、好きって、人間的な意味でですねっ」
「人間として好きって、かなりステージが上の愛やんか……と、透湖ちゃんっ、まだ会ったばかりやのに、そんな大胆な……うちはせんせの筋肉とかええなと思うけど、そんなレベルと違うやんか!」
「ち、違うの、そういうわけじゃ……え、えっと、朝ごはん作ってきまーすっ!」
水乃亜さんが慌てて階下に降りていき、二人もその後に続く。
「観音寺さん、筋肉が好きなのか……運動の指導を希望しているということかな」
「えっ、そこ? 優くん、鍛えた身体を褒められてときめいたりはしないの?」
「生徒が教師を男性として意識したりはしないはずだ。俺もそうだから」
「……優くん、何か我慢していることがあったら言うのよ。そういうのは、溜め込むと良くないから。私が力になってあげるわ」
「う、うん。紫苑さんがそう言ってくれるなら……」
最初はピンと来なかったが、紫苑さんが恥ずかしそうに部屋を出て行ったあとで、俺は彼女が言わんとすることに気が付いた。
教師は絶対に、生徒によこしまな気持ちを抱いたりはしない。
そう誓っている俺なのだが、受け持つ生徒たちはそれぞれの魅力があり、教師でもありながら生徒でもある俺の心を大いに揺り動かすことになる――そんな予感を禁じ得なかった。