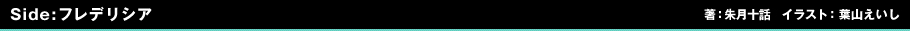コンテンツページ
私の名前はフレデリシア・スタインバーグと言います。スウェーデンの特殊能力者が通う学園から、日本の神ヶ峰学園に転入してきました。
日本語はこちらに来る前に、半年ほど勉強して覚えました。まだネイティブの方々ほどこなれているとは言えませんし、なぜかお嬢様みたいだと言われるのですけれど、私としては普通だと思っています。できるだけ丁寧に話そうとした方が、相手に失礼を与えないと母が言っていましたし、私もそうしようと思っているというだけなのです。
でも、私は人と話すことが苦手です。それは、私の能力に起因することです――能力の制御ができないので、私はありとあらゆる『声』を聞かないように生活しています。そのために役に立っているのが、ノイズキャンセリング機能のついたヘッドホンです。
元々歌手を目指していたこともあって、どのようなジャンルの音楽でも好んで聞くのですが、外の音を防ぐために適しているのはロックです。ボーカルが入っていると不都合なので、私が聞くのは楽器のみのインストゥルメンタルです。普通の人は耳が壊れそうというくらいの爆音ですが、私は平気です――少しでも人の声が聞こえてしまう方が、私には耐え難いことなのです。
声を聞くことはできませんが、人の唇の動きを読めば、話していることは分かります。それもできなければ、日常生活を送ることも難しかったでしょう。
能力の制御ができるようになれば、このヘッドホンを着けずに済みます。私はそのために、新たな指導を求めて日本に来ました。
ですが、神ヶ峰学園に転入してから二ヵ月が過ぎても、制御ができるようになるための手掛かりは、まったく見えてきていません。私は制御試験を通らない生徒が自動的に配属されるJクラスになり、担任の先生には私たちの問題児ぶりは荷が重く、六月に入ってから新しい先生に代わることになりました。
お父様に日本への留学を認めてもらえたのに、このままでは制御試験に通らず、夏休みのうちに帰国することになってしまいます。
その新しい先生というのが、国内に数名しかいない、教師を兼ねることができる生徒――『指導学生』だというのです。
五条優介。その名前を聞かされたとき、知り合ったばかりの男子に能力の使い方を教えてもらうなんて、と少し身構えました。
彼が転入してきた当日にも、私は素直に指導をお願いしたいとは言えずに、ヘッドホンを外さず、ガムを噛んで、手と足を組んで席に座っていました。
人の話を聞くときはヘッドホンを外すべき、そう言って彼は――私に声を聞かせるために、その能力を使って見せたのです。
◆◇◆
(……変わった人ですわ、本当に)
町にただ一つだけある、駅前の音楽CDを売っている店で、私はCDを探しながら五条先生のことを考えていました。
爆音を鳴らすヘッドホンを着けた私に、彼が声を直接聞かせるために取った方法。それは、とても単純で、明快で、想定外のものでした。
彼は、声を大きくしたのです――その能力で、私の耳が馬鹿になってしまいそうなくらいの大声を出して。
自分のあらゆる身体能力を増幅することができるという五条先生の特殊能力は、私や透湖、そして愛乃の能力を抑え込んでしまうだけの万能性を持っていました。
私の耳には、まだ彼の声が残っているように思えます。『俺の話を聞いてくれ』という訴えは切実で、あれから数日経っているのに、ふと気づくと頭の中で再生されます。
「お客様、何かお探しですか?」
「あ……い、いえ。ありがとうございます、もう少し自分で探してみますわ」
店員さんがぼーっとしている私に声をかけてきたので、私は慌てて答えたあと、探していたCDを買ってお店を出ました。ネットで音源だけ買うのも良いのですが、紙のジャケットやライナーノーツを見るのが好きなのです。
◆◇◆
お店を出て、寮への道を歩いている途中で、私はふと何かの気配を感じて振り返りました。
「……珍しいですわね、野良猫なんて」
私の後を、小さな白い猫がついてきていました。動物に懐かれるほうではないのですが、その子は私の靴をぺろぺろと舐めてきます。
「そんなもの、美味しくありませんわよ。お腹がすいているんですの?」
みゃーん、と子猫が愛嬌たっぷりに鳴くので、私は何かこの子の助けになってあげたいと思いましたが、餌になるものを持っているわけでもありません。
かがみ込むと、猫は私のことを見上げて、つぶらな瞳で見つめてきます。
「……首輪をつけていませんのね。でも、寮では動物を飼ってはいけない決まりなんですの」
頭を撫でてあげても、猫は逃げたり、嫌がったりしません。それどころか、ぺろぺろと私の手を舐めようとします。
ヘッドホンをつけても、私の聴覚を完全に封じ込めることはできません。爆音の中で小さく聞こえてきた猫の鳴き声で、私は――その猫が、何を考えているのかを悟りました
その猫は私を優しい人だと思っていました。それでも私は、その子を連れて帰ってあげることができません。
せめて、何か餌になるものをあげられたら。そう思っているうちに、足音が聞こえてきて――そちらを見やると、思いもしない人が立っていました。
「……あれ、フレデリシア?」
「っ……ご、五条先生。どうしたんですの、こんなところで」
「駅前に色々店があるって聞いたから、一度見に来ようと思ったんだ……おっ、その猫はどうしたんだ?」
「こ、これは……」
私はびっくりして、つい猫を抱き上げてしまっていました。猫は私の気持ちも知らずに、胸にはっしとしがみついてきます。
「つ、爪を立てちゃだめですわ、制服が……な、何ですのその顔は。ほほえましそうに見ないでくださいませっ」
「いや、動物に懐かれるってのは凄いことだよ。俺もそんなふうになってみたいもんだ……おお?」
猫を地面に降ろしてあげると、ぱっと走っていって、今度は五条先生に飛びつきます。そして先生が抱き上げると、頬を舐め始めました。
「……その子が、普通の猫より人懐っこいだけみたいですわね」
「ほ、本当だな……これだけ人に慣れてるってことは、野良じゃないのか。それにしては、首輪もしてないな」
「寮では、動物はだめなのですが……このまま残していくのは心配ですわ」
「そうだな。確かに……よし、俺が預かってくれるところを探そう」
ほとんど迷いのない先生の答えに、私は――驚くと同時に、正直に言って、頼もしいと感じました。
でもそれを顔に出すことはためらわれて、口をついて出るのは、思ってもみない言葉でした。
「簡単に見つかるわけありませんわ、そんなに急に」
「じゃあ、預かってくれる人が見つかるまでうちの寮で面倒見るか」
「っ……そ、そんな、規則では、動物は厳禁と……」
「職権を振りかざすのは問題あるかもしれないが、俺は先生だしな。俺が責任を持って面倒を見るってことで、何とかならないか掛け合ってみるよ」
そのとき、私は五条先生の顔を見ながら思いました。一度そうすると決めたら、この人は迷いも何もなく、自分の意思を曲げない人なのだと。
それに比べたら、私は簡単に迷ったり、立ち止まったりしてしまう。そんな自分が恥ずかしく感じられて仕方がなくて、思わず弱音が口をつきました。本当は、そんなことを言うべきではないのに。
「……薄情だと思いますか? 私のことを」
「ん? そんなこと、思うわけがない」
「で、ですが……私は規則だと言って、その子を置いて行こうと……」
「どうしようか悩んでたなら、全く薄情なんかじゃない。そもそもこの猫は、俺たちが何かしなくても元気に生きていけるかもしれない……でも人に懐いてるなら、こうして干渉するっていう選択もある。余計なお節介かもしれないけどな」
何も考えていないわけでもない。彼は彼なりに考えて、この猫に干渉すると決めて――それが善意の押しつけにならないかと考えてもいる。
「フレデリシア、餌は何がいいと思う? キャットフードが無難か」
「……ふふっ。確かに無難ですが、猫は人間のものを食べると身体を壊しやすいですから、それでいいと思いますわ」
私は普通に答えたつもりでしたが、先生が驚いたようにこちらを見ているので、なぜそんな顔をするのかと考えて――気が付きました。自分が、笑っていることに。
「な、何ですの? 聞かれたから答えただけですわよ」
「あ、ああいや……何でもない」
照れ隠しも、五条先生にはそのうち通用しなくなるかもしれない。私は一瞬だけそう思いました。
――けれどまだ、私は先生に対して素直になるにも、ヘッドホンを外すにも、とても勇気が足りていません。
でも、先生が指導してくれるのなら――夏休み前の制御試験は、合格できるかもしれない。
彼の熱意に感化されていることが、自分でも分かりました。けれどまだ、具体的に何が変わったというわけではありません。
「……不思議な人ですわね」
「ん、何か言ったか?」
「言ってませんわ。ヘッドホンから音が漏れてしまったのではないですか?」
「いや、完全に密閉されてるが……まあ、気のせいならいいんだけどな」
私は猫の餌を買って寮に帰るまで、時々五条先生と言葉を交わしました。そうするほどにわかるのは、彼が真面目で、生徒との距離に対して誠実であるということでした。
この人の『声』なら、私はヘッドホンをせずに聞けるかもしれない。
今はできなくても、どうしようもなく臆病でも――もっと心から、先生のことを信じることができたのなら。
◆◇◆
その後、猫は五条先生の従姉であり、寮の管理人でもある紫苑先生の知り合いに引き取られていきました。本当の飼い主が見つかるまでは、とのことです。
猫がいなくなるとき、五条先生が少しだけ寂しそうな素振りを見せたのは、私だけが気づいていたことだと思いますが――透湖と愛乃には、教えないでおこうと思います。だって、そんな話をしたら、きっと彼は照れるのでしょうから。