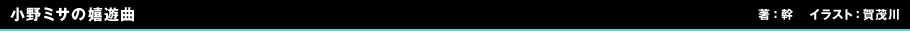コンテンツページ
「なあなあ、みんなの恋愛経験とか教えてくれへん?」
夏休みも後半のある日。
地下鉄小野駅周辺にあるミサの家に遊びに来て、彼女の部屋でくつろいでいた萌、咲、澄に、ミサがおもむろにそんなことを尋ねてくる。
さきほどからミサは自分のベッドに座って、眉をひそめながら愛用のエレキギターをアンプにつながないままつま弾きつつ、なにやらノートに書き込んでいた。
「恋愛経験って……なんでいきなりそんなこと?」
萌もミサが何をやっているのか気になっていたのだが、その質問は意外だったので目を瞬かせて尋ね返す。
同じように話を聞いていた咲と澄も、ミサのいきなりの言葉に不可解そうにしていた。
「いや、実はさ」
するとミサは、困った様子で眉を八の字にしながら答える。
「私いま、作詞してるねん」
「作詞?」
その言葉に萌、咲、澄は一様に首をかしげる。
「そう――今度さ、学校の子らと組んでるバンドで、文化祭にオリジナル曲やることになってんけど。その歌詞を考えてんねんか」
「へえ、オリジナル曲なんてすごいやんミサちゃん!」
「うん、高校生のバンドだと、たいてい有名曲をそのまま演奏するくらいだもんね。オリジナル曲やるって、本格的なんだね」
萌と澄が口々に褒めると、ミサはふふん、と自慢げに鼻をならして胸をはった。
「けどミサ、これまで作詞なんてしたことないやろ?」
「うん、せやからどうもええのが思い浮かばへんくて困ってるねん」
「まあミサは素人なんやし、出来はそう気にせんでもええんちゃう?」
「そんな訳にはいかへんよ! 私は素晴らしい詩を書く! そう――『放課後お茶時間』みたいな!」
咲の言葉に、自分の愛するガールズバンド(アニメ)の名を出し、拳をぐっと握りしめて決意を固めるミサ。しかしそれからすぐに、拝むように萌たちに両手を合わせた。
「という訳で、みんなもちょっと手伝ってくれへん? どれだけ頭ひねっても、いい詞が浮かんで来いひんねんか」
「手伝うのはええとしても、うちら作詞なんてできひんよ?」
萌が言うと、咲と澄も同意してうなずく。
「違う違う、インスピレーションのきっかけになるような話とかないかなってこと。それを聞かせてもらったら、なんかええ詞が浮かんでくるかもしれへんやん?」
「ああ、だからさっきの質問なんだね」
納得がいった、と澄が深くうなずいた。
「そうそう、やっぱ女子高生っていえば恋愛、つまりラブソングやんか? せやからみんなの恋愛経験を教えてもらおうと――」
言いかけて、ミサは萌と咲それぞれに視線を送ると、数秒何事かを考えてから、ふう、とため息を吐く。
「うん、二人はやっぱええわ」
「あ、ミサちゃんひどい!」
「どういう意味やそれ!」
「だって二人とも恋愛の経験なんてろくに無いやん」
抗議の声をあげる萌と咲を、ミサは鼻で笑った。
「う、うちはよく学校の子らから告白されるで!」
「咲、女子校やんか」
「わ、私この前、スペイン人の男の人と一緒に南禅寺に行った!」
「ええ!? ちょっ、それ詳しく――」
「どうせ道を尋ねられて案内したとかやろ。萌ってそういうこと多いし」
萌の言葉には澄が驚きの声を上げたが、しかしミサは冷静な声で指摘する。
「た、確かにそうやけど」
「なんだ、そうだったんだ。よかった」
図星を指され萌が認めると、なぜか澄が隣でほっと胸をなで下ろした。
あっさりと反論されて、萌と咲は恨めしげにミサを見る。
「だいたいそれやったらあんたも変わらんやろ!」
「わ、私は、その――この前、地下鉄四条駅の駅メンに声かけられたし!」
咲の反撃にあったミサは、慌てた様子でそう言った。
“駅メン”とは、地下鉄駅周辺の飲食店などのイケてる男性従業員のことで、地下鉄の駅の構内に写真が貼り出されていたりする。
「声かけられたって、どこで? なんて声かけられたん?」
「…………お店に行ったときに、『いらっしゃいませ』って」
咲が訊くと、ミサは気まずそうに視線を泳がせながら言った。
「普通のお店の人の挨拶やんか!」
「そ、それはそれとして!」
ごまかすように、ミサは声を張り上げる。
「とにかく、だから他の人の恋愛話を聞きたいねん。まあやっぱり萌と咲はあてにならんかったけど、大丈夫、まだ澄がおるし!」
「え、私?」
いきなり話を振られた澄は、びっくりした様子で自分を指さす。
「澄は東京の人やってんから、レディースコミックみたいな大都会の女のどろどろにただれた恋愛事情を語ってくれるはず!」
「なにその偏見!?」
「なんかあるやろ? 学校でも有名な理想のカップルやったけど実はお互い別の本命がいてそのカモフラージュやとか、金持ち学校に行ったらぼんぼんの男子四人組に目をつけられてロッカーに赤札が貼られてたとか」
「あるわけないでしょそんなこと!」
澄にすぐに否定され「ええ~、無いん~」とミサが残念そうな顔をする。
「澄だけが頼りやったのに」
「そんなことを頼りにされても」
澄は苦笑しながら息を吐く。
「もうなんでもええから、みんななんか心ときめくことって無い?」
ミサに言われた萌たちだったが、互いに顔を見合わせてから首を横に振った。そんな萌たち三人に、ミサは絶望的な表情をする。
「ああ~、結局なにも思い浮かばへん~! はあ、やっぱり私には作詞の才能なんて無いんかなあ」
突然ネガティブなことを言い始め、頭を抱えるミサ。
「もう、しゃあないなあ」
そんなミサに萌はおもむろに近づき、その両手をそっととった。そのまま引っ張って、ミサをベッドから立ち上がらせる。
「……萌?」
「それやったらミサちゃん、外に遊びに行こうよ!」
「はい? 外に遊びに?」
何を言っているのか、とミサが首をかしげる。
「いや、作詞せなあかんって言ってるやん。遊んでる暇なんてないってば」
「ううん、作詞するために遊びに行くの!」
萌の言葉に、ミサはきょとんとした顔で萌を見つめた。
「部屋の中でうなってたって、ええ詞なんてできひんって! 外に出て、いろんなものを見て、感じて、経験した方が絶対良いよ!」
「確かに、萌の言うとおりやな」
「うん、私もそう思うよ」
即座に咲と澄が同意し、どちらもミサを誘うように手を差し出す。
そんな三人の姿をしばらく見ていたミサだったが――やがてぱっと笑って言った。
「――よし、ほな行こっか!」
「そうこなくっちゃ!」
やる気を見せるミサに、萌も嬉しくなって手を叩く。
「それでどこに行く?」
「寺町三条のあたりに、面白い劇団があるみたいやからどうかな?」
「うちは祇園花月とかでもええと思うで」
「哲学の道とかどう? 風情もあるし、喫茶店とかギャラリーも多いで!」
澄に訊かれて、萌、咲、ミサの三人はそれぞれにお勧めを答える。
「じゃあとりあえずは地下鉄に乗ろっか!」
そんなことを話しながら、萌たちは部屋を後にしたのだった。
――後日。
完成したミサの詞は、女子高生の恋愛を書いたものでは無く、友達と遊びに行く楽しさを書いたものだったのだが、なかなかの好評を博したという。