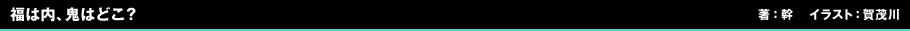コンテンツページ
「あれ、小鬼さんたちだ」
二月のある日、京都の女子高生、太秦萌、松賀咲、小野ミサ、そして白河澄の四人が地下鉄丸太町駅の構内に下りると、小さな鬼たちがたむろしていた。
萌たち四人はとある事件以来、彼らのような妖怪や精霊といった不可思議な存在を見ることが出来るようになった。
萌たちの膝ほどの小さな体に、もじゃもじゃの髪、そしてそこからそれぞれ一、二本の角を生やしている彼ら小鬼とも、その頃からの付き合いだ。
「小鬼さんたち、こんなところで何してるん?」
「ん、ああ、萌はんたちか……」
萌が声をかけると、小鬼の中の一人がどこか憂鬱そうに萌の顔を見あげてくる。
「今日はわしら、地上はどこにもいづらくてな」
「いづらいってなんで――ってそっか、今日は二月三日やん」
咲が頭の上に疑問符を浮かべたが、すぐにそれに気がついた。
「そういえばそうやったね。私も帰ったらお母さんが豆を用意してると思う」
「私の友達も、吉田神社のお祭りに行くって言うてたっけ」
「コンビニで恵方巻きも売ってたしね」
萌にミサ、澄も口々に言い合うように、神社仏閣の多い京都では、あちこちで節分の行事が催されていた。
「地上はどこも豆が撒かれてて、わしらにとっては地獄みたいなもんやねん。せやからこうして地下に避難してるんや」
萌たちにとっては節分も楽しいイベントなのだが、鬼にとっては違うようだ。
「地獄みたいなもんて、鬼やったら地獄って自分の家みたいなもんちゃうんかな?」
「ていうか鬼って、ほんとに豆が苦手なんだね」
ミサと澄で話していると、小鬼は首を横に振った。
「いや、豆自体はええんや。昔は豆やなくて米とか粟とか撒いてたりもしたからな、別に豆そのものが苦手なんや無い――問題はあの言葉や」
「言葉って『鬼は外、福は内』ってやつ?」
「そう、あの掛け声や」
萌がたずねると、小鬼はひどく深刻な声で答える。
「言霊言うて、言葉には力が宿るさかいな。そう言って投げられた豆は、確かにわしらを遠ざける効果を持つねん。この地下でも、地上では豆が撒かれてるから居心地がええわけやないねんけど、まあ地上よりはマシなんや」
その言葉どおり、小鬼たちにはいつもより元気が無いように見える。
「そっか、大変なんやね」
「まあええ、こうして今日一日わしらが我慢してればすむ話なんやから」
萌の言葉に笑う小鬼たち。しかしその声や表情はさびしげで、割り切れないものがあるようだ。そんな彼らを萌たちはそろってじっと見つめていたが、やがて――
「なんとかしてあげたいなあ」
萌が言うと、他の三人も同感だと言うようにうなずく。
「けど萌、なんか方法はあるん?」
「……ようは豆を避けて、鬼さんが避難出来るところがあればいいんやけど」
「雨宿りならぬ豆宿りやね!」
と、ミサがはしゃいだ声を上げた。
それからしばし、乗るはずだった電車が来て、それが行ってしまうくらいの時間がたってから「そういえば」と澄がぽつりと漏らす。
「なんか思いついた、澄ちゃん?」
「東京の浅草寺だとさ、観音様の前に鬼はいないからってことで『千秋万歳、福は内』とだけ言って豆を撒くんだ。京都にだってそういうところがあるんじゃないかな?」
「なるほど『鬼は外』って言ってへんところか」
澄の言葉を聞いて咲がそれに当てはまる場所を考え始めると、その隣で同じようにしていたミサが、すぐに口を開く。
「それやったら知恩院がそうやったと思う。知恩院での豆まきは『福は内』とだけ言うって、前にうちの学校の校長先生が言ってた!」
「おお、ミサナイス、それや!」
「いや、それもあかんねん。『鬼は外』って言ってへんだけやと、周りでやってたらそれに影響されてもうて、やっぱりわしらはいづらいんや」
「ううん、そっかあ。いいアイディアやと思ったんやけどなあ」
これで解決と盛り上がっていたところで鬼に否定されて、ミサたちは落胆のため息をはいたのだが、萌にはそんな彼女たちの会話を聞いて頭にひらめくものがあった。
『鬼は外』とは言わないで豆を撒くところが駄目でも、あそこならば――
「うん、あそこやったら大丈夫!」
そう言った萌は、こちらを見上げてくる小鬼たちに片眼をつむって見せるのだった。
――地下鉄今出川駅から北に二駅の、北大路駅。
そこでバスに乗り換えてから十分ほど移動して、千本鞍馬口という停留所で下りる。あたりが暗くなり始めた中を、萌が先頭に立ってみなを案内しながら歩いた。
その間、小鬼たちは確かにどこか居心地が悪そうにそわそわとしていた。
そして数分歩いたところで、萌たちはあるお寺にたどり着く。
「はい! というわけで千本ゑんま堂にやってきました!」
萌はツアーガイドよろしくそのお寺、引接寺――通称千本ゑんま堂を手で示した。節分祭が行われているのだろうそのお寺には、すでに結構な数の人々が入っている。
「というわけでって言われても」
「ここが目的地なん、萌?」
「見る限り普通のお寺だけど」
咲、ミサ、澄の三人も萌の意図が分からずに、ただのお寺に連れてこられたことに戸惑っていたのだが、しかし――
「こ、これは……」
「なんと……」
小鬼たちの反応は違った。みなが呆気に取られたような、それでいてどこか感動したような面持ちで寺を眺めながら口を開いた。
「ここはわしらを遠ざけようとしてへん! いやむしろ歓迎してくれてる!」
「こんな場所があったなんて!」
「よかった、やっぱりここやったら大丈夫なんだ!」
口々に言い合う彼らに、萌は満足そうに笑みを浮かべた。
「なあ萌、なんでこのお寺やったらええの?」
「このお寺でも狂言の奉納とか、豆撒きとかの節分の行事は行われてるけど、ここの豆まきは一つ変わったことがあるの。ここのお寺はね、豆撒きの時に『福は内、鬼は外』やなくて――『福は内、鬼も内』って言って、豆を撒くんだよ」
「あっ」「なるほど」「言霊、か」
咲、ミサ、澄の三人は納得のいった声をあげる。
「そう――このお寺は豆撒きをしてないんやなくて、鬼さんもいらっしゃい、って言って豆撒きをしてくれてるから。鬼さんにとっても居心地いいんやないかなって」
「いやあ、萌はんありがとう! こんなところ、あったんやなあ!」
「鬼のわしらでも知らんかったわ」
「さすがやわあ!」
「いやあ、どうもどうも。ここに限らず閻魔さまや鬼さんが祀られてるお寺やと、節分に鬼さんを歓迎しているお寺って実は結構あるからね!」
盛り上がった小鬼たちが萌を褒め称えると、萌もまんざらでも無さそうに彼らに対して手を振って応えながらそう伝えた。
「ほんまにありがとうな~!」
そうして小鬼たちは我先にと門をくぐり、スキップでもしそうな足取りでお寺へと入っていく。それを見送った萌たちは、そこで立ち止まって話し合った。
「さて、どうする? うちらもちょっとお寺に入ってく?」
「いや、さすがにもう帰らないといけないんじゃない?」
澄がそう答えたように、もうすでにとっぷりと日は暮れて街灯の明かりが灯っている。さすがにこれ以上、遅くなると門限を破ってしまう。
名残惜しく引接寺の門前から引き上げた萌たちは、バス停にたどり着いた。
「萌、よくあのお寺のこと知ってたなあ。うちは全然知らんかったわ」
「私は休日にはお寺とか神社、色々と行ってるからね」
ベンチに座ってバスを待っていると咲が感心した様子で言ったので、萌は照れながらそう返す。
「けどうちとかは歩いてる途中で見かけてても、素通りする場所ってのもあるしなあ」
「そういう知らない場所があるからこそ、いつも新しい発見があって楽しんだよ!」
「なるほど、それはそうやな――けど萌、知らん場所はなにも神社仏閣だけやないで!」
そこで咲が、負けていられないとばかりに不敵な笑みを浮かべて声を張り上げる。
「たとえばうちこの前、三条通りの商店街で、すっごいおいしくて安いラーメン屋見つけてんから!」
「あ、それやったら私、市役所近くでええ感じの小物のお店知ってる!」
「私もカメラ持って祇園をまわってたら、おしゃれなカフェがあったよ」
「え、行きたい行きたい!」
つぎつぎに言ってくる咲、ミサ、澄に、萌もはしゃいだ声を出した。
「それじゃ、次の休みにみんなでまわろっか!」
と、そうして四人で遊ぶ約束をしたところに、ヘッドライトをつけたバスがちょうどやってくるのだった。