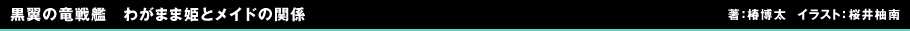コンテンツページ
アイゼンバルド王国の王女、フィーネ・エル・ラティネ・アイゼン。
美しいドレスを着た彼女は、王宮の一室でソファーに腰掛け、難しい顔で考え込んでいた。
「どうしたら、よいものか……」
フィーネは独り言をつぶやき、ため息をつく。
すると、扉がノックされ、一人のメイドがワゴンを押して入ってきた。
「姫様、お茶の用意をして参りました」
メイドが一礼し、ソファー前のテーブルに、ティーカップを置く。そして、ティーポットから紅茶を注いでいった。
「エイダよ、聞いてもよいか」
「私にお答えできることでしたら、何なりとおたずねください」
エイダと呼ばれたメイドが、フィーネに答える。
彼女の年齢は一七歳で、一二歳のフィーネより年上である。しかし、王女とメイドでは身分に天地ほどの差があり、エイダはかしこまって答えていた。
「実は、困っておっての」
「はい」
「殿方の気を引きたいのだ」
「……はい?」
「何か、よい手はないかのう」
ポカンとするエイダの前で、フィーネは深々とため息をつく。
「あ、あの……それは、姫様が片想いをしておられるということで?」
「うむ」
「お相手は、他国の王族の方でしょうか?」
「いや、この国の平民だ」
「へ、平民ですか!?」
エイダが驚き、甲高い叫び声を上げる。
「姫様が平民に懸想(けそう)を……」
「まあ、まだ会ったこともない相手なのだが」
「応援させていただきます!」
「う、うむ?」
突然エイダが真剣な顔で言い、フィーネはきょとんと首をかしげる。
「ああ、すばらしいですわ! 身分の違う恋。私、そういった話が大好きなんです!」
「そ、そうか」
「お任せください。必ず、姫様の恋を成就(じょうじゅ)させてみせます!」
エイダは目をキラキラさせ、力強く宣言する。
その様子を、フィーネはあっけに取られた表情で見ていた。
◇◇◇
「男性の心をつかむのは、やはり料理です!」
キッチンに立ったエイダが、フィーネへ話しかける。
「料理か。これまでしたことないのう」
「お相手が貴族の方でしたら手料理を振る舞う機会など無いでしょうが、平民の家には料理人などおりません。作れるようになっておいて、損はないかと」
「ふむ。個人的にも興味があるし、習うのにやぶさかではないが」
フィーネは言い、物珍しげにキッチンを見回す。
王女である彼女の食事は、普段は専属のコックが作っていた。そのため、彼女はキッチンに入ること自体が初めてで、並んでいる道具などを興味津々といった様子で見ている。
「それでは姫様、オムレツを作ってみましょう」
エイダが卵をいくつか用意し、調理台の上に置く。
「まずは、こちらのボウルに、卵の中身を取り出します。最初は私がやってみますので、見ていてください」
「それくらい、教えられずともできるぞ。貸すがよい」
「で、ですが」
エイダが困惑するが、フィーネは気にせず、卵を奪い取る。
そして、フィーネは卵を握った手を、天井に向かって高々と掲げると、次いで勢いよく振り下ろした。彼女は、調理台にあったボウルに、力強く卵を叩きつける。
「……ふむ。予想外の結果だの」
「姫様……」
叩きつけられた卵は、当然のことながら、中身を飛散させていた。卵の中身が、フィーネやエイダの顔にまで飛び散り、二人のほおや唇に滴っている。
「おかしいのう。妾(わらわ)がいつも食べている卵は、固形だったのだが」
「ですから、最初は私がやると……」
エイダは、がっくりと肩を落とす。
「卵は火を通すと、固まるのです」
「ほう、そうなのか」
「ああ、姫様のドレスまで……。とりあえず、湯浴みとお着替えの用意をして参ります」
「いや、続けてよいぞ」
「しかし……」
「ここで引き下がっては、妾の気が済まぬ」
フィーネは、きっぱりと言い放つ。
その様子に、エイダは説得をあきらめると、ため息をついた。
「では、お顔だけおふきします」
エイダは急いでキッチンを出て行くと、綺麗な白い布を持ってくる。そして、フィーネの顔についた卵を、ていねいにぬぐい取った。
そのあと、自分の顔もふき、彼女はレクチャーを再開する。
「では、もう一度やってみましょう」
エイダに促され、フィーネが再び卵を手にする。
フィーネは先ほどの失敗から学習し、優しく卵を扱うと、中身が飛び散らないように注意しながら殻を割った。それでも、まだ手慣れていないので、殻の破片がボウルに入ってしまう。
「難しいのう」
「殻を取れば大丈夫です」
エイダはボウルから卵の殻を取り除くと、次はかまどへ移動した。かまどには、すでに火が付けられ、上ではフライパンが熱せられている。
「火は危ないので、私が作り方をお見せします」
「味付けはしなくてよいのか?」
「あ」
フィーネが指摘するが、すでに卵はフライパンの中へと流し込まれた後だった。フライパンの中で固まっていく卵を見て、エイダはあたふたと慌てる。
「ああっ、油も引いてないっ」
「油なら知っておるぞ。妾が入れてやろう」
フィーネは手近にあったビンを取り、中身をフライパンに注ぐ。
それは確かに、油だった。しかし、彼女は量を考えず、ビンにあったすべての油を、ドバドバとフライパンに注いでしまう。
「ひっ、姫様!?」
ボッと油に火が付き、エイダが悲鳴を上げる。
大量の油に引火し、キッチンの天井に届くほどの大きな火柱が上がっていた。
「おおう、これはすごいのう……」
「どうしましょう……」
目の前で燃え盛る炎に、フィーネとエイダは為すすべもない。
二人は炎を前に、呆然と立ち尽くしていた。
◇◇◇
「姫様、お召し物を」
フィーネとエイダは、キッチンから移動している。
キッチンで上がった火柱は、駆けつけたコックや他のメイドによって、すぐに消し止められた。被害は壁が焦げた程度で済み、けが人も出ずに騒動は終息している。
その後、二人は卵やすすの汚れを落とそうと、浴室に来ていた。今は脱衣所で、エイダがフィーネのドレスを脱がしている。
「申し訳ありません。私が料理をお教えするなどと言わなければ……」
「気にせずともよい。あれはあれで、楽しかったぞ。それに、妾には料理は向いていないこともわかったしの」
フィーネは苦笑して答える。
そして、ドレスを脱いで裸になった彼女は、湯船へと向かった。王宮の浴室は、一面が大理石張りになっており、床に埋め込まれる形で広々とした浴槽が作られている。一人で入るには広すぎる浴槽に、フィーネはゆっくりとつかっていった。
「んー、気持ちよいの。エイダよ、そなたも入ったらどうだ?」
「そのような恐れ多いことはできません」
エイダが恐縮して返事をする。
彼女はメイド服を着たまま、湯船の近くに立っていた。王女であるフィーネの着替えや入浴は、すべてメイドの仕事であり、こうして常に近くで待機しているのが決まりだった。
「つまらぬのう」
広い湯船に一人でつかっているフィーネは、不満げな表情になる。
すると、次に彼女は、ちゃぷんとお湯の中にもぐった。
「姫様?」
エイダが声を掛けるが、フィーネはお湯から出てこない。そのことに不安を覚えたエイダは、慌てて湯船に近寄っていった。
湯船は床より低い位置にあるため、彼女は浴槽の縁に立ち、視線を巡らせる。
すると、彼女の足首に、何かが触れた。
「姫さ……きゃっ!?」
突然エイダは足首をつかまれ、バランスを崩してしまう。
そして、そのまま湯船に倒れ込んでしまった。
「ふふ、油断したの」
「姫様……」
エイダの足をつかんだフィーネが、お湯の中から現れる。
「これで、そなたも汗を流せるの」
「お戯(たわむ)れが過ぎます……」
「そう言うな。たまには、こんなのもよかろう。しかし……なかなか大きいの」
フィーネはそう言って、エイダをじっと見つめる。
メイド服を着たまま湯船に入った彼女は、服が体に張り付いていた。そのおかげで、胸の部分が強調され、フィーネはそこをまじまじと見ている。
「ふむ、さわり心地もよいな」
「え、ひっ、姫様!?」
フィーネが、もみしだくように、エイダの胸をさわる。その行動にエイダが顔を真っ赤にするが、フィーネは気にせず手を動かし続けた。
「やはり、これくらいあったほうが、殿方は嬉しいのかのう」
「やっ、あんっ」
フィーネに胸をもまれ、エイダはなまめかしい声を上げる。彼女は相手が王女ということで、振り払うことができず、我慢してフィーネの行為を受け入れていた。
「それに比べて、妾は……」
フィーネは、自分の体に視線を落とす。
そこには、ぺったんこな胸があった。
「むう、うらやましいぞ」
「姫様、ご勘弁くださいっ」
エイダが、もだえながら懇願する。
すると、ようやくフィーネは、彼女の胸から手を放した。
「妾のも、大きくならぬかのう」
「姫様は、これからが成長期ですから……」
エイダは息を整えながら答える。
そして、何とか平静を取り戻した彼女は、戸惑った表情をフィーネへ向けた。
「あの、このようなことを、お聞きしても良いのかわかりませんが……」
「よいぞ、申せ」
「何か、心苦しいことでもありましたでしょうか? 今日の姫様は、いつものおしとやかなお姿とは、あまりに……」
エイダは、言葉を濁しながら問い掛ける。
一方のフィーネは、すぐには答えない。彼女は暗い表情になり、顔をうつむけた。
「……明日、王宮に来るのだ」
しばらくし、フィーネは、ぽつりとつぶやく。
「来る……とは、どなたがですか?」
「先ほど話しておった、妾の想い人だ」
「平民とうかがってましたが……。姫様が招待されたのですか?」
「いや。その者は、王立騎士学院に通っておっての。授業の一環で、見学に来るらしい」
フィーネは湯に身を沈めながら、瞳を水面に向ける。
彼女の瞳は、波紋が広がる水面と同じように、揺れていた。
「明日、会えるかもしれぬと思うと、落ち着かなくての」
「そういえば、まだお会いしたことがないと、おっしゃっていましたが……。会ったこともない平民を、なぜそれほどまでに……」
「今は、多くは語れぬ。だが、その者は、妾にとっての希望だ」
「希望……?」
「ゆえに、怖い。明日会ったとき、もし拒絶されたらと思うと、怖いのだ」
「姫様……」
不安げに表情を曇らせるフィーネを、エイダは心配そうに見つめる。
すると、フィーネは水面から視線を外し、エイダへ顔を向けた。
「そなたに一つ頼みがあるのだが、よいか?」
「はい。何なりとお申しつけください」
エイダは即答する。
思い悩む主(あるじ)のために、彼女はどのような頼みごとでもこなしてみせると、心に決めていた。
◇◇◇
「あっ、やんっ。姫様、そのようなところを、さわっては……」
エイダがベッドの上でもだえる。
「よいではないか」
「だっ、ダメですぅっ」
「これが気持ちよいのだ」
時刻は夜で、エイダはフィーネの寝室に連れてこられていた。二人はキングサイズの立派なベッドの上で、抱き合うように寝ている。
「うむ、落ち着くのう」
フィーネはネグリジェに着替えており、エイダの胸に顔をうずめるように抱きついていた。エイダの胸を枕のように使い、フィーネは満足げに微笑んでいる。
一方、エイダも寝間着に着替えていた。彼女はラフなワンピース姿で、くすぐったそうに身をよじっていた。
「ううう……。やっぱり、今日の姫様は、おかしいですぅ……」
「妾が寝つくまででよいから、このままでおらせよ」
フィーネの頼みごととは、添い寝だった。そのためエイダは、フィーネのベッドで、並んで寝ている。
「本当にこれで、よくお眠りになれるのですか?」
「一人で居ると、余計なことを考えてしまうからの。話し相手になってもらえると助かる」
「姫様がよろしいのであれば、構いませんが……」
エイダは嘆息しつつ、フィーネを受け入れる。フィーネにさわられるのも、ようやく慣れ、彼女は静かにベッドに横になった。
そして、しばしの間、静寂が訪れる。
「……久方ぶりだ」
「はい?」
フィーネが静寂を破り、エイダは眉をひそめる。
「母上が死んでから、こうして誰かといっしょに寝ることはなかったと思っての」
「…………」
「父上や兄上は、妾に興味がないからのう」
フィーネは笑いながら話す。
だが、その微笑みは、どこか硬かった。
「お寂しい……のですね」
「さて。母上が死んだときは悲しく思ったが、父上と兄上に関しては、もはや期待してはおらぬからの。妾としても、考え方が違いすぎるあの二人とは、積極的に話したいとは思わぬし」
フィーネは苦笑して答える。
「それに、さっきも言ったように、妾には希望がある。明日、あの者と親しく……いや、せめて一言でも言葉を交わせるとよいのだが」
「姫様は、それほどまでに、その方のことを……」
「だから、今の気持ちとしては、緊張しているというのが正直なところかの。明日が来るのが楽しみで、怖いのだ」
フィーネはそう言うと、エイダの体に腕を回し、強く抱きついていった。
「眠りにつくまで、こうしておってよいか?」
「……はい、姫様」
エイダも微笑み、フィーネの体を引き寄せる。
ベッドの上で、王女とメイドが、抱き締め合う。
そうして、夜は更けていった。
◇◇◇
王宮の敷地内で、もっとも立派な建物である、中央宮殿。
今、その宮殿の廊下を、少年たちが歩いていた。数十人の少年たちは、白を基調とした制服を着ており、宮殿の中を見学しながら進んでいる。
「姫様、姫様っ。学院の方々が来ました!」
その一団を、物陰からメイド服姿のエイダが覗いていた。彼女は、生徒たちから少し離れた場所にある柱の陰に隠れ、様子をうかがっている。
「うむ、わかっておる」
そんな彼女に、フィーネは硬い表情で答える。彼女はピンク色の美しいドレスを着て、エイダと同じように、生徒の集団を見ていた。
同じベッドで就寝した二人は、翌朝、中央宮殿へ来ている。エイダは生徒たちを前にして興奮気味だったが、フィーネは異なり、緊張した表情をしていた。
「それで、姫様の想い人というのは、どの方ですか?」
「見れば、すぐわかるはずだが」
そう言って、フィーネは生徒のほうを凝視する。
そして、一人の少年に目を留めた。
「あれだ。む、足を止めたぞ?」
フィーネが眉をひそめる。
彼女が目を付けた少年は、なぜか足を止め、集団から離れてしまっていた。見学をしている生徒たちは先へ進んでいき、その少年は廊下で一人になってしまう。
「むう、何かあったのかのう」
「ひ、姫様……。あの方が、姫様の想い人なのですか?」
「うむ、そうだ」
「で、ですが、あれは忌(い)み……」
「それ以上は言わなくてよい」
エイダの言葉を、フィーネは鋭い声で遮る。
「そなたが言いたいことはわかる。だが、妾は、その呼び方は好かぬ」
「…………」
「移動するようだ。こちらも追いかけるかの」
目当ての少年が一人で廊下を進み出し、フィーネが追っていく。その後ろを、エイダも無言でついていった。
「……この辺りでよいか」
少年を追いかけて来た二人は、宮殿内にある中庭へと来ていた。どうやら、少年は道に迷ってしまったようで、困り顔できょろきょろと周囲を見回している。
それを確認したフィーネは、中庭に作られた渡り廊下で立ち止まり、深呼吸をした。
「ふぅ……。これほど緊張するのは、いつぶりかの」
「……姫様」
「妾の気は変わらぬぞ」
「いえ、お止めする気はありません」
エイダは首を振り、真剣な顔でフィーネを見つめる。
「私は、姫様のメイドです。ですから、どのような状況でも、姫様の味方です。どうか、後悔の無きよう、行動くださいませ」
「…………」
その言葉を聞いたフィーネは、正面からエイダを見返す。
そして、ふっと微笑みかけた。
「苦労をかけるの」
「いえ。姫様にお仕えすることが、私のつとめですから」
「そうか。では、妾も望むがまま、行動するとしよう」
フィーネはそう言うと、視線を少年へと向けた。
「あの者とは、妾だけで話をしたい。そなたは、ここで待っておれ」
「かしこまりました」
「では、行ってくる」
頭を下げるエイダを残し、フィーネは歩き出す。
進む先に待っているのは、黒髪黒眼の少年。
フィーネは、微笑を浮かべると、弾むような声で、その少年へと話しかけた。
「ここで、何をしておるのだ?」