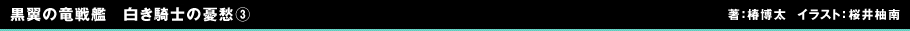コンテンツページ
前方の廊下を、少女が歩いてきている。
それは、シルクのような美しい金髪の少女。
年齢はユミリアより年下で、一二歳前後だろうか。小柄で、愛くるしい顔立ちの少女は、ピンク色の豪奢(ごうしゃ)なドレスで着飾っている。また、その姿は気品に溢れており、しずしずと二人へ近づいてきていた。
「これは、珍しいの。ノイブルク家の親子が揃っておるのか」
「フィーネ竜姫爵(りゅうきしゃく)、ごぶさたしております」
微笑を浮かべて話しかけてきた少女に、ドラギオルが深々と頭を下げる。一方、隣では、ユミリアもうやうやしくお辞儀をしていた。
その少女の名は、フィーネ・エル・ラティネ・アイゼン。アイゼンバルド王国の王女にして、竜姫爵の爵位を持つ少女だった。
「そなたらは、めったに王宮に姿を見せぬからのう。妾(わらわ)は寂しいぞ」
「恐縮です」
「そうそう、ユミリアの活躍、妾も聞いたぞ。たった一人で、帝国軍を蹴散らしたそうだの。さすがは王国最強と名高い、白翼の騎士だ」
「お褒めの言葉をいただき、光栄です。娘も喜んでおります」
「ローレン帝国は、失われた先史文明の兵器を復活させた、強大な侵略国家だ。これからも、そなたらの力が必要となるであろう。どうか、この国のために、尽力してくれ」
フィーネはドラギオルに、にっこりと笑いかける。
そして、次にユミリアへ視線を向けた。
「ユミリアよ。戦場は大変であろうが、頼むぞ」
「はい」
「おお、そうだ。そなたに会ったら、聞きたいことがあったのだが、よいか?」
「何でしょうか?」
ユミリアが、いぶかしげな表情になる。
一方のフィーネは、微笑を崩さず、言葉を続けた。
「最近、そなたを平民街で見かけたという噂を聞いたのだが、本当かの?」
「――――っ」
ユミリアが息を呑む。
だが、すぐに彼女は平静を装うと、前髪で表情を隠すように頭を下げた。
「人違いかと」
「ふむ。まあ、そうであろうな。貴族であるそなたが、そのような場所に用があるはずもなかろう」
フィーネは、あっさりと納得する。
「おかしなことを聞いて、すまなかったの」
「いえ……」
「このわびに、今度、茶会にでも招待しよう。以前から、そなたとは、ゆっくりと話がしたいと思っておったしの。ドラギオル、そなたもどうだ?」
「酒があるなら行きますが」
「ふふ。では、近いうちに、また会おうぞ」
フィーネは会釈し、歩き出す。彼女は優雅な足取りで遠ざかっていき、廊下にはユミリアとドラギオルの二人だけになった。
「ふう、やれやれ」
「さっきの質問……」
「ん?」
ドラギオルが眉をひそめて、ユミリアを見る。
「どうして、あんなこと聞いたのかしら」
「家に帰るところを、誰かに見られてたんだろうな。ま、確証は無いみたいだし、大丈夫だろ」
「そうならいいけど……」
「不安になるのも、わかるがな。何せ、フィーネ竜姫爵は、アレスの……」
「ちょっと!」
「ぐえっ」
ユミリアの肘鉄(ひじてつ)が、ドラギオルの腹に突き刺さり、うめき声が上がる。
「こんな場所で、変なこと言わないで。誰かに聞かれたら、どうするのよ」
「お前、父親に……」
ドラギオルが顔をしかめる。
一方、ユミリアは気にした様子を見せない。
「とにかく、これからは家に帰るのも慎重にしないと。お父さんも気をつけてよね」
「わかったよ」
「それじゃ、わたしは戻るわ。アーくんも学校が終わるころだし。お父さん、晩ごはんは?」
「飲んで帰るから、いらん」
「あんまり飲み過ぎないでよ」
ユミリアはため息をつき、廊下を歩き出す。
そして、ドラギオルを残し、一人で王宮の出口へと向かっていった。