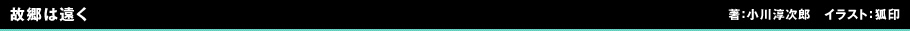コンテンツページ
神楽は日本にいたころ、海をよく見ていた。
登校中の朝、学校の昼休み、放課後。
海をよく見ていた。
その都度思っていた。
「夢より現実のほうがひどいな……」
まだ日が昇っていない時間帯のモルニア。
アーニャの屋敷にある客間、そこのベッドに神楽が横になっている。身体を丸めてすやすやと静かに眠っていた。
まだ野鳥が目覚めたばかり。アーニャが店を開けるのも数時間ほどあとのことだ。あとしばらくは、彼もこのまま眠っている。そのはずだが、訪問者があった。
小さな女の子である。音もなく客間に入ってきて、神楽が眠るベッドに近寄ってきた。
アーニャ、ではない。
その少女は黒かった。長い黒髪に黒い肌、瞳だけが金色であり、
身につけているのは若干透けてしまっているほどの薄手のワンピースだけであった。
靴も靴下も、下着すら着けていない。
そんな彼女は小さく微笑み、静かに神楽の眠るベッドに上がった。
そうして、神楽の顔を数秒ほど見下ろすと、大きく口を開いた。
そこには牙があった。人にはあるはずのない牙。
ぽた、ぽたと先端から白い液体が滴り落ちている。
「はあ……っ」
少女は舌なめずりをする。
そのしぐさはとても妖艶で、男も女も誰もがぞくりと身を震わせるものであった。
少女の視線は神楽の首筋に注がれている。
ゆっくり、ゆっくりと身体を下げていき、その牙を神楽の頸動脈に近づけていく。
しかし、寸前である。
ぷつっと皮膚に刺さる寸前、大きな手が少女の頭を掴んだ。
神楽である。寝ぼけ眼だが、不快そうに眉を顰めて身体を起こした。
ベッドがギシリときしむ。
少女は頭を掴まれていながらも、弾むような声であいさつをする。
「やあっ。おはよん、カグラくんっ」
呼ばれた神楽は返事をしなかった。
ただ、不快そうにうなった。
「暑いんだ。オルガ、お前は」
そう言って、ベッドから床に足を下ろして、しっかり踏みしめて、投げた。
神楽はオルガと呼んだ少女を窓に向かって放り投げた。
「ぎにゃああああ!」
軽々と野球のボールみたく飛んで、オルガは窓を突き破った。
常人であれば大怪我は確実だが、一度部屋に涼しい風が吹き込んだあと、ひょっこりオルガは窓下から顔を出してきた。
頬をぷっくりふくらませている。
「扱いがひっどいわよー、カグラくん。優しくしてよー、こーんな可愛い女の子なんだからさあ。ねっ?」
可愛らしくオルガは小首を傾げた。
ちょうど日が昇ってきて、オルガの黒髪がキラキラと輝いていた。絵本から飛び出してきたようなお姫様みたいである。
だが、神楽は無視をしてベッドに潜り込んだ。
「ちょっと! へいへい! 寝ないで寝ないでカグラくん!」
オルガは部屋に舞い戻ってきた。
ガラス片を踏みつけるも怪我はなく、汚れることもなかった。
「起きて起きて、カグラくん。ねえねえ、今回は暇つぶしにきたってわけじゃないの。ちゃんとした理由があるのよ、カグラくん」
寝ようとしても激しく揺さぶられた神楽は、億劫そうに頭をもたげる。
そこで、じっとオルガの顔を見つめて、すんすんと鼻を鳴らした。
「……臭いがないなあ。いつもの、くさいのが」
「今日は呑んでないわよん。とっても大事なお仕事があるから」
「そう。んー……じゃあ、とりあえず、あっちを説得して」
神楽はオルガから視線を外し、客間の入り口を見た。
廊下に出る扉が開いており、寝巻き姿のアーニャが立っていた。
可愛らしい顔であるのに、ギリギリ歯ぎしりをして歪ませている。両方の拳を強く握りしめ、ぶるぶる震わせていた。
アーニャはバヂッ、バヂヂッと、全身から漏電させながら部屋に入ってきた。
対するオルガは早々にベッドから降りると、明るい笑顔で話しかける。
「おっはよん。アーニャちゃん」
「――出ていけバカ姉ぇ!」
アーニャは怒声とともに全身から稲妻を撃ち放つ。
常人ならショック死する強さの稲妻である。眩い閃光が客間を満たし、轟音が鳴り響く。
だが、姉と呼ばれた少女、オルガは涼やかに笑っていた。
彼女の指先から黒いモヤが放出されていて、それがアーニャの稲妻をかき消している。
だが、神楽のことは守ってくれなかった。
「あガガガガッ!」
稲妻、その余波で大いにしびれる神楽だが、どっちも気に留めてなかった。
やがて、アーニャが根負けして稲妻が途切れた。
客間はあちこち黒焦げ、ベッドも一部が燃えてしまっていた。神楽は長時間しびれたのでぐったりとなっている。髪もちりちりパーマがかかっていた。
さすがにアーニャもぜえぜえと肩で息をしている。しかしオルガといえば、変わらなかった。にこやかに笑っている。
「んもう、乱暴者ねえ。汚れちゃうじゃないのよん」
そんなことを言っているが、オルガには汚れ一つなかった。縦横無尽に暴れまわった稲妻は彼女に届かず、肌や髪、服も焦げていなかった。彼女の半径三〇センチだけは綺麗なものだった。
オルガはやれやれと大げさにため息をつくとアーニャに歩み寄っていき、そっと手を伸ばした。
そして、アーニャのほっぺたをつまんだ。
「んぎい! ひゃ、はなせぇ! はなせ外道! ちくしょう! サイテー女ぁ!」
「口が悪いわよん。アーニャちゃん」
ぐにぐにオルガはアーニャのほっぺを縦横にひっぱっていく。アーニャも抵抗しているのだが、まったくかなわなかった。
「やぁめ、やめんかぁ!」
「ダメよん。ちゃーんと、ごめんなさいお姉ちゃんって謝るまではね。おほほほほ」
「じぇーったい、言わない……!」
アーニャは真っ赤な顔でオルガを睨んでいる。
二人は姉妹である。オルガが姉で、アーニャが妹。
見ての通りアーニャが一方的に嫌っている。いまも完全に敗北状態だが決して頭を垂れることも、口だけの謝罪もない。意地を張って、真っ赤な顔でオルガを睨んでいる。
このままでは昇った朝日がそのまま夕日になっても終わりそうにはなかったので、神楽が声をかけた。
「オルガ、俺になにか用があったんじゃあないの?」
「そうなのよん、カグラくん」
パッとアーニャから手を離して、オルガは神楽に振り向いた。
「ちょーっとね、大事な用件なのよ。遠い遠いところにカグラくんを連れていかなくちゃいけなくなったの。そんなわけで借りるわね」
「誰が貸してやるものか! 帰れ帰れ! 一人でいけ!」
頬を押さえてアーニャは怒鳴っているが、オルガは笑顔を崩さない。
「残念ながら拒否権はないのよん。お姉ちゃんはつよーいもん」
そう言うと、全身、髪や手、つま先から黒いモヤを生み出していった。
どっと神楽の肌に汗が浮かんできた。前髪が額にぺたりと張り付いている。
姉であるオルガも当然、吸血鬼。それでいて、稲妻ではない別の力を持っている。
それが彼女が出す黒いモヤである。
神楽は汗を拭いながら言った。
「火事になるからやめろ」
「甘いわよん。火事なんかにはならないわ。灰になるから、一気にね」
オルガは黒いモヤを壁に放った。
衝突しても消えることはなく、そのまま突き抜けていく。
ぽっかりと穴ができて、さらさらとした細かな灰だけが残っている。
オルガの力。それは炎である。
「人の家になにするかあ!」
アーニャが怒りの抗議。実に真っ当である。
「もう許さん! 絶対に許さん! 窓を割るわ、壁に穴開けるわ、人に物を頼むのならもっと誠実に頼まんかあ!」
「窓はカグラくんなんだけどね」
「知っている! とにかく許さん! でていけ! でていけでていけでていけ! でていけええ!」
酸欠でアーニャは顔を真っ赤にしていた。
オルガも困ったように唇をへの字に曲げた。この調子ではいくら神楽がいくといっても許可してくれないだろう。
だが、オルガにはまだまだ奥の手があった。
「しかたないわねん。カモン!」
パンパンと手を叩くと、窓の外から若い男が顔を出してきた。
見覚えのある男だった。
神楽より先にアーニャが名前を呼んだ。
「……ボリス!? なんでここにいるんだ!?」
「お久しぶりでございます……。稲妻姫、カメラカグラ。彼女、黒女皇には、私が頼んだのでございます」
ボリス。以前、神楽とアーニャがとっちめた男だ。
ナヴァリナという都市を治めるレオンチェフ家の当主だったが、身勝手な動機で近隣の村に侵攻し、仲裁役をかってでたアーニャにも剣を向けたので、私闘と置き換えて制裁した。
その後は隠居して、おとなしく暮らしているはずだったのだが。
「頼みって、なんだ。神楽を必要とする? 大災害でもあったのか? 救助とか必要だったりするのか?」
崩落事故とかなら、神楽も非常に役立つ。
アーニャはそう考えたのだろうが、ボリスは否定した。
「そうではありません。状況は、私がやらかしたことと酷似しております」
「酷似? ナヴァリナが封じ込めにでもあったのか」
ボリスは沈痛な面持ちでうなずいた。
「二日前、ナヴァリナの海に艦隊が展開され、交易も漁業もできなくなりました。まもなく、ツポーレ商会も事態を把握しましょうが、彼らに解決できることではありません。要求がなにかと尋ねますと……」
そこでボリスは話に参加していない神楽に目を向ける。
「彼を、カイジュウを連れてこいとのことでした」
結局、アーニャも折れた。
彼女は実の姉、オルガ・シムレアをかなり嫌っている。細々としたものが積み重なってとか、生理的にとかではなく、憎悪の領域に入っている。
しかし、元々がボリスの頼みとなれば話は別だった。
頭を落ち着かせて、ナヴァリナ、ボリスが暮らす港湾都市を封じ込めている謎の艦隊からの要求、その真意を探った。
考えるまでもなく、アーニャはすぐさま一つの結論にたどりつく。
「……本当の狙いはここ、モルニアだな」
「はい。そう思われます」
ボリスも同意した。
というのも、神楽、亀楽神楽(かめらかぐら)。彼はカイジュウ、怪獣と呼ばれるだけのことはあり、一騎当千、一騎当万の力がある。
その巨人と言っても差し支えのない体格、さらには巨大化という特性を活かして縦横無尽に暴れ回れば止められるのはアーニャかオルガくらいだ。
それを引き離せば、モルニアの守りは当然弱くなる。非常に。
兵隊がいるにはいるが、ハッキリ言って役に立たない。練度が低く、傭兵くずれの盗賊にも後れをとる始末だ。
無論、これまではアーニャがいて、その稲妻に誰も逆らおうとはしてこなかった。
だが、今回のように神楽が呼び出されたら、必然アーニャもついていかなければならなかった。
神楽のような迷い人は、実は単独で生きられない重大な欠陥がある。環境の違いだ。
世界が違えば大気組成も違う。空気そのものが毒になるのか、迷い人は重病にかかったみたいに非常に弱ってしまう。神楽も例外ではなかった。
それを治癒できるのは吸血鬼だけである。神楽はアーニャに血を注がれることでこの世界の環境に適応し、日本にいたころと変わりない行動ができるようになった。
だが、その効果の範囲は極めて限定的。その、血を注いでくれた吸血鬼の近くにいなければ効果が切れてしまうのだ。
そのため、神楽がボリスの暮らす都市ナヴァリナに向かうのならアーニャも同行することとなってしまい、モルニアは、がら空きとなる。
仮にどこかの兵隊が襲ってきたりしたら、一週間と経たず占拠されてしまうだろう。
今回はなにがどうなるかわからない。一日で終わるかもしれないが、もしかしたら長々と拘束されるかもしれない。もしくは、なんらかの罠があるかも。
おとなしくしたがうのは、危険極まりなかった。
しかし、神楽を呼び寄せろという要求を受けたボリスも元当主。才覚はあり、この狙いを看破し、裏技を思いついた。
「オルガ様、黒女皇がいれば問題はないでしょう」
オルガも吸血鬼。彼女から血を注がれたら、アーニャから離れていても神楽は弱ったりしない。
一応、オルガからは別案も提示された。
「もちろん、私がここに残って、アーニャちゃんがカグラくんと一緒にナヴァリナに向かったっていいわよん」
アーニャは絶叫するかのように拒否した。
「断わる! ケダモノの口に我が子を放り込む母がいるか!」
「アーニャちゃん、ストレートにひどいわね。お姉ちゃんをケダモノって……」
我が子とはモルニアのこと。元々ここには街などなく、アーニャが生きていくうちに徐々に人が集まり、村ができて街になり、城郭都市になったのだ。彼女にしてみたら我が子のようなものだろう。
苦虫を噛み潰したような表情で、アーニャは言った。
「神楽、非常に、かなり、尋常じゃなく、不快で、不愉快で、腸が煮えくり返っているが、オルガと一緒にナヴァリナに向かえ」
長い前置きだった。
神楽も異論はなく、引き受けた。
そこでオルガがにんまりとほほ笑んで、牙をむき出しにする。
「というわけで、噛むわよ!」
「もう噛んだだろう!」
オルガが神楽に飛びかかろうとするのをアーニャが防ぐ。
事実、神楽は以前オルガに噛まれたことがある。彼女の血は熱かった。
しばらく争っていたが、稲妻が品切れになったアーニャが敵うわけもなく、神楽はオルガに噛みつかれた。やっぱり熱かった。
その後、アーニャにも噛まれた。痛かった。
「マーキングかい……」
神楽はぼやいて、マントを羽織る。
そしてボリス、オルガとともに出発した。
別れるときまでアーニャはオルガを睨みつけていた。
ボリスが御者を務め、二頭仕立ての馬車で街道を走る。
神楽とオルガは荷台で朝食を食べ、数時間ほど変化のない光景をぼけーっと眺めていた。
それにも飽きたので、神楽は馬を軽快に走らせるボリスに声をかけた。
「どこの人だとか、予想はできてるの?」
「はい。確定してます。私に支援をしてきた都市のものです」
声音から察するに、ボリスには神楽への恐れなどないようである。
客間で再会したときにも感じたことだが、どことなく憑き物が落ちたような感じである。
「支援ってことは、タケマの村のときは独断じゃあなかったのか」
「野心は自前ですがね。装備を整え、兵を動員させるのは、父も健在でしたから不可能です。お金もいりますしね」
「あー……」
神楽もあのときの光景を思い出す。
ボリスたちは天幕も張っていた。ということは、食料も用意していてしばらくは過ごせるはずだった。多大な資金が必要になる。勝手に使える金額ではないのだろう。
「アーニャも言ってたような気がするなあ。なんか、支援があったとかなんとか」
「ええ。支援がありました。自由に使え。応援するぞと。利用されてるってわかってましたが、俺ならその支援者の予想を超えて、逆に利用してやれるって、慢心してました」
「……まあ、ツェツィの部下が足止め食らってなかったら、俺とアーニャも間に合わなかったしなあ」
ボリスの暴走を止めることができたのは偶然でしかなかった。
そんな話をしていると、景色がゆっくりと変わってきた。
海にやってきた。なにもない砂浜を街道から見下ろすことができる。
潮風が心地よかったが、徐々に不穏な空気が漂ってくる。というのも、沖合に何隻もの船があったのだ。
漁船ではない。マストをつけた大きな船が何隻もある。帆があるが、いまは張っておらず、錨を下ろして静かに浮かんでいる。
映画で見た海賊船そっくりだ。違いはドクロマークが見当たらないこと、大砲がないことくらいである。
すべてが同じ方向に船首を向けている。
そこには、岬に半ばはみ出した都市があった。
まだ遠いが、モルニアよりも規模が大きいとわかる。港という立地もあり、交易が盛んなのだろう。
ボリスがいったん馬を止め、神楽に説明する。
「あの都市が、私の暮らす港湾都市ナヴァリナ。交易と漁業が主な産業ですが、あの艦隊によってそれを阻まれています」
神楽は艦隊のほうを向き、双眼鏡を使って覗き込んだ。
甲板に船員がいて、ブラシで掃除をしている。着ている服は白を基調として襟や袖に水色の縞模様がある、いわゆるセーラー服だ。スカートじゃなく、ズボン。
「私にも見せてよ、カグラくん」
オルガに双眼鏡を奪われる。
彼女は神楽の肩にひょいっと飛び乗って、ふんふふーんと鼻歌混じりに観察をしていく。そして、ある一隻の船だけを見るようになる。
「……あれっぽいわねん」
「なにが?」
「あの船に、一番偉いのがいるわ。ほら、あそこ」
オルガが指差す先。双眼鏡を戻してもらってよく覗きこむと、ほかの船員とは違った黒い服を着た男がいた。
甲板にいるが掃除をせず、椅子に座って一人で酒を呑んでいる。
あからさまに偉そうだ。
神楽はボリスに尋ねた。
「要求を出してきたのは、黒い服の男なの?」
「ええ。艦隊の隊長と言ってました。とりあえずナヴァリナへ向かいましょう。そこに到着してから、要求通りに連れてきたと連絡を出して……」
「いや、連絡は俺が出しますよ」
そう言うと神楽は双眼鏡を懐に収めた。
ボリスはどういうことかと首を傾げる。
「船なら出しますが……」
「石があればいいよ。港でこっちから呼びだそう」
さっぱりわけがわからないといった顔であったが、ボリスは馬にムチを入れてナヴァリナに走らせた。
オルガが肩から降りて、輝かんばかりの笑顔で尋ねてくる。
「なにする気ー? どーんな楽しいことーん?」
「宴会芸するだけだよ」
神楽は端的に答えただけだが、オルガはとってもわくわくしていた。
「わくわく! わくわく!」
口で言っているのでわかる。
ナヴァリナでは数名の男が待っていた。
ボリスの家の召使であるらしい。ボリスは馬車を彼らに預け、神楽の頼みを伝える。
「えーと、石を用意してくれ。大きさは……」
「拳大くらいで、たくさんお願いします」
荷台から降りた神楽が言うと、召使たちは一歩後ろに下がって、震えながら了承し、逃げるように馬車を引いていった。
モルニアではないので、ついうっかり背中を曲げるのを忘れていた。神楽はがっくりと肩を落とす。
「……慣れてるけど、慣れない」
「なんとなーく、意味はわかるわねん」
オルガはケラケラ笑っている。
ボリスも顔をひきつらせていた。
「えー……、それじゃあ、こっちへいきましょう」
ボリスが先導し、三人で街を歩いていく。
港町だけあり、潮の香りが充満している。人口が多いのか五階建てや六階建ての建物が多く並び、一階部分では商店が並んでいた。賑わっていたであろうことを想像させる。
過去形なのは、現在、どの店も閉まっているからだ。
街の住人は明るいが、ところどころに苦い表情でため息をつくものも見受けられる。イライラしてゴミに当たり散らしているものもいた。
「まだそこまで苦しんではいないなあ」
神楽のつぶやきは思いの外、大きなものだったか、通りすがりの人たちが顔を向けてくる。そして、毎度のことだが、ぎょっと仰(の)け反る。
こうやって心が動く分、余裕はあるようだ。
やがて三人は港に到着する。神楽が希望した場所だ。彼が思った通り、ここなら船団の姿がよく見える。
トンビかなにかが空を飛んでいるが、舞い降りてはこない。かっさらう食い物がないからだ。
ここには立派な漁船、商船がぎっしりと並んでいるが、ただそれだけ。人がいない。水揚げがなく、活気がなかった。
ボリスが尋ねてきた。
「ここで、どうするんです?」
「まあまあ、見てのお楽しみ」
神楽はマントを脱いで、待った。
少しして、ボリスの召使たちが石ころを持ってきた。神楽の注文通りの大きさだ。
「じゃ、呼びだそうか」
神楽はその石を掴み、埠頭に立って船団を眺めた。
足元を確かめ、数歩下がる。
オルガの期待の視線を受けてつぶやく。
「宴会芸……」
亀楽神楽は日本人。
日本にいたころからすでにこの体格、二メートル五〇センチの身長。二二〇キロの体重だった。
力も強く、運動神経も抜群で、オリンピックへの出場をいまかいまかと待ち望まれていた。実際、レスリングや柔道など、複数の競技への出場案があったくらいだ。
しかし、彼自身に興味はなく、年に数回顔を合わせる親戚の子たちをどうやってもてなすかばかり考えていた。
それで生まれたのが、筋肉を使った芸だった。
「一〇八の筋肉芸のひとーつ……」
その筋肉芸は無数に思いつくので適当に一〇八と言っている。甥っ子や姪っ子、従兄弟たちに大好評だった。
そして、迷い人となってアーニャに保護され、巨大化という特性を得てパワーアップ。
神楽は石を掴んだまま大きく腕を振りかぶる。
そのとき、彼の全身が膨張した。
足から腰、腰から背中、背中から肩、肩から腕。
身長も高くなっていた。体重も、おそらくは三〇〇キロを超えただろう。
神楽は左足を高々と掲げる。
その一連の動作、迷い人、ドクならば一目でわかった。
野球のピッチャーだった。
「大・遠・投!」
掲げた左足をずぅんっと踏み下ろし、上半身を前に引き寄せ、投石した。
石は風を切って、甲高い唸りをあげた。
弓矢の速度を、距離をはるかに超えて飛んでいく。
そして、船のマストをぶちぬいた。
「――――ひゃーっはっはっは! ぶひゃあーっ、はっはっは!」
オルガが腹を抱えて笑っていた。
ボリスと石を持ってきた召使たちは腰を抜かしていた。
「と、投石機でもあんな飛びませんぞ……」
「怪獣だからなあ。さーて、そんじゃあ第二投、いっくぞー」
神楽はまた石を拾い、再び筋肉を膨張させ、投げた。
石の軌道は山なりではなく直線。
まっすぐ、勢いを殺さずに再び船のマストをぶちぬいた。
さっきと同じ船。偉そうな男が乗っていた船である。
「あっはっはっは! すっごーい! オルガちゃん大感激! 昇天しちゃいそう! ボリス、もっと人を呼びなさいな! こんなの私らが独占するにはもったいない!」
「わ、わかりました」
ボリスと召使は埠頭から出て人集めに奔走した。
大きな声で呼びかけていくと、仕事が無いのでひまだったのだろう。ぞろぞろ集まってきた。
そんな彼らの前で神楽は石を投げる。
投げる。
投げる。
投げまくる。
百発百中、外れはない。
港を封じ込めている船のマストをぶちぬいていく。二発ならともかく、三発当たったら折れてしまったので、対象を別の船に変えて、また投げる。
「兄ちゃんすげー」
一投ずつに歓声と拍手が起こる。
神楽はたまった鬱憤のはけ口になっている。相当困窮する未来が見えていたのだろう。子どもよりも、仕事ができなくなっていた男たちが一番盛り上がっていた。
「なんだか、昔みたいだな」
小さく神楽の口元に笑みが浮かんだ。楽しくなってきてついつい力が入ってしまう。
しかし、さすがに船団の方も行動してきた。
白旗を立てた小舟を出してきた。オルガが指さした。
「カグラくん。あれはやんないの?」
「や、やめてくれ、それは!」
ボリスが慌てて止めに入る。
「白旗を上げてるのに攻撃したら交渉もなにもあったもんじゃない! みんなも攻撃するなよ! 絶対するなよ!」
「はーい」
神楽と観衆たちが同意した。
小舟は警戒しているのかゆっくりだったが、着実に神楽たちのところにやってきた。
乗っているのは黒い服の男。部下を漕手にして自分は酒を呑んでいる。
それなりに歳を重ねた男。目つきは鋭く、しっかり神楽を見据えていた。
男は埠頭に上がってこず、神楽たちの手前で小舟を止めた。
「よぉ、ちゃーんと呼んでくれたみたいだなあ。そいつ、カイジュウを。でっかいやつだ」
陽気に話しかけてきたが、答えるのは神楽ではなくボリスである。
「望んだとおり、モルニアにて稲妻姫が保護している男を連れてきた。カイジュウ、カメラカグラだ。用件は満たしたぞ」
堂々とした立ち居振る舞いだ。
目と声に力がある。元当主としての貫禄だろう。
「約束を果たした。この街の包囲を解き、撤退しろ」
「ああ、わかってる。わかっておりますとも。このルイス、キャプテン・ルイス。しっかり約束を守りましょう。うちの船団を引き上げさせる。ただ――」
そのルイスは神楽に視線を向ける。巨体に物怖じする気配はない。
「そちらのカイジュウには私の船に乗船していただきたい。できましたら、いますぐにでも。そもそも、お話がしたくてお呼びしたのだからね。拒否をされましたら、引き上げることはできません」
ルイスという男は明るく、なにも悪いことをしてないように振る舞った。
半端ない度胸がある。ここで神楽がノーと返事をし、飛び掛かればそれで終わり。観衆がいるのでこの場で袋叩きにされかねない。
神楽は一つ質問した。
「話って、なに。乗る前に教えてよ」
「ああ、別になんでもないお話さあ」
ルイスはもったいぶるような言い方をする。
「そう、親睦を深めたいと思ってねえ。なにせ俺とお前さん、おんなじ立場の人間だあ。そんな気になってもおかしくはないだろ?」
おんなじ立場。
神楽は口を閉じて次の言葉を待つ。
「そう、俺とお前は、おんなじ迷い人だ。仲良くしようぜえ」
神楽は思った。
――うさんくさい。
酔っていないのに酔っているような態度。
第一、同じ迷い人と親睦を深めたいからと関係のない街を封鎖してどうする。話が繋がっていない。
船に引き上げて、なにがしたい。その目的はなにか。
「頭悪いからなあ……」
ドクではない。推理もなにもできない。神楽には。
となると、飛び込むしかない。ルイスの目を見て言った。
「いいよ。そっちの船に乗る」
「おお、ありがとうございます。包囲も、すぐさま解きましょう。歓待しますよ、カイジュウ。無論、そこの稲妻姫も」
ルイスはオルガをさして稲妻姫と呼んだ。
稲妻姫はアーニャのこと。オルガではない。
神楽たちは、あえてその間違いを訂正しなかった。
ボリスやナヴァリナの住民に見送られて港を出た神楽たち。ルイスに先導されて、船団に向かっていく。同船しているオルガが警告する。
「気をつけなさいよん。敵地になるわけだからねん」
「あいあい」
神楽は適当な相槌を打った。
「ちょっと、まじめに聞きなさいよん」
「じゃあ、まずはお前がまじめに話せよ。酒を呑まずに」
神楽は船を漕ぎながら、オルガを呆れた目で眺めていた。
彼女は酒を呑んでいる。お礼として住民たちから渡された多種多様な酒。それを喉に流し込んでいた。
「今日は酒を呑まないんじゃなかったのか」
「だってもったいないじゃないのん。それに、ここまできたらあとはなにが起ころうと問題ないわ。なにが起ころうとね」
含むような言い方のオルガであった。
前を行くルイスがある船に乗り込む。神楽もそこに小舟を近づける。登ろうとするとオルガは背中にしがみついてきた。
「泳げなかったりするの? あんたも」
「さあねん」
はぐらかしたが、オルガはセミのように神楽の背中に張り付いていて離れようとはしない。引き剥がしたりせず、神楽はそのまま乗り込んだ。
甲板には大勢の船員が待っていた。
双眼鏡で覗いたときと同じくセーラー服の船員だ。
先に上がっていたルイスが神楽に向かって恭しく頭を下げる。
「ようこそ。私の船に。歓迎するよ、カイジュウ」
丁寧な言葉づかいだが、そこに敬意は見えない。
その目、その笑顔、この船の雰囲気。
歓迎ではなく、嘲りを神楽は感じ取っていた。自然に表情が硬くなり、口からは警戒心がこぼれ出た。
「キャプテン。早くここから出ていってくれ」
「……会話を楽しもうとはしないのかい」
「楽しんでやる義理なんてない」
神楽はふんっと鼻を鳴らして船員たちを見下ろした。
「どうした。早く出航してください。そういう約束でしょう」
「そうだそうだー。はやくしろー。ぼけなすどもー」
オルガは神楽の背中にしがみついたまま急かした。肩に顔をのせてきたので、神楽の鼻にアルコール臭がぷんっと漂ってきた。
ルイスはやれやれと頭を振り、船員に命じた。
「錨を上げろ! 出航だ!」
船員の動きは素早かった。
帆を張り、錨を上げて、舵を回した。
ゆっくりと船は回頭し、ナヴァリナから離れていく。他の船もちゃんとついてきていた。
速度は遅いが、一隻の船のマストを折ってしまったせいだろう。文句を言う気はなかった。神楽は小さくなっていくナヴァリナを眺めてただ時間が過ぎるのを待った。
やがて夕日が沈む。
空は灰色になり、ぽつぽつ星がまたたきだした。
船団はナヴァリナから遠く離れた。このときになって、ルイスは神楽に話をした。船長室には入れないので、甲板上でのことである。
ルイスは葡萄酒を用意していた。
「呑まないかね? お付きの吸血鬼は、好きなようだが」
未だに神楽の背中から離れないでいるオルガは、じーっとルイスの手にある酒瓶を見つめていた。
「俺はそんなに。呑んだことはあるけどね。それで、そろそろ話してくれるんじゃないの? 俺を呼んだ理由」
「……話を急かすものじゃあないぞ。まあいい。率直に聞くが、故郷に帰りたくはないか」
「――――」
神楽は何か言おうとしたが、言葉が詰まった。
脳裏には数年前の記憶がよぎる。忘れようとしても忘れられない、故郷。家族。亀楽家の過去。
無意識に眉間にしわが寄った。
「……意味がわからないな」
神楽は、苦しそうにそんなことを言った。
「帰れるわけないでしょう。俺は、迷い人だよ。どうせそのくらいのこと調べているんじゃないの?」
「ああ。ああ。わかってる。迷い人は稲妻姫の下にだけやってくるわけではないからな。俺のように。だが、迷い人を送り返すことができると言ったら、どうだ」
「……頭おかしいんじゃないの?」
かなり失礼なことを言っている自覚が神楽にあった。だが、素直な感想であった。
会話のさなか、オルガは一言も発しなかった。神楽の背中にしがみついたまま、ただ優しく、彼の頭をなでていた。
ルイスは葡萄酒を一口呑んで、話を再開する。
「迷い人の丘のような土地は色んなところにあり、大勢の人間が研究している。その研究に成果が出ていたとしても、なんらおかしいことじゃあないだろう?」
「あんたにナヴァリナの封じ込めを命じたところが、なにか発見したとでもいいたいの?」
「……いまさら俺がどこかから派遣されたとか、隠してもしかたないか。ああ、そうだ。帰ることができる」
ルイスはまっすぐ神楽の目を見て明言した。
「カイジュウ。お前は日本という国からきたらしいじゃないか。帰れるものなら帰りたいだろう?」
「ひょっとして、あれか。勧誘しているのか」
「そうだとも。モルニア、そこの稲妻姫から離れてもいいだろう? 金がほしいのなら用意する。なあ、聞いてくれよ、稲妻姫」
稲妻姫ではなく、オルガはふふっと笑った。
「そうよねー。帰りたいなら、帰ってもいいわよん。お金を献上したら、恩を返すってことになるもの」
「そうか……。はっは」
ルイスは嬉しそうに言って葡萄酒を呷る。一気に飲み干して、しんみりと語った。
「俺もなんの因果かここにきてしまって数年が経った。だけど、もうすぐ帰れる。お前を勧誘したら終わり。帰ることができる。そう、家族のもとに」
「家族」
オウム返しのように神楽はルイスの言葉を繰り返す。
父、映画オタク。とりわけ怪獣映画が好きで、神楽も付き合わされた。
息子にその怪獣を由来とした名前をつけたことがバレて母と祖母に殴られていた。昨日のことのように思い出せる。
ゴッド、つまり神。そこに『ら』をつける。実にバカバカしい。
ゴッド、ラ。本当にバカバカしい。
ルイスは遠い空を見る。
「ここには月が二つ。合わさると真円になるように浮かんでいる。俺たちの故郷は一つだった。思い出すなあ、子どものことを」
「子どもを残してきたの?」
神楽は空を見ない。海を見つめる。オルガはなおも神楽の背中から離れず、子どもをあやすようによしよしとなでていた。
そうさと、ルイスは言った。
「男の子と女の子。海が好きでな、どっちにも操船の技術を教えてやってた。船を持って海賊退治をするってのが夢って言ってたんだ。早く帰って、教えてやらないと」
「ふーん、元気なのか。子どもは」
「ああ。病気もせずに健康でな。酒も強くて一緒に呑むんだ。成長したなあと実感する」
神楽はお盆や年末年始を思い出す。
親戚が揃って毎度宴会だった。酌をして回って、酔いつぶれた父や叔父たちを寝床に運ばされた。身体がでかいから大丈夫だろうと酒を呑まされたこともあった。未成年だって言っても聞かなかった。
ルイスは長いため息をついた。
「そろそろ、帰れる。帰れるんだ」
「楽しみか」
神楽が尋ねた。声が重く、掠れていた。
ルイスは気づかなかった。
「ああ、楽しみだ。どんだけ成長しているのか、怖くもあるが、会いたいなあ。楽しみだ。やはり、ここじゃなく向こうこそが、俺の故郷で――」
「もう、黙れ」
神楽はルイスの言葉を遮った。
ルイスはあからさまに狼狽(うろた)えだす。
「ど、どうしたんだ? なにか気に触ったのなら謝るが、なにをそんなに怒ってる。仲良くしようじゃあないか。同じ迷い人なんだ――」
「迷い人じゃないだろ」
静かに、淡々と神楽は言った。
「アーニャから引き離してモルニアを奪いたいか。ああそうか。別にそのことについてはどうでもいい。そんなことについてはどうでもいい」
「おち、落ち着け! なにをそんなに怒っているんだ! 大体、俺は本当に迷い人で……」
「迷い人がそんな帰りたがるわけないだろう」
神楽はルイスの胸ぐらをひっつかんだ。腕が震えていた。
「勧誘したいなら素直にそうしろ。迷い人を騙(かた)って、嘘の希望を見せようとするんじゃあない。俺たち迷い人に、故郷なんて残っちゃあいない」
これには語弊があった。
迷い人には帰るところも向かうべきところもない。だから迷った。
故郷が残っている場合もある。
ドクやハリーはアメリカ。アメリカの自宅などは残っている。
神楽は、違う。
日本は残っている。
日本は残っていても、街は、家族は。
ぽんっと、オルガが背中から伸ばした手を彼の頭に置いた。ぐりぐりと神楽の頭をなでながら彼女は言った。
「ルイス、キャプテン・ルイス。あなたは逆鱗に触れたわ」
オルガは優しく、神楽の目の下をぬぐった。熱くはなく、暖かかった。
「触れちゃいけない逆鱗。迷い人に故郷の話題を、家族の話をするなんて研究が足りないんじゃないの? どうせ、全部嘘っぱちなんでしょうけどねん」
ルイスは反論しなかったが、口元には笑みを浮かべていた。
「……そうだ。そのとおり。いや、まいった。だが、もう引き返せないぞ。もう我々と契約するしかない」
神楽は腕に力を込めた。ルイスの顔が青くなる。
「や、やめろ! もう遅いんだよ!」
命の危機を感じてかルイスは急いでしゃべった。
「吸血鬼は水に弱い! 知っているぞ! 泳げないだろう! どのみち、お前が断わるならば、強制的に従わせるつもりだった! カメラカグラ、どのみち、この船に乗り込んできた時点でお前は――」
「つまり、遠慮せずにぶっ倒していいってことか」
「話聞けよ!」
神楽はしっかり聞いていた。聞いていた上で、ルイスを海へと放り捨てた。
水しぶきが上がる。ルイスは浮かんできて、別の船へと泳いでいく。そうしながら大きな声を上げた。
「火を放て!」
その声にしたがい、ほかの船から多くの火矢が放たれた。
船の内部からも火が点いて、たちまち炎上してしまった。船員は一人残らず海に飛び込んでいった。
神楽はその手際のよさに感心を覚える。
「船も安いもんじゃないのに迷いなくやったなあ。このままじゃあ焼け死ぬか、海に飛び込むしかないんだけど……」
「そうねん。いや、姑息で卑怯極まりない嘘っぱち野郎だけど、やることは間違っちゃいないわ。一つ、勘違いをしているけれども」
二人の視線の先で、ルイスは近くの船に救助された。
濡れたままの姿で松明(たいまつ)を片手に叫ぶ。
「降参しろ! でなければ死んでしまうぞ! そこの稲妻姫と沈みたいか!」
それを聞いてオルガが笑った。
神楽はため息をついてから訂正してやった。
「こいつは稲妻姫、アーニャじゃない!」
「……なに!?」
「こいつの名前はオルガ! オルガ・シムレア! 操るのは稲妻じゃなく……」
オルガは神楽が話している途中に彼の背中から降りた。
神楽から少し離れて大きく腕を広げ、オルガは叫んだ。
「間違えないよう覚えておくことよ! 私は黒女皇オルガ! 炎を支配する!」
支配。その言葉がふさわしい。
船に広がっていた赤い炎がその動きを止めて、オルガへと引き寄せられていった。
球体になってオルガの手のなかに収束する。物理法則なんてあったもんじゃない。まばゆい光と超高温が神楽に伝わってくる。
「なるほど。アーニャちゃんなら、為す術もなかったかもしれないわねん。海に溺れていたかもしれないわん。でも、私は、違うのよ!」
オルガは炎を持って振りかぶる。
神楽のものまねだ。投げるのは石ではなく、炎。
「だーいえーんとーう!」
大遠投。
オルガが投げた炎はルイスが乗っている船に飛んでいった。
炎は衝突した瞬間にはじけて船を包んだ。ルイスたちは急いで消火に移る。
船員が大勢いるのだ。直に収まるだろう。
しかし、有耶無耶(うやむや)になんかしてやらない。
神楽はマントを脱ぎ、服を脱ぎ、下着だけの姿になる。
なんかオルガが興奮する。
「いやん! ムキムキ!」
頬に手を当てて、きゃーっと黄色い悲鳴をあげる。
神楽の身体は、全身の筋肉が隆起した、まるで球体をつなぎあわせたような肉体である。ムキムキという表現では、まだ物足りないくらいだ。
しかも、その筋肉と骨は膨張する。
質量そのものが増える。甲板がミシミシと悲鳴をあげる。
「じゃあ、ちょっくら沈没させてくる。ちゃんと救助してやってよ。死者は出したくないから」
「オッケイ。では、いってらっしゃーい」
オルガに見送られて、神楽は飛んだ。
衝撃で甲板の床が砕けるほどの跳躍である。
神楽は海に飛び込むと、まずクロールでルイスの船に近づき、船底を殴りぬく。
一ヵ所だけでなく何ヵ所も。あとは放っておけば沈んでいく。
「こんな、こんな戦いがあるか! 矢を! 矢を放て!」
ルイスは船員に矢を射掛けるよう指示したが、神楽は海中に深く潜った。
それだけで矢は届かない。神楽は潜水したまま他の船に近づいて、拳を振るう。
あっけないものだった。
「降参! もうこっちが降参する! だから、船をもう沈めないでくれぇ!」
ルイスの嘆きが海に響くが、神楽はやめなかった。
怒っていた。
騙そうとした。知らなかったこととはいえ神楽の逆鱗に触れた。
怒りは治まらなかった。
海のなかで咆哮をあげる。どこにも届かない。
届いても返事をするものはいない。
わかっていても咆哮をあげる。
モルニアに神楽が戻ってきたのは深夜である。
ルイスたち船員の救助もして、ナヴァリナにとんぼ返りして引き取ってもらわねばならなかったので時間がかかってしまった。
アーニャの店には未だに客が多く残っていた。彼らの前で、別れ際にボリスから渡されたお土産を披露する。
「タコの干物と、イカの干物と、鯵の干物と……」
「干物ばっかりじゃないか! タコをくれ! タコ!」
ベロンベロンに酔っていたドクが大喜びで奪いとった。
干物ばかりになったのは保存がきかないからである。生魚を運搬するわけにはいかない。
ほかの客たちも好きな干物を取っては店の表に出て火で炙りだした。自由気ままなことである。日本であれば警察にしょっぴかれるのは確実だった。
そして、ここから報告の時間である。
カウンターにいたアーニャがすさまじい仏頂面で神楽に詰め寄ってきた。
「どうだった」
ドスの利いた声である。脅されているような気分を神楽は味わった。
「事件は、無事解決。ナヴァリナはすぐ交易を再開したよ」
「そうか。オルガはどうした」
「首を噛んだら街の門のところでどっかいった」
「……そうか」
アーニャはそれだけしか言わなかった。
神楽は首を傾げた。
「もっとしつこく聞かれると思ったのに、やけにあっさり……」
「そんな顔をしてるやつにはなにも聞かない。座れ。簡単な飯くらい作ってやる」
アーニャは竈の方に戻っていき、フライパンを振り始めた。
神楽は自分の顔をぺたぺた触って適当な椅子に座る。
「そんなに変な顔してるかなあ」
してるんだろうなあと神楽は思った。
腰を据えた途端、どっと全身から力が抜ける。今日は疲れていた。夜も遅いのでじわじわと穏やかな眠気が全身に広がっている。
我慢できずにテーブルに突っ伏すと、アーニャから注意された。
「寝るなよ。私じゃあ、お前を家にまで運ぶことできんからな」
「はいはい」
隠していたスルメをかじりながら返事をする。
アーニャが作っているのは炒り豆。それとステーキ。
香ばしい匂いがする。腹が鳴った。
「…………」
神楽はぼんやりとアーニャの背中を見る。
内装も違う。
調理する人も違う。
空気も違う。
なのに、故郷を思い出す。
母がいて、父がいて、祖母がいて、従兄弟も大勢いた。
もう彼らの姿をこの目で見ることはない。帰ろうと、帰るまいと、同じだ。
出会うとすれば夢。
今日は夢を見そうだと、神楽は思った。