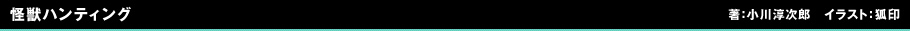コンテンツページ
亀楽神楽は困っていた。
それも借金や、不用意からものを壊してしまったとかではない。
純粋に力の問題で、である。
珍しいことである。
身長、二メートル五〇センチ。
体重、二二〇キロ。
彼のその異様な、巨人という体格から繰り出される力はたいていのことは可能にした。
しかし、こういう状況では無力である。
この日、彼は自身が暮らしているモルニアのすぐ近くの山にいるのだが、状況は深刻だった。彼は運動不足を補うために、ハンティングにやってきていたのだ。
しかし、現在、彼の周囲には狼がいた。
集団である。一匹一匹が鋭い目で神楽を見つめ、距離をとって囲んでいる。
狩り。ハンティング。
されているのは神楽だった。
無論、彼は巨大化が可能。狼など一〇〇匹集まっても物の数ではない。
問題は、彼らが野生ではなく、調教された狼であること。
うかつに動くと、撃たれるということ。
パァンとはじけるような音がして、神楽の肩に激痛が走った。
「――いたい!」
いたい、では普通すまない。
神楽の異常な筋肉密度のため弾が止まるのだ。
しかし、筋肉の薄い頭部なんかに当てられたら、危険だ。
巨大化したら骨も頑丈になるとはいえ、絶対に大丈夫なんて保証はない。
ワン、ワンワンと脅すように狼が吠え立てる。
「ワン! ワンワン!」
神楽も吠え返す。
なにも頭がバカになったわけではなく、
自分を大きくみせることで追い返そうとしているのだ。
だが、狼たちの調教の練度は非常に高い。
恐れたりせず、じり、じりと距離を狭めてきている。
「終わりだ、カイジュウ」
今度は掠れた男の声がした。
神楽は名前を呼んだ。
「ハリーさん、もうやめたら? そのうち夜になるよ、これじゃあ」
「夜になったら、こっちの独壇場だな。稲妻姫も俺を見つけられない」
返事のあと、再び撃たれた。
姿は見えない。どこからか、山の緑に隠れたまま神楽の膝を正確に撃ってきた。骨にまで響く激痛。
「どこだよ、ああもう。全然わかんない」
「すぐそばだ。いま、ゆっくり装填している」
声がして、気配もして、それでも姿は見つからない。
ガサガサと移動する音は聞こえているが、神楽は武術の達人ではないので聴覚で居所を察知するなんてことはできやしない。
「さあ、撃つぞ。今度は左足の内ももだ」
その言葉通りに内ももを撃たれた。
激痛、出血、したたる汗。
神楽は追い詰められていた。
このハリーという『元迷い人』に。
「ドクはいい仕事をしてくれた。あいつは天才だ。アメリカ人の、俺の魂である銃を作ってくれた。とはいえ、マスケット銃だがな」
「あのクソジジイ、ケツをひっぱたいてやる」
「できないよ。お前には。お前は帰れない。お前はもう、故郷には帰れない」
「……お互い様だろ。俺たち『迷い人』には元々、故郷なんて残っちゃあいない」
ふんっとつまらなさそうに神楽は鼻を鳴らした。
内ももの出血は、部位が動脈だっただけに量が多かったがすぐに止まった。
ハリーもどこか寂しそうな声であった。
「そうだな。そう、俺たちに故郷はない。俺は、時代でなくした。お前はなんだ。なんで故郷をなくした」
「……ハリーさん、あんたに教える義務、あるの?」
神楽は言う。疲れたような口調だった。
「そうだな。ない。そんなものはない。さあ、終わりだ」
「終わらない」
「終わりだ。眉間を撃つ。終わりだ、カイジュウ」
パァンと銃声が響いた。
未だ復興工事中のモルニア。
日の出ている時間帯は常に工事の音がこだましていた。
そこでは昔から吸血鬼アーニャが暮らしていて、どこからか現れる迷い人というのを保護していた。
その迷い人の一人、亀楽神楽。
彼は巨人と言っても差し支えのない体格だ。
身長は二メートル五〇センチ。
体重は二二〇キロ。
その姿、太さのとおり、力も常人の数倍はある。彼が工事を手伝えばぐんっと進むだろうが、そうすると大工たちの仕事を奪うことになるというので禁止されている。そのため、やることといえば薪割りくらい。それが終われば昼間はのんびりすごしていた。
とはいえ、たまに用事を頼まれることもある。
食材を買ってこい。
手紙を出してこい。
餌をやってこい、など。
「おーい、飯だぞー」
神楽はアーニャと暮らす家に戻ってきた。
古い館である。広い庭があるけども手入れはしていない。神楽がたまに雑草を刈るぐらいで、観賞用の花なんかもなかった。
ただ、神楽がやってきて少しすると、ペットができた。
誰も飼えず、かといって殺処分するのも哀れなのでアーニャが引き取ったのだ。
名前はまだない。なので、神楽はその種別で呼びかけた。
「虎ー、おーい、虎。飯だぞー」
「……ヴルルゥ」
ぬうっと、神楽の前に虎がやってきた。
大きな虎だった。首輪や口輪もなく、檻にも入っていない。正確な種別としては剣牙虎、サーベルタイガーである。
しかし、その上顎から伸びているはずの長い牙は右と左、両方ともぼっきり折れてしまっている。
それでも肉を裂く爪はあり、その巨体に衰えはなかった。
しかし、神楽の前ではごろんっと仰向けにひっくり返る。
「ウゥ! ウゥ! ウォォ!」
腹を向けて甲高い声で鳴いている。
そのポーズは服従の意思表明だ。
「ん~、猫科でも、すごい違和感だな。慌てるな、ほら、肉やるから」
神楽は荷物を持ってきていた。
そこには肉のブロックがある。虎に渡すと興奮しながら食べだした。
「……食うなあ。危うく、俺が食われるところだったのも懐かしい」
神楽は赤く染まっていく虎の口元を眺めながらぼやいた。
そもそも、この虎はアーニャが飼っていたものではない。ある盗賊団が使っていたのを、神楽が叩きのめして連れ帰ってきたのだ。
それからは馬代わりにしていたりする。必要なく人を脅してしまうので、ひょいひょい使うことはできないが貴重な足だ。
しかし、心配になることも。
「お前、太ってない?」
虎は返事をせず骨をしゃぶっている。
なんとなく腹がブヨブヨしているような気がした。おいそれと散歩に出すこともできないのだから運動不足である。
「ダイエットしたほうがいいなあ、これ」
などと神楽がつぶやいていると、背後から叫び声が聞こえてきた。
「ハンティングにいこうじゃないか!」
突然のことに神楽も虎もびっくりした。
後ろを見ると、塀の上に一人の男が立っていた。
白衣姿で、前頭部が禿げ上がった老人。名前をドクという。
なお、門は開いている。
彼、ドクは白衣を風にたなびかせ、演説のように語った。
「狩り。ハント。ハンティング。男の戦いである。人は、生物は他者を食らって生きている。文明の発達に伴いその自覚は薄れていくことになるが、我が祖国アメリカでは文化として残っていた……」
郷愁に浸っているのか、ドクはどこか遠くを眺めている。
これが美少女か美少年なら絵になるのだろうが、実際はハイテンションな、頭の禿げ上がった老人である。
もう虎は無視をして骨に夢中になっていた。
「アメリカの子どもは銃を持ち、ハンティングに出かける。父とともに、兄弟とともに、撃つ。それは一種の儀式でもあった。男になる儀式。我らアメリカ人は、罪の重さを、生きていくことの重さを知――」
「――――やっかましい!」
演説を遮る怒鳴り声がして、その直後、ドクを稲妻が打ち据えた。
「あっ、ガガガガガッ!」
ドクは敷地内に倒れてくる。
神楽は、死なんだろうと受け止めなかった。距離も遠かったので落ちるのを眺めていた。
そして、ドクが立っていたところから、アーニャがぶすっと仏頂面で、よっこらせと塀を乗り越えてくる。
彼女は神楽に怒鳴った。
「見てないで止めろ! 寒気がしたぞ! 人の家であんな演説されたら!」
「……まあ、怖いよなあ」
「そうだ。まったく、ふざけたやつだ」
アーニャはしゃがみ込み、しびれているドクの禿頭を叩いた。息はあるがぐったりしている。
目を神楽に移し、アーニャが尋ねてきた。
「それで、なんだ。なんの話をしていたんだ」
「こいつ」
神楽は骨をしゃぶっている虎を指す。
「こいつが太ってるなあって考えてたら、ハンティングにいこうって提案されただけだよ。どうする?」
「ん……あ~、太ってるかどうか、か……」
アーニャは骨を咥えてごろごろしている虎に近づいた。
稲妻があるので怖がったりはしない。むしろ虎の方がびくっと身を竦ませた。
「動くな。確かに、だな。太ってるぞ、こいつ」
アーニャが虎の腹をさする。揺れていた。
そこでドクが復活する。
「だから、ハンティングなのだ! 狩りだ! 狩り! いこう!」
「うっさいから黙ってろ」
「さのばびっ!」
アーニャから稲妻を放たれ、ドクは沈黙した。
ビクビク痙攣しているが意識はある。か細くハンティング、ハンティングとつぶやき続けている。怖い。
神楽はドクを物陰に動かしてからアーニャに尋ねた。
「ハンティングは置いといて、運動した方がいいのは間違いないぞ。肥満になるからなあ。こっちでは貫禄があるっていう美点かもだけど、病気になりやすいんだ、あれ」
「らしいな。じゃあ、神楽、ちょっとひとっ走りいってこい」
「ひとっ走り? どこに?」
「どこでもいい。ただし、あまり離れるなよ。モルニアから五キロも離れたら、私の保護下じゃなくなる。私の血がお前の血管内を走っているから、こっちの環境に適応できているんだ。忘れるなよ。倒れるからな」
「わかってるわかってる。んで……」
神楽は脇に目を移す。
倒れているドクが、なかまになりたそうな目で神楽を見ていた。
虎に鞍と鐙、手綱も装着させて、神楽は外に出た。
乗馬経験はなかった。日本では馬を間近で見る機会もなく、モルニアでも神楽はその体重と力加減の利かなさで、馬を潰してしまう。そのため乗せてはもらえなかった。
しかし、虎は違う。獲物を押さえ込むため力が非常に強く、神楽を乗せてもビクともしなかった。
さらに、どうやら普通の虎よりも大型らしく、馬のように長距離を走ってもまったく疲れなかった。
「おー、速い速い。すっごい揺れるけど」
神楽は虎の上でしっかり立っていた。
モルニアのすぐそばにある山に入り、木々の間を駆け回る。ストレスも溜まっていたか、虎は全力で走っていた。
野うさぎを発見すると足を止め、そろそろと背後から近づいていき、ダッシュ。
神楽を背に乗せているのに素早く、気づかれても逃さず、喰らいついた。
急停止したので神楽は前方にすっ飛んだ。
ヤブに頭から突っ込んだが、虎は気にせずうさぎに夢中だった。
「……楽しそうでなによりだ」
ヤブから顔を出して、神楽はぼんやり虎の捕食を眺めながらつぶやいた。
グロテスクな光景だが、さして心は乱れない。そういうことで怖がる歳ではないのだ。
虎が食べ終えるのを待っていると、つまらなさそうな顔をしたドクがやってきた。寝転がったまま神楽は応対する。
「どうした?」
「正直つまらんぞ、私は。せっかく得物を持ってきたというのに、出番がない」
ドクは白衣姿のままだが、なにかを背負っていた。
長い棒状のもので白い布にくるまれている。
「そうは言うけど、それ、剣? 槍? そんなもんじゃあ狩りなんかできないだろう? なんで弓矢を持ってきてないんだ?」
「失礼だな。これは弓なんかよりよっぽどいいものであるぞ。我ら、アメリカ人にはとても馴染み深い武器だ。魂と言っても過言ではない」
「もしかして……」
よっこらせと神楽は身体を起こした。
ドクの背後に回って、布にくるまれたその得物をじっくり見る。
「もしかして、銃か」
にんまりドクは笑った。
「正解だ。私の手にかかれば簡単なものだよ。構造自体は単純だしな」
「暴発は?」
「しないとも。実験もしたし、人に譲っても文句は言われなかったしな。むしろ感激してくれたよ」
ふーんと感心していた神楽だったが、素朴な疑問が思い浮かぶ。
「誰に譲ったんだ。ここの人間じゃあ、銃なんて扱えないだろう」
「私が銃を譲ったその男は迷い人だよ。同じアメリカ人のな」
と、そこまで言って、ドクは眉間にしわを寄せる。
禿頭をさすりながら、ため息とともに弱々しい声を漏らした。
「……大丈夫かねえ、彼は」
「珍しいなあ。ドクがそんな心配そうに言うなんて」
「君、私のことをなんだと思っているのだね。真っ当な人間だぞ?」
神楽はブフッと吹き出して笑った。
「そのアメリカンジョークすっごくおもしろい。ま、それはともかく、どうしてそんな気になるんだ。かなり貧弱だったりしたのか?」
「いや、彼は筋骨たくましい男であった。問題は、なんというか複雑でな。迷い人になった経緯が私とも君とも、また違うものだったのだ。そのせいで最後、別れるときまでよそよそしく、アーニャやモルニアの街に馴染むことができなかっ…………?」
不意に、ドクは言葉を切って周囲を見回した。いつもとは違って目を尖らせている。
気づけば、虎も食事を中断して顔を上げていた。なにか、警戒しているような目つきである。
どうしたのだろうと神楽が思ったときだ。ガサガサと音がした瞬間、物陰から狼が神楽たちに向かって飛び出してきた。
神楽は咄嗟に拳をふるい、狼の下顎を殴りつける。
「ギャィィ!」
その一発で狼はすっ飛んでいったが、妙である。
神楽は首を傾げ、ドクに尋ねた。
「狼って一匹だけで狩りをするのか?」
「違う。狼は集団で狩る。だが、そうでない場合もある」
「どんな場合?」
「まず一つは、群れからはぐれた狼だな。一匹で狩りをするしかない。だが、この場合は、小さいものを襲う。こんなでっかい虎がそばにいて狩りを仕掛けたりはせんよ」
これは毎度のことながら話が長かった。
「もう一つ、おそらく、こっちだな。やあ、参った。噂をすればなんとやらだ」
「早く言えよ。なんなんだ?」
「うむ。猟犬である。調教された狼であれば、単独で襲ってくるだろう。襲ってきた方向から考えると……」
ドクは狼が飛び出してきたところから反対に顔を向け、神楽の服を引っ張った。
「頭を下げたまえ!」
尋常ではない声で叫んだ。
すぐさま神楽はその場にしゃがみこむ。それと同時だ。
――パァン!
聞き覚えのある音、銃声が鳴った。
神楽の脳天をなにかがかすめていく。
「身体を小さくするのだ! 狙われている!」
さすがのドクも激しく慌てていた。
神楽はわけもわからず戸惑っている。
「だ、誰に、どうして?」
「動機はわからんが誰かはわかる。この銃声は私の銃の音だ。間違えん。よって、相手はわかっている。さっき話していた、同じアメリカ人の――」
続きはドクではないものが言った。
「ハリー。それが俺の名だ」
パァンと二度目の銃声。今度は神楽の足首に命中した。
「いったい! いたい! なんだこれ! すごいいたいぞ!」
「普通は『いたい』ではすまんぞ! ハリー! いきなりなんのつもりかね! というか、君はなにをしているのだ! ハンターとしてどこかで暮らしているのではないのか!」
「ハンターだ。ただし、今回はカイジュウハンター、だと」
三度目の銃声。
今度はドクの足だった。
「あいたぁ!」
「ドクも『いたい』ですましてるじゃないか」
「いたいときはいたいとしか言えんよ! あと慣れてるからな!」
ドクはアメリカ軍の元工兵。それも第二次世界大戦に従軍していたらしいから、そういう機会があったのだろう。
神楽はドクを自身の肉体で隠し、その間に応急処置をさせる。
「ハリー、ハリーさん。狙ってるの、俺なの?」
どこにいるか姿は見えないが、とりあえず話しかけてみる。
「そうだ。ドクを殺す気はない。枷にする。殺してもいいくらいには思っているが」
掠れた声での返事。男か女かもよくわからない。
ピーッと口笛が山に響くと、ぞろぞろと狼が湧いて出てきた。先ほど神楽が殴り飛ばした一匹だけではなかったのだ。
唯一無事な虎が唸って威嚇をするが、狼はうろたえない。主人の合図だけにしたがう。よく訓練されていた。
ドクは困り果てた顔になっている。
「カグラくん。まずいぞ。一斉に飛びかかってこられたら、私はどうしようもない」
「俺が守るしかないのか。足手まといだなあ」
「ズバッと言うね、君は」
およよと悲しそうにドクが嘆いた。
神楽はムカついたのでデコピンをして、一つ、現状を変化させる策を思いつく。
「二人と一頭、そろって逃げるのは難しい。虎も、いっせいに襲われたらたまらんだろうしなあ。よし、決めた」
神楽はゆっくり身体を起こし、近くの木の幹にしっかり密着する。
「ドク、少しは走れるな?」
「う、うむ。少しは。ほんの少しは」
「なら、走って。虎の背中にまでいけ。こっちは、武器を使って狼を蹴散らす」
ぐっと神楽は木に抱きつく。
途端、上半身、胸や背中、両肩両腕の筋肉が膨張する。
「一〇八芸の、棒倒し!」
神楽は持ち前の腕力で木を、一切の加減なく抱きしめ、へし折った。
「……おいおい」
ハリーの唖然とする声。
神楽は得意げに笑って、そのへし折った木を振り下ろす。
狙いは狼たち。
「どっせい!」
「信じられん! 逃げろ!」
ハリーの合図で狼たちは飛び退いた。
その直後に木が振り下ろされ、どぉんと重い音が山に響く。
狼は全部逃げてしまったが、その隙にドクは虎の背中に飛び乗った。
「待っていたまえカグラくん! 稲妻姫を呼んでくる!」
「はやくしろよー」
あまり焦りのない声で神楽は返事をした。
虎は意を汲み取ってくれて、まっすぐ山を駆け下りていく。ドクを乗せても速い。狼も追いつけないだろう。
あとは、神楽が生き残ればいいだけである。
もちろん、ハリーを倒せたら文句ないのだが、難しかった。
パァンと銃声がする。神楽の足に穴があく。
「……いたい、いたいって。なんだよもう、姿を出せよ、卑怯者。かっこわるいぞ」
「大木を素手でへし折るやつ相手に姿を出すやつがいるか。油断しない。俺がするのは狩りだ。勝負ではない」
「うぅむ。困ったなあ」
そんなに逼迫した様子のない神楽であるが、本当に困っていた。
足が痛くてまともに走れない。逃げられない。
どこかに身を隠そうにもこの巨体。ヤブに突っ込んでもはみ出てしまう。
「まさかなあ、この体格が仇になるとは……。いや、結構あったか」
日本にいたころは電車の扉や自動改札につっかえたりと散々だった。
「なにをごちゃごちゃ言っている」
ハリーに撃たれた。
今度は脇腹をかすめていった。
「いたい、いたいって! というか、なに、なんなの? なんで俺は狙われてるの?」
「依頼だ」
「依頼!?」
驚く神楽をよそに、ハリーは抑揚もなく淡々と答えていく。
「アーニャ、吸血鬼を過剰に恐れるものがいる。俺は、暗殺の依頼を受け、まずはカイジュウ、お前を殺すことにした」
「……あんたも、アーニャに助けられたんじゃないのか?」
「そうだ。彼女には感謝しているが、俺の仕事はこれしかない。これでしか、生きられない。ドクに言われたよ。ハリーというより、ランボーだなと」
古い映画が神楽の脳裏によぎる。
神楽は父の趣味で色んな映画を見せられた。主に怪獣映画であったが、西部劇やロマンス、アクション、様々な映画を見た。
その一つに『ランボー』という映画があった。
神楽はハリーの経歴を察した。
「ベトナム帰還兵かあ」
知識としては神楽も知っている。ベトナム戦争は、現地においてもアメリカにおいても、悲惨な結果を残してしまった。
ハリーは、わずかに震える声で語った。
「お前もあの映画を知ってたか。いやはや、わりかしあのとおりだ。国に命じられて戦って、散々な目にあったっていうのに、まさか帰国したら罵られるとはなあ」
声がやけに遠い。
そして、山に吹く湿った風がいやに寒かった。
「俺は仕事がなかった。経歴でハネられて、どこも雇ってくれなかった。ある日突然、見知らぬやつに罵倒されることもあった。子どもを殺した。女も殺した。鬼畜、クソ野郎。アメリカは俺たちを拒絶した。そして気づけばここにいた」
「なるほど、アメリカ人でもドクとはタイプが違うか」
「そうだ。ドクは帰るところも向かうところもなくしていた。俺は、帰るところと向かうところから、拒絶された。少し時代が違えば……そんなことはなかったんだろうけどな」
ハリーは寂しそうに言った。
ドクは、モルニアには戻らなかった。アーニャを連れてきたところで、間に合わない。役に立たないと判断したからだ。
ハリーの狼が追ってこないことを確認すると、どうにか虎をなだめて近くの木に手綱を括りつけて、神楽たちのところに戻り始めた。
足の痛みはまったくマシにならない。歩くたびにどころか、呼吸するだけでもじくじく痛む。
なのに、ドクは笑っていた。両目をギラギラ輝かせて、力いっぱいの子どものような笑顔であった。
適当な木を見つけると、老齢でありながらも力強い動きで登り始めた。
一番高いところまで登ると、白衣から双眼鏡を取り出した。彼の目には神楽と狼だけが見えている。ハリー、件の人物の姿は見えない。
だが、ドクは焦っている様子はなかった。
「時代が違えば、なるほど、君はベトナム戦争におもむくこともなかっただろう」
誰に聞かせるでもなく、ドクは一人しゃべりだした。
背負っていた得物を取り、布を外す。
そこにあったのは銃。単純な構造の、先込め式のマスケット銃である。
しかし、そこに改造を施す。
双眼鏡を分解し、マスケット銃に取り付ける。スコープにしてしまった。
ドクは木の枝にしっかり腰を据えた。
舌なめずりをする。
「ハリー、君と違い、私は第二次世界大戦に従軍した。帰ったら賞賛されたよ。硫黄島にはいってないが、よく戦ってくれた、よく勝ってくれたと。対してハリー、君はなんてことをしたんだと罵倒された。結局この違いは私と君という個人に関係なく、時代が違う、ただそれだけのことだ」
ドクのスコープの向こう側には緑しかない。
少し太い木の枝である。神楽や狼からは若干離れている。
「ひどいものだよ。私と君、同じアメリカ人なのになあ。だが、私と君は同じアメリカ人だ。同じアメリカを愛してしまっている」
ドクは引き金に指をかけた。
「同郷のよしみだ。同じ国を愛したものどうしだ」
笑顔が消える。
「稲妻姫ではなく、私が止めよう」
遠くから銃声が響いたが、それだけだった。
神楽の体のどこにも弾丸は命中しなかった。
それなのに悲鳴が聞こえてきた。
「ぐっ! あ、ああ――――」
どこかで大きなものが落ちていく音がした。
風向きが変わった。
神楽は立ち上がり、ふらふらしながらも音が聞こえた方向へ歩いていった。
狼たちは動かなかった。
神楽が音のしたところにやってくると、血があった。
真っ赤であるので、いまさっき出血したというものであったが、そこには誰もいない。どこかに歩いていった痕跡もない。
しばらく首を傾げていると、足を引きずってドクがやってきた。銃を持っている。
怪我をしている割には元気だった。
「やあやあカグラくん。間に合ったようだな。無事でなによりだ」
「……無事?」
神楽は自分の身体をあちこち見た。
穴だらけだった。
「全然無事ではないな!」
ドクは笑っていた。あいもかわらず腹の立つ顔だと神楽は思った。
「で、どうしてアーニャを呼ばなかったんだ」
「間に合わんし、私と同郷の男だからな。私が止めるのが筋だろう。どれ、ちゃーんと命中したようだな」
さっきの銃声はドクのものだったと神楽もわかった。
「でも、逃げられたようだぞ。どこにもいないし」
「いや、いるとも。ハリーはそこにいる。カグラくん、一歩前に踏み出したまえ」
「……?」
言われたとおりに神楽は一歩前に踏み出した。
雑草しかないところだが、ぐにゅっとなった。
なにか、いた。
「ハリー、彼はベトナム帰還兵。迷彩を施すのが得意だったのだろう。稲妻姫に噛まれて、そういう特性が身についた。ほら、とっととその保護色を解除するのだ」
ドクが言うと、神楽の足元がどろりと変色していった。
そこには小柄だが筋骨たくましい男が一人、銃を持って倒れていた。
無精髭を生やした三〇くらいの男だ。迷彩ペイントを施した長袖の服とズボンである。出血は脇腹から。神楽ほどの体格ではないので、当たり前だが、撃たれてつらそうだった。
「なんでわかった、ドク。俺の居場所が……」
横たわったままハリーが言った。
ドクはトントンと自分の頭を人差し指で叩く。
「私の特性は、計算力の飛躍的向上だ。足し算引き算ではなく、世界の流れを、風のゆらめきを、音の距離を計算できる。君の迷彩は大したものだが、じっくり観察すればわかるのだよ。さすがに、落ち着いていないと真価を発揮できんがね。それで、どうするかね、カグラくん」
「応急処置。してあげて」
神楽は迷いなくそう言った。
「いいのかね? 君を殺そうとしていた相手だぞ?」
「知ってる。でも、俺は生きてるしなあ。別にいいんじゃない?」
「……そうだな。別にいいか」
ドクはてきぱきとハリーの応急処置を始める。
服を脱がし、脇腹の傷口に白衣から取り出したピンセットを突っ込む。
「ぐああっ!」
ハリーが悶えた。
ドクは躊躇せずに深くまでピンセットを潜り込ませて、弾丸を摘出する。
それが終われば針と糸を出す。裁縫用のものだった。
そいつを使って傷口を縫い始める。
「おっ、あっ! あぐぁぁぁ!」
「すげえ痛そう」
「うむ! ちょっと痛くしてある! 私だってぷんぷん怒ってるぞお!」
老人がぷんぷんとか言うのは気味が悪かった。
応急処置が終わったところで、神楽はハリーを担ぎ上げ、彼の銃はドクに渡した。
「んじゃ、アーニャのところに戻るか。虎はどこだ?」
「案内しよう。逃げ出したりしないよう、木に繋いである。だが、ハリーを連れ帰っていいのかね? いや、傷も治したことだから、こうするのはわかっていたが」
「稲妻姫、アーニャを殺す依頼を受けたって言ってたなあ」
大した事のないように神楽は言う。
ハリーは息も絶え絶えであったが、どうにか口を開いた。
「俺は、稲妻姫の暗殺依頼を引き受けたんだ……。連れていけば、チャンスを与えることになるんだぞ……」
「そうだなあ。でも、アーニャなら連れ帰ってこいって言うぞ」
「言うだろうなあ。あの子は」
ドクも神楽に同意した。ハリーも、否定はしなかった。
歩いていく。
三人のあとには狼がしっかりついてきている。
少しして虎と合流。神楽はハリーをその背に乗せると手綱を引いて、モルニアに向かう。
「アーニャは、そんな怒らないだろう。というか、怒れないだろうなあ。自分が拾ってきたんだからって妙な責任を感じて」
ドクも、うんうんとうなずいた。
「だろうな。ハリー、しばらくは私の手伝いをして、酒でも呑んで気分を晴れやかにしろ。鬱屈としたものは、そのうち消えるだろう」
「……忘れたくても、忘れられない」
ハリーはじとっと脂汗を浮かばせている。
「あの戦場も、アメリカも、どっちも地獄だった。忘れられるのなら、俺はきっとここにはきていなかった」
「ならば、望むままに悶え苦しむのだな。稲妻姫は話し相手になってくれるだろう。安心したまえ。我々のアメリカには戻れないが、我々がアメリカに望んでいたものは、ここにあるのだ」
得意満面なドク。鼻歌を歌い始めて、ハリーも合わせだした。
曲名は『ヤンキー・ドゥードゥル』だ。独立戦争のころの愛国歌である。
神楽も知っているので合わせて口ずさむ。日本では『アルプス一万尺』として知られている歌なのだ。
店に戻ってアーニャに事情を説明すると、彼女はハリーの尻をフライパンでぶっ叩いた。それだけで、今日は酒を呑んでいけと言った。
その日、アメリカ人たちは夜通し酒を呑み続けたが、翌朝、ハリーの姿はなくなっていた。彼は店に置き手紙を残して去っていった。
朝食の最中にアーニャはそれを読み、神楽に伝えた。
「ありがとうだと。私と、神楽、お前に向けて」
神楽は水を飲み、小さくうなずく。
「ありがとうか。礼を言うくらいなら街に住めばいいのに」
「ハリーは、出会ったときから息苦しそうだった」
アーニャはため息をついた。
「多分、あいつはもうどこかの町や村で暮らすってのが難しいんだろう。けれど、あいつがやってきたら私は酒を出して、飯を出して、話を聞く。ずっとそうする」
「いいんじゃないの。それで。休憩地みたいで」
神楽は食事を終えたので立ち上がり、店の扉を開けた。
涼しげな風が入ってくるが、ぷんっとアルコール臭も漂ってきた。
原因は、店の表で酒瓶を抱きしめて熟睡しているドクである。
「アーニャ、こいつどうする?」
「……ほっとけ。バカは風邪をひかないからな」
「はいはーい」
とはいえ、邪魔になるので神楽はドクを脇によせてから店に戻った。
なお、ドクは本当に風邪を引いておらず、目覚めたらすぐに酒を飲みだした。
「アメリカに乾杯! USA! USA! USA!」
「うるっさーい!」
アーニャ、怒りの稲妻。
騒がしいが、神楽はもうこの光景が楽しいなと思えるようになっていた。