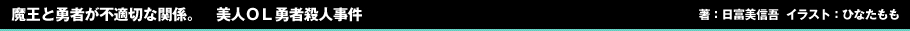コンテンツページ
穏やかな休日、その昼下がり。
日本のとある高校に通っている魔王(の息子)であるリファイ・ケウルスは従者のミルファ・ルセウスとともに、クラスメイトであり美少女勇者でもある井寄(いより)琉羽(るう)の家のリビングにいた。
魔王(の息子)として勇者を倒すために乗り込んできたわけではない。少し前のリファイであればそうだったかもしれないが、今のリファイはそんなことはしないのだ。
ならばなぜ、リファイが琉羽の家にいるのか? その理由はリファイのすぐ目の前、呆然と立ち尽くす琉羽の隣に転がっていた。
白目を剥(む)いた美しい女性。井寄洲央(すおう)。琉羽の姉であり、普段はOLとして働く彼女も勇者だった。
その勇者が倒れているのである。
「洲央姉(すおうねー)さま、目を開けてください! 洲央姉さま、洲央姉さま!!」
そんな洲央に取りすがり、一〇歳の美少女が泣き叫ぶ。井寄陽緒(ひお)。この少女もまた勇者であり、リファイのところにやってきて、洲央が倒れたと知らせてくれたのだった。
リビングに響き渡る陽緒の悲痛な叫びに、リファイは自分の胸が締めつけられるような苦しさと痛みを覚えた。頬にも痛みを覚えたがこちらはミルファがガジガジ囓(かじ)りついているからだろう。琉羽の家に行くと言った時からずっとこんな感じなのだ。
それにしても、いったい誰がこんなひどいことをしたというのか。
勇者は途方もない力を持っている。それこそリファイが暮らしていた世界アフマル・ガメクにおいて、悪鬼羅刹(あっきらせつ)と恐れられるほどだ。実際、琉羽とぶつかり合ったことのあるリファイは勇者の実力を思い知らされている。そんな勇者を倒すことができる者がいるとはとても思えない。
だが、現実に洲央は倒れている。ならば、倒した者がいるということだ。
「勇者を倒すことができるなんて……そいつは化け物だろうな」
「ば、化け物……!?」
すっとんきょうな声が琉羽から上がった。その顔は青ざめ、リファイの言葉に恐れ戦いているようだった。
「怖がらせてしまったみたいだな。だが、現実的に考えて、とんでもない化け物という以外の答えが見つけられないんだ」
「ば、化け物……化け物……」
うわごとのように『化け物』という単語を繰り返す琉羽。よほど怖いのだろう。それは当然だ。洲央の次に襲われるのは自分かもしれないのだから。
何かあった時、琉羽は自分が守ろうとリファイが心に決めていると、凛とした声が響き渡った。
「間違った推理はそこまでよ!」
それまで白目を剥いて倒れていた洲央である。
「勇者が倒れていたからと言って、犯人が化け物だと決めつけるのは早計だとあたしは思うの!」
「では、いったい誰が? ……い、いやいやいや、待て待て待て!? 洲央、あなたは倒れていたはずだ!」
「魔王子くん」
洲央はリファイのことをそう呼ぶ。
「考えちゃ駄目、感じるのよ!」
その勢いに思わず「わかった」と頷くものの、すぐに意味不明であることに気がついた。
「とりあえずお姉ちゃんはリファイくんの推理に反対よ!」
倒れていた洲央の証言だ。信憑性は高いだろう。というか正しいに違いない。
「だが、化け物でなければいったい誰にあなたはやられたというんだ? 化け物以外にはあり得ないではないか」
「あのね、魔王子くん。あたしが君の推理に反対するのは、君のためでもあるのよ?」
「さっぱり意味がわからないな。どうして化け物があなたを倒したという俺の推理を否定することが、俺のためになるんだ? 勇者を倒すほどの存在だ。それは化け物以外あり得ない。つまり、化け物が倒したと考えるのが自然だろう」
「ああ、そんなに化け物、化け物って連呼して……」
なぜか洲央が困った表情になる。その理由にまったく思い至らず、リファイが首を傾げていると、琉羽がとんでもないことを口走った。
「化け物でごめんなさい……!」
「何を言ってるんだ琉羽? 君が化け物、あり得ないぞ」
「でも、お姉ちゃんを……お姉ちゃんを倒したのは、このわたしなんだもの……!」
「な、なんだって!?」
どうして琉羽が洲央を倒したのか。仲のいい姉妹ではないか。衝撃を受けながらもそう尋ねたリファイの言葉に対する琉羽の答えはこういうものだった。
「リファイくんにわたしの作った手料理を食べて欲しくて……それで特訓してたの」
先日、調理実習とやらで作ったというクッキーを陽緒がリファイに持ってきたことがある。それを食べてリファイがうまいと言っているのを見て、うらやましくなったらしい。自分も手料理を作ってリファイにおいしいと言って欲しいと。
「二度と料理はしないって決めてたんだけど……特訓すればなんとかなるって思ったの。でも、駄目だったね。お姉ちゃんに迷惑をかけて、陽緒には心配させちゃった」
洲央が倒れていたのは要するに琉羽の手料理をつまみ食いしたからで、リファイを呼びに来た陽緒はそれを知らなかったのだ。
「つまり、俺のためにがんばってくれていたというのか……?」
「……うん」
「俺はなんて馬鹿なんだ! そんなこととは知らず、君を化け物扱いしてしまった! 俺は許されないことをした!」
「だ、大丈夫だよ、リファイくん! わたしなら気にしてないから!」
「許してくれるのか……!?」
「もちろんだよ」
「ああ、琉羽、君はなんて素晴らしいんだ……! こんな俺を許してくれて――いや、それだけじゃない。俺のために苦手なことに果敢に挑戦し、それを克服しようとする姿も本当に素晴らしい! 君はどこまで素敵なんだ!」
「ふぁっ!? リ、リファイくん、思ってることが漏れてるよ!?」
「む、そ、そうだな。だが、かまわない。君が素敵であるのは本当のことだし、むしろ言い足りないくらいだ」
「そ、そんな……恥ずかしいよ。でも、ありがとう」
そうやってリファイと琉羽が見つめ合っていると……。
「あ、あれ、何かおかしくないこの雰囲気? さっきまであたしが倒れて『誰が犯人なんだ!?』みたいなことやってたはずなんだけど」
「そんな感じはまったくなくなっていますですね……」
「リファイが誰のご主人様か忘れてる。これは大問題」
外野が何か言っていたが、今のリファイと琉羽にはまったく聞こえていない。
「それで琉羽の料理はどこにあるんだ? ぜひ食べさせて欲しい」
「駄目だよ! だってわたしの料理、勇者を倒す代物だよ!? 化け物級だよ!?」
「かまわない。俺が食べたいんだ」
「リファイくん……!」
はにかんだ表情で琉羽が差し出した料理を口にした瞬間、リファイは意識を失った。
倒れたリファイの顔には、何かをやり遂げたような、とても満ち足りた表情が浮かんでいた。