
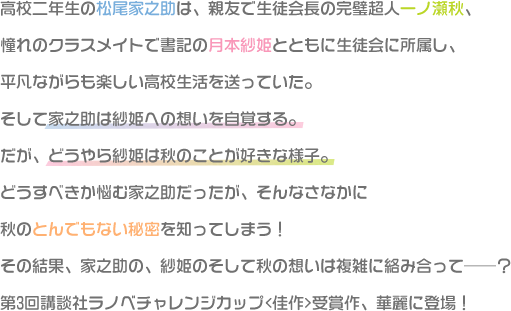





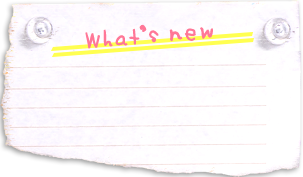
2015.06.26
2015.06.24
2015.06.17
2015.06.16
『二線級ラブストーリー』公式サイト オープン !!
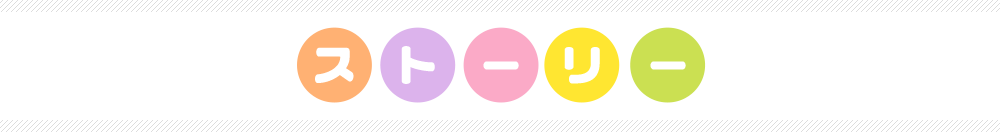

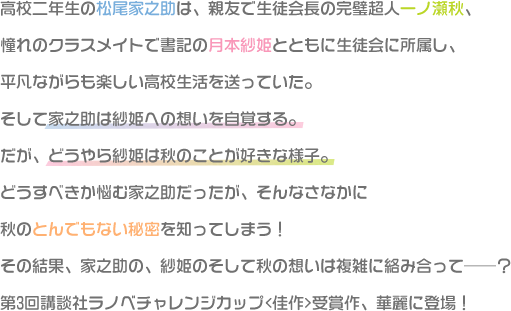


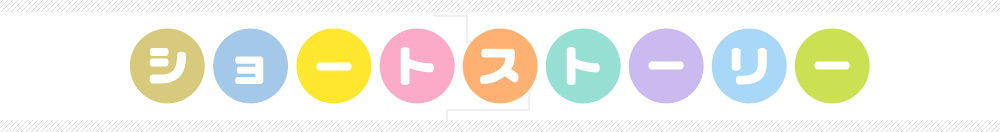
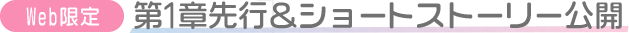
入学式を明日に控えた春休み最後の日、一二三高等学校生徒会各人は、スピーチ原稿の最終チェックや新入生歓迎企画の資料作りに勤しんでいた。
おおよそ全員の集中力が切れた現在は、帰宅前のまったりタイムだ。
生徒会室にコーヒーの香りが充満する中、ひとつ興味深い話題を振りまいたのは、我が妹、芽衣だった。
「そういえば、みなさん、自己紹介って得意ですか?」
「ん? どうした、急に」
俺がそう尋ねると、芽衣は恥ずかしそうに頭をかく。
「いやー、明日クラスで自己紹介するんだーって思ったら、憂鬱でねー」
芽衣は俺たちのひとつ下で、明日は新入生として迎え入れられる立場である。
しかし同学園の中等部上がり、つまりエスカレーター組で、今年度の生徒会会計を勤めているのだ。
そんなできる後輩芽衣の悩みに、生徒会のメンツが反応する。
「そうなのか? 芽衣ちゃんそういうの得意そうだけど」
秋は、女子生徒たちを虜にする中性的なハンサム面を向け、柔らかに微笑む。
「あー私も苦手だなー、自己紹介。私たちもやったりするのかなあ?」
月本は、男子生徒たちを虜にする見目麗しい顔を向け、芽衣に同調する。
「おそらくどの学年でもやると思います。私はクラスを持っていませんが」
近江教諭は、クールな表情で淡々と述べた。
「そういや明日クラス発表かー。また同じクラスだと良いね、私と秋と松尾くん」
「おう」「だな」
月本の願望に、俺と秋は同意の声を送る。
良いね、というかそうでなくては困るというものだ。
あまつさえ俺だけ省かれ、秋と月本だけ同じクラスになった日には……秋への嫉妬が涙となり、風呂の水かさが増えるだろう。
「やめてよ気色悪い……兄の涙が配合したお風呂なんて入りたくねえ……」
芽衣は身震いを起こしていた。兄の心を読むんじゃない。
「芽衣ちゃん、そんなに苦手なら、ちょっとここで練習したら?」
改めて、秋が芽衣にこんな提案をする。
「ああ、そりゃいいな。俺らの前で出来たら怖いもんなしだろ」
「スピーチの達人、秋もいるからね! いい練習になるんじゃない?」
加えて賛成する俺と月本に、芽衣は照れくさそうに立ち上がった。
「じゃ、じゃあちょっとやってみますね……」
コホンと咳払いをすると、芽衣は自己紹介をはじめた。
「はじめまして、松尾芽衣です。中等部から上がってきました。去年から生徒会を手伝っていた関係から、新入生ですが生徒会の会計をやっています」
とうとうと話す芽衣。どう見ても心配なさそうじゃないか。
「ちなみにこの学校でそこそこ目立っている、アホでマヌケで変な顔ですね毛の濃い、最近風呂で密かにラップの練習をはじめた、『センター過去問』というフォルダにエロ画像を保管している生徒会副会長は、私の兄で……もが」
「やめてーーーーっ!」
唐突な個人情報の漏洩に、慌てて俺は妹の口を塞ぐ。
「なんなのっ? なに言ってんのっ? ていうかなんで知ってんのーーーっ?」
俺の問いかけにも、芽衣はニヤニヤ笑って「ほががー」とか言うだけだった。
「「……………………」」
妹による言葉のドメスティックバイオレンスを目撃した同級生二人は、なにかを隠した温かな瞳で俺を見つめていた。その優しさと無言が痛い。
最後に近江教諭が、さして興味なさそうな声で一言。
「松尾、センター試験に保健体育はありませんよ」
「わかってますッッ!」
俺のメンタルがにわかに破壊されたところで、秋が月本へお鉢をまわす。
「じゃあ今度は紗姫もやってみたら? 苦手なんだろ?」
「えー、恥ずかしいなー。でも、わかったよー」
月本はほんのり顔を赤らめ、立ち上がる。
その端正な顔を俺たちに向け、自己紹介をはじめた。
「はじめまして、月本紗姫です。生徒会の書記をやっています」
心の毒を洗い流してくれるデトックスボイスで、月本も流暢に語る。
この子も苦手とか言っておいて、全然危なげないな。
「趣味はカフェ巡りと読書と映画鑑賞と半身浴です。特技は書道と料理、あとお裁縫もできます。長所はだれとでも仲良くできるとこで、短所は体力がないとこと、ちょっと天然入ってるとこかな? あ、あと実家が豆腐屋で毎朝五時起きなので、いつも眠たそうって言われちゃいます。好きな食べ物はミルフィーユとかマカロンで……」
「つ、月本ストップ、ストップ……長いな、ちょっと長いな」
月本の情報ならいつまでも聞いてやりたいところだが、クラスの自己紹介としては少々長尺だろう。なのでいったん止めてやる。
すると月本は、自虐するような笑顔でぺろっと舌を出す。
「ごめん……緊張しちゃって、どれだけ話したかわかんなくなっちゃった。ダメだね私、短所におしゃべり好きって、追加しなきゃだねっ♪」
可愛すぎる。
自己紹介が苦手という二人の実践が終わったところで、スピーチの達人らしい秋の出番……と思いきや、ここで意外な人物が立ち上がる。
「続いては、私ですね」
「え? おーみきょーゆもやるんですか?」
「はい。これでも簡潔な自己紹介は得意なので、お二方の参考になれば、と」
なるほど。たしかに近江教諭なら、言いたいことをすっきりまとめるのが得意そうだ。ひいては自己表現もお手の物だろう。月本や芽衣も、うんうんと頷いている。
近江教諭は感情の見えないいつもの無表情で、自己紹介をはじめた。
「はじめまして、近江悠子と申します。二十四歳です。数学教師をしております。また、生徒会の顧問も担当しています」
平淡な口調で、慎みを崩さず説明する近江教諭。
さて、ここからどう簡潔に自分を表現するのか……?
「好きな武器はガスバーナーです。以上です」
顧問のいろいろおかしい自己紹介に、生徒四人はそろってずっこけるのだった。
「いやいや短すぎでしょ教諭!」
「そしてガスバーナーは武器じゃないです!」
「ていうか好きな武器を発表って、どんな武装組織での自己紹介ですか!」
俺の手にも余ると思ったのか、秋と芽衣も俺に追随してツッコミを入れる。
可愛い生徒たちのジェットストリームアタックにも、近江教諭は平然とした顔で小首を傾げていた。
「明快でわかりやすいと思ったのですが」
「ヤバい人ってことしかわからないですよ! 他にも、たとえば特技とか趣味とか……」
「特技ですか? 特技はどんなに気に食わない人間でも、心の底からは嫌いにならないよう努力できることです」
「人知れずやるべきことはなしで!」
「趣味は、縁もゆかりもない墓の前で意味深な表情をしながら、『もう少し……もう少しで私もそっちに行くから……』と呟くことです」
「普段なにやってんだあんた!」
顧問が思う存分生徒を弄んだところで、真打ち登場である。
秋は堂々とした表情で、俺たちの顔を見回す。
「じゃあ俺も、ちょっとやってみようか。自信はないけど、経験はあるからな」
役職柄、人前での演説に長けた秋はそんな謙遜を前置きに、自己紹介をはじめた。
「はじめまして、一ノ瀬秋です。二年生ですが生徒会の会長をしています。放課後はほとんど生徒会の仕事をしているので、付き合いが悪くても嫌いにならないでください(笑)」
時折ユーモアを交える秋の自己紹介は、声の音量・抑揚、立ち姿、表情など、すべてにおいて完璧だった。
そこそこ高いハードルを軽く越えてくるあたり、悔しいがさすがと言えよう。
そうして秋のスピーチは、なんの問題もなく締めに入る。
「ちなみに趣味はトウチョウとトウサツです。こんな俺ですが、よろしくお願いします……と、こんな感じかな!」
「いや最後っ!」
完璧だからこそ、最後に入ったとてつもない異物感が際立っていた。
「趣味、盗聴と盗撮って、さらっとヤバい発言すんなやっ!」
「なにをー、人の趣味に口出しすんなよー」
「えっ、マジなのっ? マジで盗聴と盗撮が趣味なのっ?」
「勘違いすんな。登頂と透察だって。山登りと、人間観察ってことだ」
「まぎらわしいわ!」
びっくりした……一年にわたって付き合ってきた親友が、盗聴や盗撮に興じていたなんて知ったら……俺はこれからどんな顔で会えばいいか、わからなかった……。
「いやー、つい俺もボケたくなってな。すまんすまん」
「まったく、肝が冷えたわ。そしてよかったよ、ただのボケで本当によかったよ」
秋は能天気に「わははー」と笑っていた。人の気も知らずに……。
「さて、じゃあ最後に……おまえも自己紹介してみろよ」
「へっ?」
秋のでシメかと思って油断していた俺に、秋はこんなことを言ってきやがった。
しかもなぜか他の面々も、それに賛同を示す。
「あ、私も見たいな。松尾くんの自己紹介」
「ウン。アタイモ、ミタヒミタヒー」
「私も是非見たいですね。松尾の醜態」
棒読みの妹と辛辣な教師は置いといて、月本にこんなことを言われては、やらずにはいられまい。
俺はできるだけ精悍な表情を浮かべ、颯爽と立ち上がる。
「仕方ないな……そこまで言うなら、俺もやろうじゃないか!」
入念に咳払いし、顔を叩いて引き締め、俺は自己紹介をはじめる。
「はじめまして! 俺の名前は松尾……」
キーンコーンカーンコーンと、空気の読めないチャイムが俺の声をかき消した。
「おっと、もうこんな時間か。じゃあそろそろ帰ろうか、みんな」
「ですね」「ではみなさん戸締まりをしっかりお願いしますね」
「いやちょっと待ってよ!」
秋の言葉を皮切りに、帰り支度をはじめる芽衣と近江教諭。ひどすぎませんか?
「聞いてよ! 俺の自己紹介も聞いてよ!」
「いやもう時間だし」
「待ってよ! こんなのあっという間じゃんよ!」
「では鍵を渡しておくので、一人で勝手にやっていてください」
「いやおーみきょーゆ! お願いだから聞いて! 俺の醜態を独り占めできますよ!」
「もう今の時点で見事な醜態を見れたので、満足です」
あまりにひどい仕打ちである。唯一俺の心を癒すのは、この状況に苦笑してくれている月本だけであった。月本はどうしていいかわからない、といった表情で周りを見る。その手はこっそりと帰り支度をしているように見えるが、気のせいだろう。
結局俺は、だれも聞いてくれない自己紹介を頭で繰り広げながら、皆を追うのだった。
はじめまして、松尾家之助です。生徒会では副会長をしています。
生徒会では、だいたいこんな感じです。
見えないかもしれませんが、一応楽しくやっているので、ご安心ください。
目が覚めたその瞬間、思わず「まずったあ」と声を漏らした。
スマホを見ると時刻は正午すぎ。春休みとはいえ、さすがに寝すぎた。春眠暁を覚えず、なんて偉い人の言い訳すら通じない所行だ。
しかしながら自己嫌悪は空腹感にかき消される。反省もそこそこ、俺は自室を出た。
リビングに入ると、妹がソファに寝転がりながら、テレビを眺めていた。
「おはよ」
一応声をかけてみると、芽衣はテレビに目を向けたまま返事する。
「おそよう。よーくそんな寝てられるねえ」
「自分でもそう思う。……なにおまえ、高校野球見てんの?」
妹の視線を一身に受けるテレビが映しているのは、土ぼこりの舞う甲子園のグラウンド。不揃いのブラスバンド演奏と少々しゃがれた実況の声が、非日常感を際立たせていた。
「どうした、めずらしい。イケメン選手でも見つけたか?」
「ひどい印象だね、私。普段興味ないのはたしかだけど。この栃木のよくわからない高校、がんばってるなーと思って」
見てみると、カードは甲子園常連の強豪校と、初出場校。芽衣の言ったほうは後者だ。
十四対十という壮絶な試合を、常連校がリードして九回を迎えている。ただ現在は後者最後の攻撃で、ツーアウト満塁という熱い場面だった。
「なるほど、これは見入っちまう状況だな」
「だしょ。最終回で一気に追い上げてきてんのよ、この栃木のよくわからない高校」
「応援してるなら名前覚えてやれよ……。母さんは?」
「かいものー」
「メシは?」
「しらなーい」
一切テレビから目を離さない芽衣。その様子から、腹が減っているわけではなさそうだ。
「……芽衣ちゃん、兄ちゃんお腹すいたな」
「作らねえよ」
察しのいい妹は吐き捨てるように言った。口の悪いやつだ。
「まったく……こういうとき『わかったよお兄ちゃん、あたいがんばって作るね!』って言ってくれる妹がよかったなあ」
「ユーカリでも食ってろ」
「コアラじゃねえんだよ、俺は」
仕方ないのでトーストを焼くことに。用意してると、テレビからひときわ大きな歓声が飛んできた。同時に妹の「栃木のよくわからない高校の夏は、まだ終わらなーい」との声が聞こえてきたので、さらに試合がおもしろくなっているのだろう。
食パンをトースターにセットし、急いでテレビへ向かう。
「いや春だろ。おお、すげえな」
「うん。そーしゃいっそーのツーベースだって。すごいよ、この恰幅の良いデブ」
「なんで一回ぼかしたのに、ストレートに言っちゃうんだよ」
興奮するとより口が悪くなる妹である。横になっている芽衣の隣に腰をかけると、裸足の小さな足が俺の太ももをぺちぺちと叩いて遊ぶ。
ゲームは強豪校側がタイムをとっていた。泥まみれの内野陣が、投手を囲んでいる。
「そういや芽衣」
「なーに?」
「ホントにいいのか、生徒会」
尋ねると、芽衣は横目でちらりとこちらを見る。
「中等部のときから手伝ってきたせいで、会計になる流れになってるけど。本来、新入生がやる仕事じゃないんだからな。なんなら、俺が秋に言って……」
「なーに言ってんだか」
芽衣は、マウンドで無理矢理笑顔を作っている投手を見つめたまま、俺の声を一蹴する。
「ひとつだけ言っておくぜ、家兄。あたいの意思は、他のだれにも干渉されないんだぜ。流れだから受け入れる、なんて私は絶対しないのよん」
そう言って、芽衣は足の親指と人差し指で俺の太ももを軽くつまむ。
「いてて。まあ、それならいい。いらん心配だったな」
「てかさ、そんなに私を生徒会に入れたくないのー? それってまさか、紗姫さん……」
「おっと試合再開するぞ。さあ注目だ」
逃げようとするも、妹はそうはさせないとばかりにカニばさみで俺を捕まえる。
「うぐぐ……放せっ……」
「まーたしかに、恋の行方を実の妹に観察されるのはいやだよねー。しかもすっごい近く、アリーナ席から。うん、わかるわかるー」
「わかってんなら言うなや……てか、マジで放して……地味に痛い……」
「まったくもー、いつまで経っても諦められないんだからなー、うちの兄は。負けるに決まってるのに。秋さんと紗姫さん、ベストカップルでしょーに」
「うるせえうるせえ! 見てろよ、今にこの栃木のよくわからない高校のように、大逆転劇を見せてやる! 秋を負かしてやる!」
「おおう、大きく出たね。じゃあこの試合の勝敗も、家兄に関わってくるね」
「おう! 栃木のよくわからない高校が勝ったら、俺の恋は順調に、確実に発展して……」
次の瞬間、テレビから金属音が鳴り響く。俺と芽衣はそろって目を向けた。
打者の打った球はショート正面だが、打球の勢いが強くショートはファンブル、しかも球を見失っている。その間にバッターランナーは一塁へ駆ける、が……。
『ああーっとバッターすっころんだーーッ! その間にショートが送球し、アウトーッ! ゲームセットーーーッ! 大波乱の末、まさかの幕切れですッ!』
「……………………」
言葉を失う俺を見て、芽衣はぷぷぷと頬を膨らませる。
「大波乱の末、まさかの幕切れだってさ。家兄の恋もきっとこの試合のように、大波乱なんだろうねえ。私もちゃんと見てるね、アリーナ席から」
芽衣はぴょんとソファから飛び起きると、「私もトースト食べよーっと」と言ってキッチンへ向かっていった。
本日も我が妹は、俺の不幸を蜜にトーストを食べる。
俺は、我が恋の安寧を祈るばかりであった。
いやホント……大波乱とか、ないですよね……?
俺、秋、月本の三人は、本日の昼食を学食でとることにした。
現在俺と秋はご飯ものの列に並んでいる。
「月本はどこ行ったんだ?」
「紗姫は麺類だろ。パスタ食べたいって言ってたし」
そう答えた秋は、なにか難しい顔でメニューを睨んでいた。
「うーむ……うーむむむ……」
「まだ決まってないのかよ。もう順番来るぞ」
「うーん……カツ丼と親子丼で迷ってて……どうしようか……」
「パッと決めろってそんなの」
「テレフォン使うか、オーディエンス使うか……」
「どこで迷ってるんだよ」
ねえよ、学食にそんなツール。
ここで、俺の番が回ってきた。注文を尋ねるおばちゃんに、俺は迷うことなく答える。
「チキンステーキをお願いします」
「うあー、それ俺が食おうと思ってたのにー」
「いやおまえカツ丼と親子丼で迷ってなかったか……? てか、食いたかったらおまえも頼めば良いだろ」
「いやいやー、二人そろって同じもん食ってたらアレだろー。『わー、生徒会長と副会長、おそろいだー。なかよしー』って思われて、アレだろー」
「気にしすぎだろ。どうでもいいわそんなの」
「大体なんだよおまえ、チキンステーキて。肉食かよ。農耕民族であることを忘れたか。恥を知れ、恥を」
「なにで怒られてるんだ俺は。普通にご飯も頼んだよ」
ていうかおまえもチキンステーキ頼もうとしてなかったか?
「まあご飯もいっしょなら……ってちょっと待て、それだけ? ご飯とチキンだけか? それじゃおまえ一日に必要な栄養素を補えないだろ!」
「母ちゃんかおまえは!」
「ダメだダメだそんなんじゃ! ちょっとおばちゃん、このお兄さんにみそ汁追加!」
「なに勝手に注文してんだよ!」
「あちらのお客様からです」
「おばちゃんもノリ良いな!」
払うのは俺なんだけども。新手の抱き合わせ商法か。
俺の注文が済んだところで、今度は秋が尋ねられる。秋は最後までうんうん唸った末、決断した。
「じゃあカレーでお願いします」
「カツ丼でも親子丼でもチキンステーキでもねえのかよ……」
なんだったんだ、あの悩んでいた時間は。
「ファイナルアンサー?」
「おばちゃんのノリ!」
「……いややっぱ、テレフォン使います」
「まだ続くのこれっ? もうやめろ、この悪ノリ!」
「ではこちらを。すでに電話が繋がっています」
「ホントにあるのかよっ!」
おばちゃんから手渡された受話器を耳に、秋は真剣な表情だ。
これメシなににするか悩んでるだけだよね……? てかだれと繋がってるんだよ……。
『もしもーし。ちーっす秋さん。ついでに家兄もちーっす』
「芽衣かよ!」
あの妹なにやってんだ! ヒマか!
『うーん、悩みますよねー昼食って。それで午後のテンション左右されますからねー。あ、あとさっきから気になってるんですけど、家兄、後頭部に寝癖ついているよ』
「は? 後頭部?」
謎の発言に振り返ってみる。
そこにはテーブル席につき、うどんをすすりながらこちらに手を振っている芽衣がいた。
「そこにいたのかよ! 直接話せや!」
ここでプチッと通話の途切れる音が聞こえた。テレフォンが終了したらしい。
「はい、時間切れです。参考になったんじゃないですか?」
「はい。芽衣ちゃんには感謝しなければいけませんね」
「どうでもいいことしか言ってなかった気がするけど……」
そして、学食のおばちゃんは静謐な声色で、改めて尋ねた。
「では、解答は?」
「はい、カレーでお願いします!」
「ファイナルアンサー?」
「……ファイナルアンサー!」
「なんだこの緊張感……?」
テテテーン。
「なんか聞こえた今! SEも忠実再現なのっ?」
俺とは対照的に、口を閉じ続ける秋とおばちゃん。
長い沈黙の果て、ついにおばちゃんが言い放つ。
「正解!」
「正解ってなにっっ?」
「「「うおおおおおおおおおっっ!」」」
「うおおおおってなにーーーっ?」
瞬間、列の後ろの面々が歓声を上げ、学食は大盛り上がりである。
秋はその場で崩れ、大げさにガッツポーズをしている。芽衣もすぐそこの席から、涙をこらえるような笑顔で何度も頷いていた。
謎が謎を呼ぶ学食のシステムに、俺はひとり困惑していた。
「ちなみに、甘口と辛口どちらにしますか?」
「うーん……じゃあオーディエンスで」
「もういいわ!」
「なあ、ふたりとも。パセリのこと、どう思ってる?」
学食にて、俺と秋と月本の三人で昼食を終え、まったりしているときだった。
秋のこの質問に、俺と月本は首を傾げる。
「どうしたの秋、急に」
「どう思ってるって……おまえはパセリのなんなんだよ」
「ああ、質問が悪かったな。要は、付け合わせとしてのパセリを食べるかどうかって話」
どうしてそんな話題を持ち上げたくなったのだろうか、この男は。
そう思っていると、真意はすぐに明らかとなる。秋は、俺が食したチキンステーキの空になったプレートに視線を落とし、語りだした。
「いや、家之助さっきさ、付け合わせのパセリ食べてたじゃん? あたりまえのように。俺的にはアレ、地味にカルチャーショックだったんだよね」
「そうか? まー食わない人が多いのもわかるけど……俺は残さずに食うぞ。食後の皿になにか残ってるのが気持ち悪いんだよな。あと単純に好きだし」
「えー、家之助好きなのかー? 変な味するじゃんアレー」
秋は珍妙な生物を見るような目で、俺を見る。なんでも出来る完璧人間の秋だが、実はかなりの偏食家だったりする。
この話題に、月本が持論でもって新たな風を吹き込む。
「私も食べないけど、嫌いってわけじゃないよ。はじめから食べないものとして認識してるって感じ? お弁当に入ってる、緑色でギザギザの仕切りみたいな」
「なるほど。紗姫は、パセリは飾りっていう意識が強いわけか。でもまあ、とどのつまりは俺といっしょだな。つまりパセリ食べる派がおかしいってことだ」
「いやいやちょっと待てよ秋、その解釈はちがうだろ」
いくらパセリが嫌いだからって、その言い草はあまりに極端だろう。俺はパセリ好きとして黙っていられなかった。
「食べる派がマイノリティなのは、そうかもしれない。だがそれを否定的に捉えるのは、間違ってる。正義の反対は悪ではなく、またひとつの正義なんだ」
「最後のが言いたいだけだろ。だいたいパセリ一枝を食すことに意味はあるのか? 食わせたいならもっと載っけるだろ。コックだってハナから彩りとしてしか見てないんだよ」
「でもパセリって結構栄養価高いみたいだよ。ビタミンとかカリウムとか」
月本はスマホを見ながらそう言う。調べてくれたようだ。献身的でいい娘である。
「あと付け合わせだけじゃなくて、いろんな料理に刻んで入ってたりするよね。香味野菜として。だから食材としてみることは、おかしくないんじゃないかな?」
「ほれ見れ、秋!」
「ただ付け合わせのパセリを食べるか食べないかだと、食べない方が圧倒的みたいだね」
「ほれ見れ、家之助!」
果たして月本はどっちの味方なのだろうか。というかどっちの味方でもないのか。食べないけど嫌いじゃない、パセリ食べない穏健派なのだろう。
噛み合いそうで、噛み合わない三人である。
ただ現状、数の論理で食べる派が苦戦を強いられているのはたしかだ。
これは、負けられない……っ!
「ひとつ、前々から気に食わなかった風潮がある」
そう前置きすると、食べない派ふたりは俺の声に耳を傾ける。
「パセリとパクチーの、扱いの差だ」
「パクチー?」「なんでパクチーが出てくるんだよ」
「パクチーと言えば、好き嫌いが大きく分かれる食材の代表格だ。だからこそ、好き嫌い関係なく、一目置かれている印象がある。奥深い食材としての地位を確立しているんだ。なのに何故同じセリ科で、パクチーよりもクセが少ないパセリが、そのポジションを掴めない。あまつさえ何故、食材としての土俵に立つことさえ危ぶまれているんだ!」
「う、うむ……ちょっと熱が入りすぎだが、言いたいことはわかった」
「たしかにパクチーって昔から妙な存在感あるよね。パクチーの専門店もあるみたいだし。テレビで、山盛りのパクチーもしゃもしゃ食べてるとこ見たことあるー」
「うへえ、なんじゃそりゃ……おぞましい光景だなあ……」
やはりと言うべきか、秋はパクチーもダメらしい。
しかし、論点はそこじゃない。
「だから俺は声を大にして言うぞ! パセリは食材だ、食べられるために生まれたんだ! ここにパセリの市民権を要求する! パセリはおいしい!」
「いやいや、それは無理な話だ。食材と主張するには、彼はデコレーションとしてのスタンスに甘んじすぎた」
「うーん……パセリってパクチーよりもクセが少ない分、インパクトも弱いしねー。パクチー並みの地位はさすがに難しい気がするなー、私」
「くう……おまえらパセリ農家のおじさんのことを思ってもそんなこと言えるのかっ? おじさんはおいしく食べてもらえると思って、丹精込めて育ててくれてるんだぞ!」
「うぐ……おじさんを引き合いに出すのは卑怯だぞ!」
「それ言われちゃうとなにも言えないよね……」
三人の議論が最高潮になってきた、そのとき。
この激論に終止符を打ってくれそうな人物が、俺たちの前に現れた。
「みなさん、なに騒いでるんですか? そろそろ昼休み終わりますよ?」
友達を引き連れ、丼の載ったトレイを持つ、我が妹芽衣だ。
彼女の登場に、俺たち三人は目を輝かせた。
秋が代表して、芽衣に尋ねる。
「芽衣ちゃん……付け合わせのパセリ、食べる?」
ごくり、と俺と月本はつばを飲み込む。
きっと、ここで決着がつくのだ。
現在好き嫌いで両極端に振り切っている俺と秋、さらに食べない側穏健派の月本がいる。
ここで芽衣が好きと答えてくれれば……僅差で食べる派が勝てる……はずっ!
緊張が走る中、芽衣は満を持して、口を開いた。
「パセリですか? 私は食後の口直しとして食べますよ」
「「「……………………」」」
想像の斜め上を行く回答に、三人は言葉を失った。
食後の口直し。つまり食材として食べはするが、味わうわけではない。
それは、食べる側穏健派という新たな勢力誕生の瞬間であった。
「……うまーいこと、フィフティフィフティで分かれた感じだな」
「そうだな」
「食べるにせよ食べないにせよ、おおよそ必要とされてるのは良いことなんだよ、たぶん。パセリ農家さんにとってもね」
三人で和やかに笑い、結論はまだ出さない結論に自然と収束した。
そんな中芽衣は、「どういうことですか?」と不思議そうな顔をするのだった。
パセリ論議はまだまだ決着には至らない。
俺はパセリ農家さんのためにも、食べる派の勢力拡大をここに誓う。
三月下旬、だれもが待ち望んだ桜の開花が発表された。
休日の花見へ向けて、大人たちはにわかに浮き立ち、春休み中の学生はあからさまに浮き立つ。
そんな街中が浮かれるさなか――俺は、風邪をひいた。
「三十八度三分、完全に風邪ね。吐き気はある?」
「それは、大丈夫……。ただ、頭がふらふらする……すっげーだるい……」
自室のベッドに横たわりながら、俺は母親に症状を説明する。
前日の夜からなんとなく予兆は出ていたが、今日の朝になって一気に襲ってきやがった。おおよそ一年に一、二度強烈なのが来る体質だが……まさかこの時季に来るなんて……。
「早く治したいのなら、今日は絶対安静ね。母さんはこれから友達と映画だから、世話は出来ないけどね」
薄情な母親である。息子の体温が三十八度三分もあるのに、友達と映画て。
「め、芽衣は……?」
「ああ、あの子はいるみたいよ。さっきあんたのこと言ったら、『マジけ! 家兄が風邪っぴきっ? こうしちゃいらんねえ!』って言ってなにか準備してたわ」
やべえ、追い込みかけられる……妹に弱っているところを突かれる……っ!
「ちょっと呼んでみるわね。芽衣ー、ちょっと来てー」
「い、いや別に呼ばなくて……」
と、制止したにもかかわらず、即座に「はーい!」という返事が扉の向こうから聞こえてきた。そうして入ってきたのはもちろん……。
「呼ばれて飛び出せジャンバラヤ、白衣の天使芽衣ちゃんだよー」
みんな大好き芽衣ちゃんでしたー。あ、吐き気してきた。
おおかた予想できていた芽衣の登場であったが、解せないことが一つある。
「おい芽衣……なんだ、その恰好……なにボロボロの白衣着てんだよ……」
なにかうきうきしている芽衣は、部屋着の上に白衣を羽織っている。しかしその白衣は所々焦げていたり破れていたりと、ズタズタになっていた。
「コスプレするにしてもナースだろ……なにがしたいんだよ……」
「芽衣ちゃんはビジュアルよりも実力を重視するタイプなのです。だから今回は野戦病院の女医さんをイメージしてみましたー。どうよ家兄、この躍動感」
「やだやだ助けて、こんなのに看病されたくない。意味不明だもの。理由を聞いてなお、意味不明だもの。お願いだから今の俺を、こんなのと二人きりにしないで」
重い身体にむち打ち、母親へ必死に懇願する。すると母親は立ち上がり、言い放つ。
「良かったわね家之助、良い妹を持って。じゃ」
「薄情者! 化けて出てやる、野戦病院で亡くなった霊を引き連れて化けて出てやる!」
訴えもむなしく、母親はさっさと部屋を出て行った。
それを見送ると、芽衣は愉悦に浸ったような笑顔で、呟く。
「やっと二人きりになれたね、家兄……ドクトル芽衣ちゃんドキドキしちゃうぜ」
遊ばれる遊ばれるー。自由がきかないことを良いことに、妹に弄ばれるよー。
「あの、ドクトル……俺、寝ますね……睡眠が最高の治療って言いますし……」
「ええー? せっかくマリオカート持ってきたのにー。やろうよー、平日の朝からマリオカートやーろーうーよー。マリオカートが最高の治療だよー」
くそう……ひっぱたきたい……こんなときに俺は、無力だ……。
虚無感に苛まれていたが、ふと後頭部にひんやりとした感覚が広がる。
「なーんて冗談だよ。ほれ氷枕。あとこれも貼っときー」
芽衣は俺の前髪をさっとよけ、冷却シートを貼ってくれた。額と後頭部の熱が吸い取られていき、心地が良い。
「あ、それと、ちょっと待ってて」
そう言って芽衣は立ち上がると、白衣をなびかせながら部屋を出て行く。ものの一分ほどで帰ってくると、その手には小さな土鍋を持っていた。
「ほい、おかゆだよー。寝る前にちょっとでもお腹に入れたほうがいいよ」
「おかゆって……これ、おまえが作ったのか……?」
「うん、そうだよ(ホントはお母さんだけど、ここで恩を売っておいて損はないね)」
「……ありがとう、芽衣。うれしいよ」
「おっ、風邪っぴきの家兄は素直だね。うんうん、いいことだ」
芽衣は満面の笑みで、俺の頭をわしわしと撫でていた。
「さ、早く食べな」
「……うん」
「一回寝て、起きたらマリオカートやろ?」
「……やる」
そうして俺は、芽衣が見守る中で、芽衣特製のおかゆを口に運ぶ。
それはまるで芽衣の優しさが内包されているようで、じんわり味覚がよろこんでいく。
さらに、鼻が詰まっていてもわかる……舌がとけそうな刺激的な味わい…………。
「ちなみにそれ、ニンニク五個ほどすりおろして入れてあるから」
「ぐわああああああああっっ!」
辛さに悶絶する俺に、芽衣は「あははははっ!」と爆笑していた。
俺で遊ぶことにおいては他の追随を許さない芽衣は、今日も今日とて悪魔であった。
献身的な妹を持つ方よ……頼むから、コレと交換してくれ……。
放課後、生徒会室の前にて俺は突っ立っていた。
なぜそんなことをしているかと言うと、秋が生徒会室の鍵を教室に忘れてきてしまったのだ。なので秋は現在取りに戻っている。
また、月本と芽衣は掃除当番らしく、生徒会に遅れると事前に報告があった。
なので今、生徒会室前で待ちぼうけを食っているのは俺、そして……。
「……………………」
無表情の似合う、近江教諭のみであった。
無言で俺の横に立つ近江教諭。前々から思っていたが、本当になに考えているかわからない人だ。だからこそ、妙な威圧感がある。
気まずい沈黙の流れる現場にしびれを切らした俺は、おそるおそる世間話を敢行する。
「あ、秋のやつ遅いですね」
「そうですね」
「「……………………」」
大変。会話がまったく続かない。いやっ、まだめげない!
「そ、それにしても、今日はちょっと暑いですね」
「そうですね」
「こう暑い日は、扇風機の前で『ア、アノ……ワ、ワレワレハ……ソノー……』と目線を逸らしながら呟く、人見知り宇宙交信ごっこに限りますね!」
「そうですね」
「…………すみません、意味わからないですね……」
「そうですね」
「…………」
泣きそうだった。ダメだ……この人の辞書に『友好的』という文字はない……。
「……そんなに沈黙が気になるのなら、なにか暇つぶしでもしますか?」
「えっ?」
近江教諭の意外な提案に、声がうわずってしまった。
またとないチャンスだと、俺は何度も頷いて誘いに乗る。
「では、しりとりでもしましょうか」
「し、しりとりですか……?」
「ええ。私、結構得意なのです」
ありきたりなゲームで驚いたが、どうやら近江教諭はやる気なので、従うことにする。
「では、おーみきょーゆからどうぞ。しりとりの『り』から」
「わかりました……リピーター」「タヌキ」「北」「タイヤ」「屋形」「宝」「ライター」「台風」「歌」「タレント」「淘汰」「た……田辺」「ベジータ」「た……た……タンゴ」「ゴジータ」
「…………まいりました」
完敗である。やだなにこの『た』攻め。なんでこの人、ノータイムで尻に『た』のつく単語が出てくるの? そんで俺も弱すぎだろ……なんだよ『田辺』って……。
「弱いですね、松尾」
「い、いや卑怯です! 一文字攻めはずるい!」
「そういう戦法なのですが。では仕方ないので、一文字攻め禁止でやりましょうか」
「それなら! 今度は負けませんよ!」
そうして、今度は俺から『り』ではじまる。
「りんご」「拷問術」「つみき」「鬼畜」「くじら」「拉致」「ちらし」「死亡」「うみ」「皆殺し」「しか」「過度の期待」「いちご」「傲慢な上司」「しごと」「父さんが株で失敗」「い、いか」「母さんのみそ汁あと何回飲めるのかな」「な……な、なみだ」「だれでもいいとは言ったけど、君じゃないよね……」
「楽しくないっっ!」
思わず叫んでいた。やだやだなにこのネガティブしりとり。なんでこの人ノータイムでネガティブな言葉が出てくるの? 後半もう文章だったし。
「やだこのしりとり! すっごいやだ! 精神攻撃はやめて!」
「相手のメンタルから傷つけていく戦法なのですが」
「おーみきょーゆがしりとり強いのはわかりましたから、別のにしましょう!」
そう提案すると、近江教諭はすぐさま代案を挙げた。
「では、山手線ゲームにしますか」
「いいですね。……言っておきますけど、ネガティブなのはなしですからね」
「わかってます。最近の若者は精神力が足りませんね」
いつの時代の若者だって耐えられないよ、あんなしりとり……。
「私がお題を出しますね。では……近江教諭からはじまる、山手線ゲーム。いえー」
「いえー」
「好きなひらがな」
「…………」
パンパン。
「ぬ」
パンパン。
「み」
パンパン。
「の」
パンパン。
「ま……ストップ。おーみきょーゆストップ」
「なんですか、松尾」
「楽しいですか? これ楽しいですか?」
延々ひらがなを一文字ずつ言っていく山手線ゲーム。どこまでもシュールである。
「私は結構楽しんでましたけど。なかなか白熱した良い試合だったかと」
「今のどの部分に白熱した要素があったんですか……? 他のゲームにしませんか?」
きっとこのまま山手線ゲームを続けても、近江教諭のシュールな思考に呑まれるだけだ。
すると近江教諭は顎に手を当て、考える素振りを見せる。
「ほかにここで出来る遊びと言ったら……人体の痛点を実験的に検証するゲームか、にらめっこくらいでしょうか」
「にらめっこにしましょう。絶対にらめっこがいいです」
前者はもう遊びじゃないもの。確実に俺が実験台にさせられるもの。
いやでも、にらめっこって……常に無表情を貫いている近江教諭に、果たして出来るのだろうか……?
「では早速やりましょうか」
「は、はい」
「「にーらめっこしーましょ、わーらうとまーけよ…………」」
「いやーごめんごめん。鍵持ってきた……ぞ……?」
間もなく、秋が生徒会室の鍵を持って到着した。
秋は不思議そうに、平然とした近江教諭、そして地面に這いつくばる俺に声をかける。
「どうしたんですか……? なにやってんだ、家之助……?」
「……くっ……うっ……ふふっ……あはははははははっっ!」
直後腹を抱え、爆笑しながらのたうち回る俺を見て、秋はぎょっとした。
「なっ……どうしたんだ家之助! なにがそんなにおかしいんだ!」
「む、むり……しゃ、しゃべれねえ……ひあははははははっっ!」
「な、なにが……なにがあったんですか、近江先生……?」
俺では話にならないと思ったのだろう、秋は尋ねる相手を変更する。
その質問に、当人は小さく頷くと、ゆっくり口を開いた。
「まあ簡単に言うと……この三連戦、私の三タテということです」
近江教諭は、いつもの冷静な表情で答えるのだった。
「結局のところ、家兄は秋さんに彼女ができるのを待つのが無難だね」
朝の登校時、いつの間にかはじまっていた俺の恋愛相談は、校門をくぐったところで佳境を迎えていた。
専属講師の妹、芽衣は議論の末、前述のような結論を弾きだした。
「家兄の周りにいる女の人はみんな、秋さんに目がいってるわけだからね。家兄なんて眼中にないのですよ。だから、圧倒的実力差のあるライバルが戦線離脱してから行動に移すのが、最善ってこと」
「うぐぐ……いやだ! そんな後手後手な戦法、やりたくない!」
「その考えが現実的じゃないんだって。見た目・学力その他諸々完璧の秋さんを、変な顔で頭の悪い家兄が負かせるわけないって」
「うるせえ! 俺は秋よりも先に彼女を作って、あいつにぎゃふんと言わせたいんだ!」
「器が小せえ……てか、家兄に彼女が出来ても、秋さんはぎゃふんとも言わないと思うけど」
たしかに……あいつなら素直に祝福してくれそうだ……。
不毛なのか? この願望は不毛なのか?
「じゃあ、家兄が秋さんに告白してみたら? きっとぎゃふんと言うよ?」
「そんな展開、俺がぎゃふんだよ」
小悪魔な表情でありえない提案をする妹の頭を、手刀でコツンと叩く。芽衣はにやつきながら「うへっ」と気持ちの悪い悲鳴を上げていた。
「とにかく、今はあんまりがっつかないほうがいいと、忠告はしたからね。んじゃ」
そう言って芽衣は一年のクラスが集合する校舎へと向かっていった。
受け入れがたい現実に嘆息しつつ、俺も自身の教室がある棟を目指した。
しかしこのとき――予想だにしなかった出来事が、巻き起こっていた。
俺はもやもやと思案しながら、下駄箱に手を伸ばす。
「……ん?」
その瞬間、触覚と聴覚が異変に気付いた。
俺の手が、およそ上履きからは得られないさらりとした肌触りを感じた。さらにこれまた上履きからは発することのない、紙の擦れ合うような音を、鼓膜が捉えた。
その原因を、下駄箱から取り出してみる。
「こ、これは……っっっ!」
それはまるで後光がさしているかのように、ペッカーと輝いていた。
桃色を基調としたそのフォルムはスマートかつシャープ、穢れを知らぬ長方形。月のない夜の金星のようなハートシールで閉じられた封入口からはどこか甘い香りが漂う。表面には、桜色の海でその存在を主張する『松尾家之助君へ』という文字。
春の河のような、夏の雲のような、秋の楓のような、冬の雪のようなこれはまさしく――。
「ラ、ラララ、ラブレレレレレレレレレレレッ!」
目がバタフライし、膝が抱腹絶倒してしまう、これはまさしく――ラブレター。
俺は走っていた。
廊下は走るな? 注意できるのなら、してみるがいい。
光の速さで廊下を走る者を、一体だれが注意できるのだろうか?
そんな天文学的スプリンターの向かう先は、ただひとつ。
「めーーーーいちゃーーーーーん! めーーーーいちゃーーーーーーーーーーーーん!」
妹の元だ。学園内に響き渡るようその名を叫びながら、俺は駆ける。
火花が出る勢いで扉を開くと、芽衣のクラスメイトが驚いた表情で俺を見る。そんな中、俺の存在を認めた芽衣は、言い放つ。
「おばあちゃんっ!」
「だれがおばあちゃんか」
俺は一瞬で芽衣の席まで近づき、その身体を小脇に抱えた。
「お兄ちゃんエマージェンシーだ。ちょっち来い」
芽衣は疑問を浮かべる友人たちへ、やさしい笑みを振り撒く。
「大丈夫。うちの兄、たまにこうなるの。心配しないで」
俺は抱える妹のパンツを不特定多数の野郎共に見られないよう、しっかりスカートを押さえながら、再び廊下を駆け抜けていった。
到着したのは生徒会室。ここなら今の時間、だれも来ることはない。
早速俺はハンカチで包んでいた、例のブツを芽衣に見せる。
芽衣はそれを目にすると、無表情から驚愕の表情へとグラデーションさせていく。
「え、えええっ! こ、これもしかして……ラ、ララ、ラブレエエエエエエエッ!」
「そうだよな! この感じどう考えてもラブレエエエエエエエだよなっ!」
「家兄にラブレエエエエエエエなんて……正気の沙汰とは思えないよ!」
「そうなんだよ! 正気の沙汰とは思えないんだよ!」
兄妹揃って一枚の手紙に激しく動揺していた。すると突然、生徒会室のドアが開いた。
「なんだ松尾兄妹か。だれが騒いでるのかと思ったわ……」
「おはよー二人とも。廊下まで声聞こえてたよ? どうしたの?」
秋と月本だ。二人は狼狽する俺たちを見て、首を傾げている。
「な、ななななななんで、ふふふふふふた、ふた、ふたりとも、こ、ここここここに?」
「昨日ここに忘れ物したんだよ。それより、動揺しすぎだろ……」
「私は秋とばったり会って。付き添い、みたいな?」
呆れた表情の秋とどこか嬉しそうな月本。そんな二人に、芽衣は震えながらブツを掲げる。
二人は、芽衣と同様の反応を見せた。
「こ、これもしかして……家之助に、ラブレ……ッ!」
「そうだよラブレだよ! ラブレなんだよ! 生きたまま腸に届くんだよ!」
「松尾くんにラブレなんて……正気の沙汰とは思えないね」
「そ、そうだよな。正気の沙汰とは思えないよな……」
なんだろう。自分でもそう認めていたが、月本に言われるとなんか切ない。
驚きの共感相手が一人から三人に変わり、朝の生徒会室はさらに沸き立つ。
「で、だれからのなんだ、家之助っ?」
「いやそれが、どこにも名前がないんですよねー」
見ると、芽衣が勝手にラブレターを開き、読み込んでいた。そして月本も、芽衣の後ろから興味津々といった顔で盗み見ている。
「おい! 俺より先に見るんじゃない!」
糾弾し、無理矢理取り返す。文面を見てみると、たしかにどこにも名前はなかった。
「差出人の名前がないってのは、不思議だねー」
「恥ずかしかったんじゃないですか? もしくはサプライズ。今日の放課後までもったいぶるつもりなのかも」
「ん? 今日の放課後?」
俺が疑問を投げかけると、芽衣はラブレターの最後の一行を指差した。
『本日の放課後、屋上で待っていてください』
一瞬にして、顔が熱くなった気がした。
あっという間にやってきた放課後。
俺はひとり、屋上にて人生史上最高の緊張を噛み締めていた。
きっと今日のこの日のことは、おじいちゃんになっても忘れないだろう。はじめてのラブレター……はじめて異性から好意を寄せられた、高二の春。
しかし、ちょっとだけ気になるのは、あの子のこと。
俺がラブレターをもらったことを、素直に祝福してくれた。なんのひっかかりもなく、純粋に喜んでくれた。
その笑顔の中にほんの少しでも抵抗があったならよかったと、そう考えるのは、思い上がりなのだろうか。でも、そんなのあたりまえなんだ。
だって俺は、月本のことが――。
そのとき、屋上の扉が開いた。瞬間、心臓がバクンッと鳴る。
そして、姿を見せたのは……。
「……は? 秋?」
なんと秋だった。なにしに来たんだ、こいつ。
「どうしたんだ……あっ! おまえもしかして、野次馬だなっ? やめろよー、俺の一世一代のイベントの邪魔すんな……」
「ちがうよ」
通る秋の声が、スパッと俺の言葉を切った。その顔にはめずらしく感情が見えない。
「ちがうって……じゃあなにか用か? 後にしてくれよ。これからラブレターの子が……」
「俺……いや、わたしだよ」
「……へ?」
「わたしが、ラブレターの差出人なんだよーーーーーーっ!」
秋はそう叫びながら、超高速で俺との距離を縮めると、真っ赤な顔で飛びついてきた。
「うおわああああっ! な、なんだよ秋! なにしてっ……!」
おかしい。胸元に、なにかむにゅっとした感触がある。
おそるおそる視線を下ろすと、俺に抱きつく秋の、その胸が……膨らんでいた。
「な、ななななななっ……おまえ……なんで胸が……っ?」
「なんでか? 決まってるじゃん! わたし一ノ瀬秋は、女の子なんだよーーーっ!」
「ええええええっ!」
「しかも、家之助のことが大好きなんだよーーーーーーーっ!」
「ええええええええええええええええっっ!」
動転する俺など気にもせず、秋は俺にごしごしと頬ずりをする。離れようにも、足と手が完璧に巻きついているため、無理だった。
可愛いのだ。元々中性的な顔立ちのせいか、たしかに可愛く見えるのだ。
しかし……男だと、親友だと思っていた、秋なんだぞ……っ!
「さて、じゃあ誓いのキスでもしようか……家之助……?」
「いやなんの誓いだよっ!」
「きにしなーいきにしなーいっ! いくよーーーんちゅーーーーーっ!」
「うわああああああああああっっ!」
そして、秋の唇が俺の唇に接近し、ついにはくっつきそうに――。
ジリリリリリリリリッッ!
「ぎゃあっ!」
目を開くと、そこには自室の天井。
布団にくるまっていた俺は、滝のような汗をかいていた。
こ、これは、もしかして……。
「まさかの、夢オチですか……?」
理解した瞬間、がくーっと身体から力が抜けた。同時に、心からの安堵がため息として吐き出された。
「よ、よかった……夢でよかった……」
もはやはじめてのラブレターが夢でしかなかったことさえ、どうでもいい。
衝撃告白からの超絶変化を果たした秋……思い出すだけで身震いがする。
本当に、夢でよかった……っ!
『夢じゃなかったりしてーぬへへへーーー』
「ひいいいいっ!」
なにやら変態性溢るる声が聞こえた気がしたが、周囲に異変はない。
どうやらあまりに衝撃的な夢に、幻聴さえも引き起こしてしまったらしい。
二度とこんな夢を見ないように。
そう心に誓って、俺は朝の準備をはじめた。
平日お昼のショッピングモール、その雰囲気はなかなか新鮮である。
春休みで学生らしき姿はちらほら見かけるが、休日と比べれば全然人が少ない。
「まあ学生とかは、向こうの映画館やらゲーセンにいるんだろ」
隣で紙袋を片手に上機嫌な秋は、もう一方の手で隣接するアミューズメント施設の方角を指差した。
本日俺は秋に誘われ、街の郊外にある大型ショッピングモールに来ていた。
目的もわからず付いてきたが、寝室の電気スタンドがほしかっただけのようだ。ご所望の商品は、すでに秋の手に収まっている。
「大変だな、一人暮らしは。そういうのも自分で買いに来ないといけないのか」
「まー大変さと快適さで、半々ですよ。少なくとも我が家をひとりでカスタマイズできるのは楽しいよ。俺、寝室は特にこだわりたい派だからさ」
そう言って秋はウインクを飛ばす。男のくせに中性的な顔立ちをしているため、ちょっと可愛く見えるのがムカつく。
「はあ……せっかくの春休み、おまえとじゃなく、女の子と過ごしたいなあ……」
心からの本音を漏らすと、秋はなにかムッとした。
「おおっと? 俺じゃ不満かこのやろう」
「おまえというか、俺の宿命に不満を持っているんだよ」
「うまくいかないことを運命のせいにするやつほど、モテないんだよね」
くっ……悔しいが、その通りだ……。自戒、自戒。全部俺が悪いのです。
「……そんなに女の子とデートしたいなら、いっちょ練習してみるか?」
「練習? いつ、どこで、だれと?」
「今、ここで、俺と」
「…………」
なにを口走ってるんだ、この男は。
「いつか来る初デートで緊張しまくって漏らさないように、実践訓練しようって言ってんだよ。いやー、いい親友を持ったね、家之助くん」
「いくら緊張しても漏らさねえよ。それでなに? おまえを女子と見立てて仮想デートするってことか? やめろよ、気色悪い」
「いやほら、おまえがさっき思った通り、俺って中性的で女だとしてもけっこう可愛い顔してるだろ? だから、いい練習になると思うんだ」
「さらっと心を読むな。そしてなんだその自信は。くだらないこと言ってないで、どっかでメシ食おうぜ」
俺はショッピングモールのフロアマップを眺め、昼食の候補を探す。
「おっ、このばくだん丼うまそうだな。この海鮮丼屋にしよ……」
「アウトゥッ!」
「えっ」
突然謎のアウト宣告をする秋に、俺はビクッと震える。
「デートで納豆オクラねばねば丼なんて言語道断だよ! なに考えてんだおまえは!」
「デートの件終わってなかったのかよ! マジでやる気かっ?」
「あたりまえだ! やるといったらやるんだ!」
なにがトリガーとなったかは不明だが……秋さん、強情モードに入ってしまったようだ。これはもう、素直に従ったほうが後々楽なパターンだ。
しかし、一体なにがそんなに秋を突き動かすのか。
「わかったよ……で、じゃあなに食べたいんですか、お嬢さん」
「おばか! 女子に決めさせんな! こういうのは男がビタァッと決めるもんやろ!」
「その擬音はよくわからないが……わかったよ。デートってめんどくせえな……」
検討の末、安めのイタ飯屋を提案したところ、及第点をもらった。なので連れ立ってそこへ向かうことに。
役に入っているのか、隣を歩く秋はしずしずと、どこか女の子っぽい雰囲気を醸し出す。器用なやつだとは思っていたが……こんなこともできるとは。
まるで本当に女の子みたいな……。
「アウトゥッ!」
「えええっ!」
またも唐突なアウト宣告。俺はすぐさま異議を申し立てる。
「ちょっと待て! 俺、なにもやってないだろ!」
「それが問題なんだよあんぽんたん! これ見てなにも思わないのかっ!」
秋はご立腹な様子で、紙袋を掲げてみせる。
「電気スタンドだろ、さっき買った……それがなに……?」
「オマエ、テブラ! ワタシ、オモイモノモツ! オモテナシ!」
なぜ片言なのかは不明だが……どうやら荷物を持ってほしいとのことだろう。
「わかったよ……ほら」
紙袋を受け取るも、秋はむくれたままだった。
「まったく……こんなの常識だよ。あとアウトゥッがひとつで、アイスおごりだからな」
「なんでだよ! 聞いてねえぞ!」
「俺にこんなことさせてるんだ、あたりまえだろ。アウトゥッにならなきゃいいんだよ」
「おまえが勝手にやってるんだろうが! あとさっきからアウトの発音が独特すぎてムカつくんだよ!」
俺の反論はどこ吹く風と、秋は知らん顔で口笛を吹いていた。こいつ……。
デートの相手に若干の苛立ちを覚えながらも、改めてイタ飯屋へ向かう。
目的地は最上階にあるようなので、エスカレーターでそこを目指す。
ふと、俺の一段後ろに立つ秋を見ると、んがーっと大あくびをしていた。
「眠そうだな、どうした」
「んー、ちょっと眠れなか……じゃなくて、夜更かししててな、あはは。……ていうか、女子のあくびをまじまじと見てんじゃないよ!」
「女子じゃねえだろ……」
むきーっと勝手に怒っていた秋だが、天窓から差し込む強い日差しが顔に当たった瞬間、頭をふらつかせた。貧血か? と思ったそのとき……。
「おい!」
「……え?」
よろめきそうになった秋の肩を、とっさに掴んで引き寄せる。
「大丈夫か、秋? 今ふらーっとしたろ」
「だ、だいじょぶ……うん、だいじょぶ……」
正気に戻ったのか、秋はぽそぽそとそう呟いた。
ただその顔はほんのり赤い。やっぱり調子悪いのか?
「せ、せんたーまえ!」
すると秋は、こんな意味のわからないことを叫んで、俯いた。せんたーまえって……。
「ああ、センター前ね……それでもシングルヒットなのかよ」
一応は、褒められたらしい。
「さ、さあ飯屋いくぞ! イタ飯屋!」
秋はエスカレーターから離脱すると、ふらついたのがウソのように、はしゃいでいた。
「……えへへ」
先導する秋は、なにか自らの肩を撫でている。その横顔から見える目尻は、とろんと下がっているように見えた。
「…………」
それが少しだけ可愛く見えてしまった俺は、やはりおかしいのだろうか。
ちなみにその後も、秋による仮想デートは続いた。
結果として俺はもうひとつアウトカウントをもらい、アイスをおごる羽目になったとさ。
「――そんなわけでさ、結局アイスおごらされたんだよ。仮想デートとか言って、ハナから俺をハメてアイス食いたかっただけなんだよ、秋のやろう」
現在俺は、本日行われた秋との仮想デートに対する愚痴をかましていた。
その相手はもちろん、妹である。
夕飯後、芽衣は特に理由もなく俺の部屋を訪れ、ベッドで漫画を読んでいた。
なのでその場所代として、愚痴の相手をさせていたのだ。と言っても、どうせ俺の話はその右耳から左耳へ通過しているのだろうけど。
しかし愚痴を終えると、芽衣はパタンと漫画本を閉じる。
その顔が俺に向いた瞬間、とても嫌な予感がした。
「……いいね、それ」
なぜなら、瞳がキラッキラ輝いていたのだから。
「……な、なにがだ?」
「仮想デートですよ。実に生産的でステキな訓練だ。何度でも行うべきだと思うね、私は。というわけで、この献身的な妹も手伝ってあげるよ、家兄」
「俺にはおまえがタダでアイス食いたいだけの妹に見えるんだけど、どう思う?」
「冷静な分析でいいと思います」
悪びれる様子が一切見られないのが、清々しい。
「そんなわけで、明日は家兄とショッピングだー、わーい。集合時間は十時ね。集合場所は松尾家リビングで」
あれよあれよという間に計画が具体化していくー。しかも待ち合わせ場所うちって……仮想デートだというのに、ロマンが微塵もない。
「雨降ったらどうすんだよ」
「雨は……降らない」
「神様かおまえは」
我が妹、もう完全に乗り気である。現時点ですでにアイスの口になってやがる。どんだけアイス食いたいんだ、こいつは。
「なに家兄、その不満そうな顔ー。せっかく可愛い妹が協力してやってるのにー。あーあ、こういうとき『ありがとう芽衣、兄ちゃん一生懸命訓練するぜ。お礼にとびっきりうまいもん食わせてやるからな』って言ってくれる兄がよかったなあ」
「どんぐりでも食ってろ」
「イベリコ豚じゃねえんだよ、私は。…………だれが豚じゃーーーいっっ!」
「ぎゃあああああ、ごめんなさいごめんなさいっっ!」
翌日、俺は妹によって、まんまとショッピングモールへ連れ出されていた。
「さーあ、仮想デートという名のおねだりショッピングだー」
「せめて心の中で思えよ……」
ショッピングモールに到着すると、早速芽衣は上機嫌だった。俺はと言えば二日連続の買い物、しかも貢がされること請け合いな現状に、ため息しか出ない。
「さてさて、じゃあ一応は仮想デートなわけだから、理想の彼女役を演じてあげようか。どんな女の子がいい、ダーリン♪」
「じゃあおっぱい大きい子で……」
バキッ。
「と言っても、あまりかけ離れてもリアリティがないからね。年下でコミュ力が高い、妹キャラの超可愛い女の子ってことでいいね? はい指名入りましたー」
「あとできれば暴力的じゃない子でお願いします」
鼻血を垂れ流しながら、俺はそう懇願するのだった。
ていうかその彼女役……限りなくおまえじゃねえか。超可愛い以外。
しかし俺の異議が通るはずもなく、妹との仮想デート、その幕は勝手に上がった。
アパレルショップにて。
「ねえ。これとこれ、どっちが良いかな、ダーリン」
「うーん、どっちでもいいけど……両方試着して決めれば?」
「それもそーだ、じゃあ家……ダーリン、荷物持ってて」
「もう別に家兄でいいんだけど」
「覗かないでね、ダーリン♪」
「しゃらくせえ……」
アロマショップにて。
「わー、これオレンジの香りがする香水だってー。ほしいなー」
「おまえこんなん付けてたら、年がら年中みかん食ってるやつだと思われるぞ」
「デリカシーの欠片もねえな……そんなこと言うダーリンには、えいっ!」
「うおっ、吹きかけんな……って、良い匂い! 俺すっごい良い匂い!」
昼食時。
「私ラーメンがいいなー。家兄と来たときしか食べられないし」
「俺は海鮮丼が食いたいんだけど」
「おっと対立したねえ……じゃあ公平に、じゃんけんで決めようか」
「……いや、おまえチョキとか言って目潰ししてきそうだから……ラーメンで良いや」
「いくら私でもそんなことはしないよ……」
食後。
「まーラーメンと来たら、アイスですよねー」
「絶対言うと思ったわ……いいよもう、好きなの選べ」
「わーい家兄大好き! ミミズクの次くらいに好き!」
「そこそこランク低いだろ、それ……俺はどれにしようかなー」
「家兄はあのナッツのやつが良いと思うなー。似合うと思うなー」
「あとで『それ一口ちょうだい』って言わないなら、それにしようかな」
「家兄のいけずー」
その後もメンズショップや雑貨屋、本屋などを二人で回った。
ある程度満足したところで、芽衣が歩き疲れたと言うので喫茶店に入る。
「おまえ先に行って席とっとけ」
「おっけー。私、ロイヤルグレネードミルクティーね。アイスの」
「はいはい、ロイヤルミルクティーね。アイスの」
芽衣の待つ席へ、グラスを二つ持って向かう。芽衣はロイヤルミルクティーを喉を鳴らして飲むと、「ぶへー」っと生き返ったような声を上げた。
「いやー買った買った。そして食った食った」
「満喫したなー」
そうして兄妹二人でまったりムードに突入する。が、ふと疑問が浮かぶ。
「そういや俺たち……なにしに来たんだっけ?」
「え? ……あれ? そういえば、なにか目的があったような…………ああ、アレだよ。仮想デート」
「ああ、それだ」
すっかり忘れていた。てか途中から、設定もなにも完全になかったことになっていた。
「結局、妹との買い物でしかなかったな」
「彼女設定が私に近すぎたね。いつの間にかいつもの感じになってたわ」
それぞれ感想を漏らし、俺たちは同じタイミングでストローに口をつける。
互いに喉を潤し、ひとつため息をつく。
そして同時に呟くのだった。
「「まあ、楽しかったからいっか」」
「えっ、秋さんあのシリーズ全巻持ってるんですかっ?」
芽衣のこんな声が聞こえたのは、春休みの生徒会室、昼下がりのことだ。
現在室内には俺と秋と芽衣のみ。月本は家の用事で十分ほど前に帰宅した。
そして俺たちもぼちぼち帰る雰囲気になってきたころ。俺が真面目に仕事をしている最中、なにがしかの漫画の話で秋と芽衣は盛り上がっていた。
「うん。おもしろいよーアレ。もう十回くらい読み返したかも」
「へー、へー。いいなーいいなー読みたいなー」
「じゃあ貸してあげようか?」
「いいんですかっ?」
どうやら契約成立のようだ。というか芽衣は完全に貸して貸してオーラ出してたし。
「じゃあ明日……と明後日は休みだから、次の月曜日に持ってくるよ」
「え、いやアレ全巻ってなったら重いでしょう? ……そうですね、じゃあ今日、私が秋さんちに借りに行きますよ!」
「ええっ、それは芽衣ちゃんが大変でしょ」
「大丈夫です。うちの若い衆を連れて行くんで」
「それ絶対俺のことだろ」
会話から弾かれていたが、聞き逃す俺ではない。若い衆て……一人しかいねえし。
「いいじゃん家兄ー、手伝ってー」
「いや普通に、日別で小分けして借りればいいだろ」
「いーやーっ! 明日と明後日丸々使って読み切りたいのーっ!」
どこまでもエゴな要望である。
しかし結局押し切られてしまい、芽衣とともに秋の家を訪問することとなった。
秋はまぎれもなく親しい友人だが、そのマンションは我が家からそこそこ距離があるため、そんな頻繁に訪れてはいない。試験勉強などの大義名分がなければ、わざわざ行くのも億劫なのだ。
「おおー良い部屋ですねー! いいなー!」
ちなみにはじめて秋の家に来た芽衣は、このように興奮していた。
「はい、これで全巻だね。紙袋に入れようか」
「わーありがとうございます。帰ってからじっくり読みますー」
芽衣は数十冊の漫画本が入った紙袋を受け取ると、流れるように俺に手渡した。こいつ……俺のこと召し使いかなにかだと思っていやがる……。
来訪の目的を終えると、俺たち三人はソファに座り、まったりする。
そこで芽衣は秋に、なんでもないように尋ねる。
「ところで秋さん、エロ本はどこですか?」
「ぶっ!」
言下、秋は麦茶を吹き出しかけていた。
「いやそれが教えちゃくんないんだよ、こいつ。持ってないとか言って」
「えー、それはウソでしょー? エロ本持ってない男子高校生なんていないでしょー」
「いやいやいやっ、いろいろおかしい! 持ってない男子高校生だっているし、この男子高校生的なノリになにを率先して参加してるんだ芽衣ちゃん!」
この場合正しいことを言っているのは秋だろう。だが、我が家でその常識は通用しない。
「まあひとえに、俺の教育の賜物だよね」
「この兄貴、年頃の妹がいるのにエロ本無造作に置いてますからね」
「こいつも中学くらいまでは、がんばって目を逸らそうとしていたけどな。あの頃は可愛かったなあ……」
「ウブなネンネじゃいられねえんですわ、もはや」
「この兄妹……」
説明した後も、秋は信じられないものを見るような目をしていた。文化の違いかな。
「私も成長したのです。最近は無造作に置かれているエロ本はカモフラージュで、見られたくないガチの本命は別にあることも知ってますしね」
「えっ! ウソ、バレてたのっっ?」
「バレバレだよ。コンビニで一般誌読むフリしながら横目でエロ本吟味してる家兄くらいバレバレだよ」
「ええっ! そっちもバレてたのっっ?」
「そんで帰宅してすぐ、『あ、消しゴムほしかったんだ。もう一回コンビニ行ってくるわ』って言って、DVD付きのロシア人もの買ってきたのも、バレバレだよ。ちなみに本命枠」
「いやあああああああああっっ!」
成長著しすぎだろこの妹! もう俺の想像を越えてきやがった!
「というわけで、兄のおかげでエロ本に抵抗はありませんぜ、私は。なんで、言っちゃいましょうや秋さん……お宝の在り処を……」
「いやだから、持ってないって……ホントに……」
ここまで言いやすい状況を作ってやったのに、秋はまだこんなことをほざいていた。もしかして、本当に持ってないとか? いやいやそんなのありえない。
「別に秋さんがどんな好みを持ってても引きませんよ? まあ家兄がロシア人の彼女さん連れてきたら、さすがに驚くでしょうけど」
ふと、芽衣が口にしたこの発言。俺は待ったをかけずにはいられなかった。
「芽衣よ……いずれおまえがその勘違いを口にして恥ずかしい思いをするのが、俺には堪え難い。だから、ここではっきりさせておく。その発言には、誤りがある」
「え……どういうこと、家兄?」
「その発言自体が恥ずかしいとは思わないのか、この兄妹は」
秋がなにか言っているが、今はそれよりも大事なことがあるのでスルーする。
「芽衣……男にとって、恋とエロは別物なんだ」
「なっ……!」
雷が落ちたように驚く芽衣。対して秋は恥ずかしそうに俯いていた。
「こんな名言がある。『男の上半身と下半身は、別の生き物である』。つまり股間が反応する女性のすべてが、彼女にしたい女性というわけではない。いっしょにいてデートとかしたい女性と、ただただスケベしたい女性はちがうんだ」
「なんて最低な発言なんだ……」
「な? そうだよな、秋?」
「同意を求めるなっ! そんなこと思ってないわっ!」
真っ赤な顔の秋はそう言及する。なにをカマトトぶってんだこの男は。
秋とはちがい、理解力の高い芽衣はすべてを飲み込み納得した表情だ。
「たしかに……家兄のエロ画像フォルダにはいかにもギャルっぽい女の子のスケベな画像もあるけど、家兄は本来そういう系は苦手……ずっと疑問だったけど、そういうことなんだね! ありがとう家兄! また見聞が広がったよ!」
「おう、いいってことよ! だけど芽衣、俺にはどうしておまえがあのフォルダの中身を知っているのかが気になるな!」
兄妹の仲睦まじさを表したような会話の中、秋はいまだ軽蔑した目で俺を見ていた。
会話に交ざりたいらしい。俺は親切な人間ので、入れてやらんこともない。
「というわけで芽衣、早速秋の性癖も調べてみようか」
「おい! なにが『というわけ』だ!」
「郷に入っては郷に従え、ですよ秋さん」
「ここ俺の家なんだけどっ?」
わめく秋を無視し、俺と芽衣はシュタッと立ち上がる。芽衣はくんかくんかと鼻を鳴らすと、可愛く純真な笑顔で、閉まった扉を指差した。
「家兄! あの部屋から色欲の匂いがするよ!」
「どんな匂いだ!」
「たしかあそこは寝室だったな! よし、突入だ!」
そうして俺と芽衣は寝室の扉に向け、駆け出す。その中で思い出したのだが、そういえばあの部屋には入ったことがなかった。多少悪ノリ感が出てきたが、もう俺たちは止まらない。止められるもんなら、止めてみろ。
「――その部屋は、ダメだよ」
「へ?」「え?」
ドアノブに手が届きかけた、その瞬間。
かくんと膝が折れる感覚を最後に、視界と意識がブラックアウトしていき――。
「――ん? あれ?」
目を覚ますと、俺はソファに身体を預けていた。横を見ると、芽衣が俺の肩に頭を乗せ、すやすやと眠っていた。
「お、起きたな、家之助」
「秋……あれ?」
「ホント仲良しだなーおまえら。漫画読んでたら、いつの間にか二人してぐっすり眠ってるんだもん」
「ああ……寝てたのか。すまんな……っておお、もう五時半か。けっこう寝てたな……」
あれ……? でもなんか寝る前の記憶が曖昧だな……。
「……ふがっ! あ、あれ? 私……」
「お、芽衣ちゃんも起きたな」
秋は芽衣にも俺と同様の説明をした。それを聞いた芽衣は一瞬、そうだっけ……みたいな顔をしていたが、すぐさま能天気な表情に変わり「あららー、私ったら朗らかだこと」とか言っていた。
「晩ご飯食ってくだろ?」
「えっ! マジっ? 俺らの分も作ってくれんのっ?」
「わーっ、秋さんの料理はじめてーっ! 私お母さんに連絡してくるね!」
秋のお誘いに松尾兄妹は大興奮である。
その後俺たちは秋特製のビーフシチューに舌鼓を打ち、大満足で帰宅した。
なにか忘れているような気もするが、まあ、気のせいだろう。
春休みの終盤、それはつまり入学式やらオリエンテーションが近づく時期ということで、生徒会業務はいよいよ活発になる。
他の生徒と比べれば、一足早く春休みが終わるようなものだ。
さて、小忙しくなりそうな本日も朝を迎えたわけだが、ひとつ問題が生じていた。
「秋、遅いねえ」
月本の呟きの通り、秋が生徒会に遅れているのだ。
厳密に言えば集合時間まであと五分はあるが、秋は常に十五分前には生徒会長の椅子に腰をかけているため、現状が稀有なものと言える。
「風邪でもひいたんですかね? 秋さん一人暮らしだから、面倒見る人もいないし」
芽衣のこの発言に、月本が焦った表情で立ち上がる。
「た、大変……助けに行ったほうがいいのかな……?」
「い、いや月本、まだそうと決まったわけじゃ……」
秋め、月本にこんなに心配してもらえるとは……なんてうらやましいんだ……っ!
「くそうあいつめっ、風邪ひいてしまえばいい! あ、ひいたらダメなのか。ひかないで!」
「なに言ってんだおまえは」
二次災害的に動揺する俺に、芽衣は呆れかえっていた。
そのときだ。生徒会室の扉が、ゆっくり開いていく。
「あ、秋……なにしてんだ?」
遅刻寸前で現れた秋は、扉から顔だけ出してきょろきょろと生徒会室内を窺っていた。みまがうことなく怪しい様子に、俺たち三人は目が点である。
一通り室内を見回すと、秋は俺に小声で尋ねる。
「お、近江先生は……?」
「おーみきょーゆ? 今日は見てないけど……」
答えると、秋は安堵のため息をつく。
そうして生徒会室に入り込む、その手に抱えているのは……。
「えっ! あ、秋、その子どうしたのっ?」
段ボールに入った、茶白の子猫だ。
「わ、わーーー可愛いーーー、なんなんですか秋さん、この子!」
「ふわーーー、目がおっきいーーーっ! こっち見てるーーーっ!」
「ちっちぇえなあ、かわええなあ!」
秋の連れて来た珍客に、爆発的に沸き立つ生徒会であった。
秋によれば、学校のすぐそばの公園に捨てられていたそうな。そこで見て見ぬフリのできない系男子秋は、ここまで連れて来てしまったのだ。
「でもこいつ、本当に捨て猫なのか……ああ、段ボールに『可愛がってあげてください』とか書いてあんな」
「腹立ちますね、こういうの。責任もてってんだ」
動物大好きな我が妹は、めずらしく苛立ちを見せていた。まあ、同感だがな。
「今はそれより、この子をどうするかだよ。そんなわけで、だれかこの子飼えないか?」
「おまえはダメなの? 一人暮らしだろ?」
「うーん……うちのマンション、ペット飼えるかわからないし……なにより金がな。正直キツいな……」
秋の両親はロンドンに住んでいるため、秋は現在一人暮らし中だ。
生活費は親から支給されているのだが、あまり余分にはもらっていないらしい。日本に居させてもらっている身なので、無理は言えないのだろう。
「そうだな……うちも、飼えないってことはないだろうけど……」
「こんこるどがいる手前、ねえ……」
こんこるどとは、うちで飼っている犬の名前だ。犬と猫が共存できないことはないだろうけど……少し不安だ。それにうちも、経済的に微妙なところがある。
「そうなると紗姫の家だけど……」
「うちも、ごめん……ダメだと思う」
月本はつんつんと子猫を突きながら、申しわけなさそうに呟いた。
すると猫はその指を、てしっと両前足で掴む。さらにはむはむと甘噛みしはじめた。その様子に、月本と芽衣は大興奮である。
「あーーーかわいーーー飼ってあげたいーーーっ!」
「持って帰りたいーーー共に生きたいーーーっ!」
しかしそうは言ってもどうにもならない。みな家庭の事情があるのだ。
そこで秋がひとつ、提案する。
「じゃあ、学校で飼ってくれる人を探すか」
「そうだな。元の場所に返すわけにもいかないし、それが一番だ」
「でも、春休みで人も少ないのに、大丈夫かな……?」
おそらく今この学校にいるのは、野球部やバスケ部、剣道部の他、文化部がいくつかくらいだろう。たしかに、心もとない。
「それでも、きっとだれか飼ってくれるはずだ」
「よっしゃこうなったら、しらみつぶしに乗り込んだらあ!」
「柄悪いな……。でも、そういうことなら私もがんばります」
方針も決まったところで、秋は俺と芽衣にどの部へ行くかを相談する。おおよそ、各々知り合いのいる部を訪ねることに決まった。
そして月本には、俺と芽衣とは別の指令を送る。
「紗姫は、ここにいてくれ」
「へ? 私は行かなくていいの?」
「ああ。紗姫の仕事は二つ。この子の面倒を見る……そして、近江先生が来たらごまかすんだ。この子のことや、俺らがいないことについて」
なるほど、これは絶対的に必要な役割だ。
近江教諭は生徒会顧問であるため、ちょくちょく俺たちの様子を見に来る。その際だれもいなかったら不審に思うだろう。
あまつさえ、そこに子猫なんていようもんなら……。
「……近江先生、平気な顔で返してこいって言いそうだね……」
「まあそこまでは言わなくとも、怒られることは避けられないでしょう……」
「シッ!」
不意に、秋が口に人差し指を当て、全員の声を制する。みな首を傾げていたが、静寂の訪れとともに、その意図を理解した。
ホラー映画のように近づいてくるその音は……近江教諭のヒールの音だ。
「や、やばっ! 来るぞ! やつが来るぞ!」
「隠せ! その子隠せ!」
仰せの通り、俺は子猫を段ボールごと机の下に突っ込んだ。
が、まさにその瞬間、扉は開かれてしまった。
「…………なにをしているのですか?」
近江教諭が冷淡にそう言うのも無理はない。
現在生徒会室では、机の下に頭から突っ込む男子生徒ひとりを、三人の生徒が囲むという意味不明な光景が広がっているのだ。
そんな状況を、慌てて秋がごまかす。
「これはっ、家之助が急に、窓の外から宇宙人がこっち見てるとか言いだして……」
「えっ!」
驚いて声を上げるも、直後芽衣に尻を蹴られた。ひどい。
「そ、そうなんです! うちの兄、たまにこうなるんです! すみません!」
「お、落ち着いて松尾くんー、大丈夫だよー、なにもいないよー」
「う、う、うわああああっ宇宙人怖ええええっ! アブダクションされるううううっ!」
暴れる俺とそれを押さえつける三人。それを近江教諭は、無表情で眺める。
「……お大事に」
そう言い残し、近江教諭は去っていった。
「ふうー……危なかったなー……」
「さすが秋さん、ナイスフォローです」
「ナイスフォローかな? もっと他にごまかし方なかったかな?」
その後、俺の意見はどこ吹く風と、部活動巡りははじまった。
俺と秋と芽衣で意気揚々と生徒会室を出て行ってから小一時間後、生徒会役員の意気は余すことなく消沈していた。
「くそー……まさか全員ダメだなんてー……」
一二三高校生徒会一丸となって子猫の貰い手を求めたが、結果は出なかった。
俺は野球部やバスケ部、新聞部などを回ったが、ことごとく断られてしまった。秋や芽衣も同様らしい。正直、一人も現れないとは思わなかった。
「どうするよーこの子……」
当事者はというと、デスクでごろごろと寝転がりながら、笑顔の月本が突き出す指に猫パンチをし続けていた。可愛いなあ。どっちも。
「……しゃーない。やっぱ俺が飼うよ」
「いやいや秋よ。自分でキツいって言ってたじゃねえか」
「でも……元はといえば俺が拾って来たわけだし……」
「関係ないですよ。もし同じ状況にあったら、私も連れて来てますし」
「じゃあ、春休み明けるまででも俺が……」
瞬間、ガチャッというドアの開閉音に、全員の血の気が引いた。
「……………………」
現れたのはやはり、近江教諭だ。温度のない視線を、無言で俺たちにぶつける。
危険を察知した俺は、瞬発的に猫の入った段ボールを身体で覆い、叫ぶ。
「うおおおおおっ! ギャラクシーが! ギャラクシーが俺を待っているんだあああっ!」
「はっ! い、家之助えええっ! すみません先生! まだ家之助治ってないみたいで!」
「家兄行かないで! 宇宙は寒いよ! 宇宙は寒いよ!」
再び盛り上がる俺たちだったが、近江教諭は平然と尋ねた。
「猫ですか」
「ぎゃわあああああダークマターになるうううっ! ダークマターに……」
「猫ですね?」
「はい」
謹んで正座をする四人の生徒会役員を前に、近江教諭は淡々と話す。
「どうにも怪しかったので足音と気配を消して入ってみれば……こんなこととは」
この人何者なのだろう。
「……一ノ瀬くん、生徒会長が校内に猫なんて持ち込んで、良いと思っているのですか?」
「はい……すみません……」
「でも先生っ、秋は……」
「今は一ノ瀬くんと話しています。少々お待ちください、月本さん」
「でもそのまま放っておくなんて……」
「黙りなさい、皮剥ぎますよ松尾」
俺だけ辛辣ぅー。
「みなさん、生徒会役員としての責任を持ってください。あなたたちは全生徒の代表なのですよ? わかっていますか?」
全員そろっておずおずと首肯する。すると近江教諭は、さらりと告げた。
「なので今後このようなことがあったら、私に一声かけるように」
「はい……え?」
「ちなみに、この子の貰い手は見つかったのですか?」
近江教諭は、空気を読まず幸せそうに眠っている子猫を指差した。
「い、いえ……難航していまして……」
「では、今回は私が引き取りましょう」
「「「「えっ!」」」」
一斉に驚く俺たちをよそに、近江教諭は子猫を柔らかく抱きかかえる。目が覚めた子猫はじっと無表情で見つめてくる近江教諭に、人懐っこそうな鳴き声を聞かせた。
「い、いいんですかっ?」
「はい」
「近江先生のマンション、ペット飼えるんですかっ?」
「飼えますよ」
「まさかこの子を、なにかの実験にとか……」
「松尾は私をなんだと思っているのですか?」
月本、秋、俺の順で繰り出される矢継ぎ早な質問にも、近江教諭は整然と答えた。
無事猫の貰い手が現れたことを理解し、俺たちは両手を上げて喜んだ。
そんな俺たちを見てか、子猫の可愛さにやられてか、ちらりと見えた近江教諭の表情は少しだけ柔らかくなったように、俺には見えた。
こうして、生徒会史に残る子猫を巡る騒動は、意外な形で幕を閉じたのだった。
ただ――俺の中でふと、小さな疑問が芽生える。
しかしそれは、その日の業務に勤しんでいるうちに、忘れてしまっていた。
どうして秋は、近江教諭がマンションに住んでいることを、知っていたのだろうか――?
秋の拾って来た猫がなんにゃかんにゃあって近江教諭に飼ってもらえることに決まった、そのすぐあとのことだ。
近江教諭が、こんな申し出をしてきた。
「みなさんでこの子の名前を考えてくれませんか?」
「え? 近江教諭が付けなくていいんですか?」
俺のこの問いに、近江教諭はかすかに首を横に振る。
「一ノ瀬くんが拾ってきて、みなさんで貰い手を探したのですから、そうすべきかと。私も意見くらいなら出しますが」
近江教諭がそこまで言った上で拒否をする者は、もちろんいなかった。
そんなわけで、一二三高校生徒会は仕事そっちのけで、猫の名前を検討する緊急会議を開始した。ちなみに名付けられる当の本猫は、近江教諭による頭部のマッサージを受け、ふにゃっとした顔をしていた。
「そういえば、その子って男の子? 女の子?」
俺の問いに、近江教諭はひょいっと子猫を持ち上げ、無防備な腹を覗き込む。心なしか、恥ずかしそうな表情をしている。
数秒の確認作業の末、近江教諭は断定する。
「女の子ですね」
「おなごかー、おまえおなごなのかー」
芽衣はそう言って子猫の白い腹をつついていた。
「そもそも、ペットの名前ってどういうノリで付けるものなの?」
ペットを飼ったことがないという月本が、まずこんな疑問を呈した。
それに、俺は少し考えてから返答する。
「子供に付けるのと同じ感覚じゃないか? よくわからないけど」
「そうかね? ペットに『さちこ』とか『よしえ』とか付けるかね?」
「それは名前のチョイスが古いだろ……可愛い系なら、人の名前でも全然良いと思うけど」
名付けに際してバリエーションが増えるよう、俺は穏便な発言を心がけていた。が、秋はなにか難しい表情で持論を展開する。
「でもなあ……人の名前にも使われてるのを選んじゃうとさ、いろいろ厄介じゃない?」
「厄介ってなんだよ」
「たとえば、身近にいるすげえ嫌な人間と同じ名前だったりしたらさ、かなり複雑だろ」
この意見に、月本と芽衣は「あー……」と納得し、近江教諭もなるほどと頷く。
「それは考えすぎじゃないか……?」
「いや家兄、それは由々しき事態だよ。癒しのはずが、ストレスの原因となる人間と同じ名前なんて……考えるだけでおぞましい」
月本はうんうん、と首肯する。それらを聞いて、近江教諭がまとめた。
「では多数決の結果、まず方針のひとつとして『人の名前に使われそうな名前』はなしで考えましょう」
多数決なら仕方がない。別にそこまで否定することでもないしな。
件の子猫が俺たちのデスクをすんすんと歩き回り、大冒険に興じているさなか、議論は続いていく。
「じゃあ食べ物の名前なんてどうだ? 人とかぶるのは少ないし、なんとなく可愛いだろ」
この意見に、月本と芽衣は好意的に食いつく。
「あー、いいかも。スイーツの名前とかね」
「食べちゃいたいくらい可愛いですしね」
うまくまとまりかけたが、再び秋が否定的に語る。
「いやでもなあ……食べ物の名前にしたら、この子が死んだあと、その食べ物を見るたびに思い出して落ち込んじゃうだろ。絶対食べられなくなる」
「いや……まだ子猫なのに、死んだあとのことを考えるなよ……」
「いや必要だ。生き物と共に生きるということは、常に死と隣り合わせであることを理解しなければならない。いずれ来る別れを、受け入れなければいけないんだ。その食べ物を見るたびに過去に立ち返ることは、この子も望んでいないはずだ」
転がっている消しゴムをてしてし叩いて遊んでいる子猫を指差し、秋は熱っぽく語る。考えすぎな熱弁に、俺は軽く引いていた。
だが、月本と芽衣の心には突き刺さったらしい。二人は目を潤ませながら秋に同調する。
「そうだね……うぅ……食べ物の名前は、ダメだね……」
「忘れてはいけないんですね……生命の儚さを……それが情操教育なんですね……」
いや、近江教諭にもう教育は必要ないだろ……。
「ではまたひとつの方針として、『食べ物の名前』はなしですね」
近江教諭はそう、静かにまとめた。教諭が良いならいいけど……。
しかしその理論じゃ、花とかよく目にするものの名前もダメだろうな。となると……。
「じゃあ宝石の名前とか! ルビーとかサファイアとか綺麗な名前多いし。日常的に目にするものでもないだろ?」
「おまえそんな名前にしたら死んだあとポケモンできねえだろうがっ!」
「考えすぎだろ! 近江教諭、ポケモンやらねえし! そもそもシリーズ名に宝石の名前つける流れはもう終わっただろ!」
「金・銀のあと宝石シリーズになって『もう色シリーズは終わったかな』とだれもが思ったところでブラック・ホワイトが起用されたことで再び宝石シリーズに舞い戻る可能性が浮上したことを忘れてんじゃねえよっ!」
「なにで怒られてんだ俺は!」
秋の神経質な思考のせいで、よりヒートアップしていく議論。そこへふと、月本が素朴な疑問を口にする。
「そういえば松尾くんちのワンちゃん、『こんこるど』って名前だったよね? なんでその名前にしたの?」
「ああ。うちのはダックスフントなんだけど、横顔が離着陸時のコンコルドに似てるんだ」
「ね? 意味わからないですよね? うちの父と兄が勝手につけちゃったんですよ」
良いじゃないか、別に。カッコいいじゃないか。
「なるほど……身体的特徴……茶白の猫……」
秋のその呟きに、そこにいた全員がじいいっと子猫を見つめる。あらゆる角度から突き刺さる視線に気づいたのか、子猫はぴたっと動きを止め、瞳を落ち着きなく揺らす。
「じゃあ、こんなのはどうだ?」
妙案が浮かんだ秋が手を叩くと、子猫はぴょんっと飛び上がった。
「それぞれ白色と茶色でイメージするものを紙に書く。その後ランダムに一枚選んだ白色のものと茶色のものの名前をうまいこと合わせて、この子の名前を作る」
なるほど。それなら公平だし、造語であれば日常生活にあるなんらかと被ることはない。
他のメンツも納得のようなので、早速施行された。
五人の思い描く白色のものと茶色のものが書かれた紙が集まったところで、それぞれ選択していく。選択方法は当事者である子猫に依頼した。子猫が最初に踏んだ紙を、当たりとしたのだ。
「さーて、そんなこんなで出そろいましたねー、白いものと茶色のもの。果たしてだれのが選ばれたのか……じゃあまず白いものから」
バラエティ番組の司会者のように、秋はノリノリで紙をめくる。
「はい、『砂糖』です。これどーなた?」
そこで返事をしたのは近江教諭だった。実にらしい選択だが、飼い主である教諭の案が入ったのはなんとも運命的である。
そして秋は、すぐさま茶色の方の紙を手に取る。
「さあ、じゃあ茶色のほうは…………は?」
秋は呆れた顔でその紙をテーブルに放る。そこに書かれていた茶色のものとは……『Amazonの箱』。
見た瞬間全員がフリーズしていたが、俺は真っ先に声を上げる。
「Amazonの箱って……たしかに茶色だけど、センスなさすぎだろ! だいたいAmazonに限らず段ボールは茶色だし! もっと他に浮かばなかったのかよ!」
俺がひとしきりツッコミを入れたところで、秋は改めて尋ねる。
「……じゃあ、これどーなた?」
「はい、俺です」
「おまえかよ!」
ごめんなさい、本当に浮かばなかったんです、ごめんなさい。まさか選ばれるとは……。
「セルフツッコミとは……家兄も腕を上げたね」
なぜか芽衣は誉め称えるような表情でサムズアップするのだった。
ふと、近江教諭を見ると、なにか顎に手を当てて思案していた。
「……Amazonと砂糖で……『あまとう』なんて良いと思いませんか?」
「ええっ? そ、それでいいんですか、近江先生……? 名前に大手通販サイトが入ってますけど……」
「はい。良い名前だと思います」
近江教諭にしてはめずらしい、血の通ったような声色だった。
それにつられてか、月本や芽衣も同調しはじめる。
「……うん。でも、いいよね、あまとう。かわいいかも」
「私も、やわらかい印象で似合っている思います。あまとうちゃん」
そうして、やんわりと決定した。俺と近江教諭の意見が混じり合った結論。
命名。近江教諭の飼い猫、その名前は『あまとう』。
「いやーかわいいなーあまとう。名付け親の一人として、俺も鼻が高いぜ」
「おまえが言うのは、なんかムカつくな」
そう言う秋と生徒会メンバーたちの笑い声が響く。
そんな中であまとうは、近江教諭に背中を撫でられて気持ちがいいのか、名前の通りの甘い鳴き声を上げていた。
今日も私は、あなたを見つめている。
どこにいても、なにをしていても、あなたのことを考えている。
それでもあなたは、私だけを見ていてくれない。
それは、少し図々しいかもしれないけど、やっぱり悔しい。
でも、私は信じている。
いつかあなたが、この気持ちに気づいてくれることを――。
その日は朝からツイていなかった。
入学式にもかかわらず寝坊してしまった。急いだせいでしっかりセットした髪もぐちゃぐちゃ、慣れない靴で靴擦れまでしてしまう始末。
記念すべき高校生活一日目なのに、なんでこんな目に……。
入学式を終えて教室へ戻る中、私はひとり渡り廊下を歩きながら、そう心の中で愚痴っていた。
そのときだった。
「ねえ、きみ」
「え?」
唐突にかけられた声。振り向くと、中性的な顔立ちでそんなに大きくない男の子が、私に笑顔を向けていた。
見ればそのネクタイは私のリボンと同じ色、つまり同じ新入生だ。それも、さっきの入学式でしゃべってて、先生に怒られていた男の子だ。
「な、なんですか?」
見知らぬ男子に突然声をかけられれば、狼狽するのは当然だろう。私は少々怪訝な顔をしていたと思う。
でもあなたは、ずっと同じやさしい笑顔を見せてくれた。
「靴擦れしてるでしょ?」
「……え?」
「歩き方でわかるよ。新しいローファーでやっちゃったんでしょ?」
完全に図星をつかれ、私は声も出なかった。
「はいこれ、絆創膏。これ貼っておけば多少ごまかせるよ」
あなたはポケットから絆創膏を二枚取り出して、私に差し出した。
「あ……ば、絆創膏……いつも持ってるの?」
「あー、うん。俺もよくちっちゃい怪我するからねー」
そう言ってあなたは「んじゃ」と言って、私を追い越す。
そうしてちょっと先を歩いていた、入学式で怒られてたもうひとりの、特に特徴のない男の子に声をかけに行く。
あなたはありがとうも、言わせてくれなかった。
その中で、あなたのポケットからなにかの紙が落ちたのに、私は気づいた。
それを拾って、中を確認して、そして……。
「あ……」
あなたのウソを理解して、私は息を呑んだ。
それは、購買部のレシート。日付は今日で、時間はほんのちょっと前。
その購入内容はただひとつ、絆創膏。
「これ……私のために……?」
その瞬間に芽生えたのは、はじめての感覚。
それはごまかしようのない、恋のはじまりだった。
あなたのおかげで、最悪だったその日は、最高の日になった。
その後、あなたが同じクラスであることを知り、鳥肌がたったことを覚えている。
私は緊張で心を高鳴らせながら、意を決してあなたの席に近づいた。
そうしてこの恋は、「ありがとう」の一言から、はじまった。
あなたが私を、『紗姫』と呼ぶようになったのは、それから少しだけ後のことだ。
あの日、私はずっと憧れていた感情を手に入れた。
言葉は知っていても、その意味は知らなかった、『恋』というもの。
それを知ってから、私の世界はまるっきり変わった。
私にとって恋とは、あなたそのものを表すものなのだ。
だから私はこの恋を、大切に育てていこうと誓った。
今日も私は、あなたを見つめている。
あなたはまだ私だけを見ていてくれないけれど。
私がこんなにアピールしているんだから、いつかはあなたのほうから私に告白してくれるって、信じてるから。
もし他の子に転んだりしたら、絶対に許さないから。


