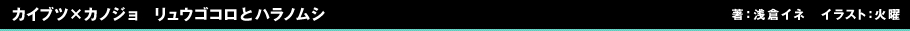コンテンツページ
――竜とは、何か?
それは“彼女“にとって答えは決まっていた。
異世界でも恐れられる竜。とても気高く。高貴で。真祖の血をもつ存在。誰にも従わず。飼い慣らされず。それどころか、人間すら“しもべ“にする気概と力に満ちた最高の存在が『竜』であった。
竜とは、すべてのものの頂点に立つ存在である。
で、その日。竜は人間界の食卓についていた。
異世界からやってきた竜。名を『アルキリア』という。事情あって本来の『真祖の竜』からかけ離れた『人間の女の子』の姿をしているが、それは世を忍ぶ仮の姿――。本来ならばとっても恐ろしい竜なのだ。
(――あむっ)
麗しの金髪、気の強そうな赤い瞳。人間になった彼女は、今は北上(きたがみ)実典(みのり)という保護者と一緒に、ダイニングのテーブルに腰掛けて『三時のおやつ』を食べていた。
『えー? 男に好かれる秘訣ゥ? ええ、ウチ分かんなぁい。ミカコは知ってるゥ?』
『んー。ウチはオシャレかなー』
二人は、テレビの街頭インタビューを見ていた。
画面に映るのは、いかにもな“渋谷系ギャル“ファッションに身を包んだ二人の女の子。化粧っ気の濃い顔をカメラに向け、インタビューに答えている。
『ミカコぉ。それ違うって! ウチら、たぶんアドバイス的な何かを求められてンだってェ。ウチらと違ってダサい系な女子がー? もっと頑張ればできるようなー、感じぃ?』
『んー。難しいな。だったらウチはやっぱりダイエットかな?』
『アハハ。言えてるゥ。がつがつ食べる女は男から嫌われるよねェ!』
――ピタッと。
ここで、皿に手を伸ばしていた竜の手が止まった。
不意に落ちてきたキーワードが、なぜか竜の心に刺さった。それからふと、竜は自分の『三時のおやつ』――皿の上にのっているドーナツを数えてみる。
……八個ある。
自分の分だけ、八個。一緒に食べていた実典のところには、わずか三つあるだけである。実典はそれすらも食べきれず、一個分を夕食後に回そうかと話していた。
「…………」
『トモヤも、アキヒロも――あ、ウチの元カレなんだけどぉ。そういう大食い女ってあんまり好きくない?のよねー。カレシに大食いに見られる……って、女としてありえなくない? 女の子は、食べる量くらい女の子してないとねー?』
『基本だよ。むしろ、大事。大食いでがさつに見られてる女って、絶対に男に大切にされない感じがする』
……! と。
竜は絶句。わなわなと、泣きそうな顔になる。
……ありえない。相手から、ありえないと見られている……。
女の子がどうとか、男にどう思われているのか――。そんなのは『竜』である彼女にはよく分からなかった。ただ、このドーナツは、もともと『ある少年』が彼女に買ってきたものである。
彼女の『胃袋』の適量をすでに知っていて、計算し、彼女が後で文句を言わないように買ってきている。それってつまり――『人の子』というものに、『大食い』で『がさつ』だと思われている、ということなのではないのか……?
「……あ、う」
半開きになった竜の口から、情けない声がもれる。
子供みたいな泣きそうな顔になった。
自分はすべてのものの頂点に立つ竜である。高貴で、気高いはずの存在である。
それなのに、今の自分の姿はどうなのか? ひどく食い意地が張った、落ちぶれた竜のように思われているのではないか。エサをただ欲しがる、人間に飼い慣らされた家畜のように……。
(……わ、私はこれでいいのか……? 竜の人生、これでいいのか……)
画面の中。渋谷ガールは、いかにもお似合いな金髪の『ヤンキー』な彼氏を相手に。腕を絡ませて、カメラにVサインを送りつけていた。
町の中華屋では、異様な熱気に包まれていた。
ハフハフ。炒めたばかりのチャーハンを口に運ぶ。レンゲを動かすたびに食油特有の香ばしさが店に広がり、厨房の換気扇でも店内の異様な雰囲気は逃げなかった。
「な、なぁ。景(けい)。ヤバいぜ」
「……うん」
高校生、北上景は、ちょうど同じ時間帯にクラスメイトの加土街(かどまち)とそんな話をしていた。顔には深刻さがある。
二人の目の前には、大男がいる。ゆうに二人分の席のスペースを陣取り、レンゲでかき込む様はまさに王者の貫禄だ。
里中(さとなか)というのが、その大食漢の名前だった。
「――ぶあーっはっっはっははあ! どーした!? 挑戦者たち。ボクチンの大食いに恐れをなしたかっ!」
米粒を飛び散らせて、戦国武将のように獰猛に笑う。
ぐっ。加土街が悔しそうに黙る。
現在、景たちは、このクラスメイトの里中を相手に戦いの最中であった。
どうしてそうなったのか。それは話が学校の放課後までさかのぼる。景たちが予約していた新作のゲーム『ドラモンクエストⅢ』という、世間で爆発的ブームを巻き起こしたソフトがあるのだが、同日に『ファイナルケントⅡ』という、これまた大人気のソフトが発売されたのだ。
どちらも、学生にとっては宝物。
だが、金銭的にはどちらも購入することは困難でもある。
里中は、それを侮辱する形で争いをふっかけてきた。「――ボクチンの『ファイナルケントⅡ』のほうが面白いね」と加土街を怒らせてから、「フードファイトといこうじゃないか。キミたちが勝てば、ボクチンのゲームを貸してやる」と条件を突きつけてきたのだ。
裏を返せば、負けたら買ったばかりの新作ゲームを相手に貸すことになる。それが彼の魂胆だった。
「ははっ。どーした? 加土街クンよ。さんざん大口を叩いた挙げ句、二人がかりでギブアップかぁ? 僕はかまわんぞ。一向にかまわん! そのかわり、新作のゲームはボクが先にもらってゆく!」
「……ぐ。ば、化物かよ」
加土街は、相手の脂ぎった笑顔を睨みつける。
景も同じ気持ちだった。――最初は『二対一だし、余裕で勝てる』と思っていた勝負だったが、この男は間違いなく景たちにとって『魔王』であった。
なにせ、食いっぷりが凄まじい。悪夢のような食欲でテーブルに降臨し、次から次に、出されてくる中華を完食してゆく。食卓を蹂躙してゆく様は、魔王の軍隊だ。
大食い勝負は、圧倒的に景たちの『劣勢』であった。
「――ぶあっはっは! これでもボクチンは、この中華街で無双の『フードマスター』として知られているからねー。学校の表の顔でしか判断しなかった君たちが悪い! ゲームは頂くよ。あっはっは!」
「さ、里中君。せめて、もう少しハンデを……」
「ダメだァ! 北上ぃ! だいたい、二人がかりの時点で大譲歩。大ハンデじゃないか!」
……ぐ。それは、その通りである。
景は反論できなかった。最初はそのつもりで勝負したのだ。『二対一なら楽勝』だと思っていたのに、不利になったとたん『ハンデ』なんて言い出したら、それこそ里中の言うようにズルい言動である。
……だが、それでも負けたくない。
景は思った。こんなやり口で他人のゲームを借りるなんて、ひどすぎるではないか。過去、里中は何度もこんな手口でクラスメイトの私物を強引に借りていた。景はそういう魂胆が許せなかったし、絶対に負けたくないとも思った。
――が、そのためには目の前の大食い男を倒さなくてはならない。相手は、まさしく人間界における規格外の怪物(モンスター)であった。
「……ん? 怪物?」
と。ここで、ふと景の箸が止まった。
「どうした? 景」
「いや。ちょっと閃いた」
…………いるじゃないか。一人。この窮地を脱させてくれそうな人物が。
いつもは洋館で食費を浪費して、食べて、食べて、食べまくって家計を火の車にしてくれている犯人。『竜』が――。
「ね、ねえ……里中君?」
「む。なんだ。弱小ベビーフードボーイ、北上よ」
「…………調子に乗って変なあだ名つけないでほしいんだけど。それより、もう一人だけ応援を呼んじゃダメかな?」
「ダメに決まってるだろ! ダメだダメだァ! お前ら、ボクチンに勝てないからって見苦しく悪あがきはやめろ! みっともないぞ!」
「それが、さ」
予想していたとおりのリアクション。だからこそ、北上景はぐるぐる脳のメモリを稼働して、なんとか必死に断られない言葉を探していた。
「……相手は、そこそこ美人な、女の子なんだけど」
「むおっ? なに、女子か!? なぜそれを先に言わん!」
その一言に傾いたことで、フードマスター・里中の運命は決した。
…………かに、思われたが。
「……むう」
竜の少女は、座っている。
呼び出された少女は、本来の彼女であれば大好きな『脂ぎった肉料理』が並べられた中華屋で、難しい顔をして座っていた。
色とりどりに並べられた料理。食材の旨みが滲んだ中華の香り。――が、彼女はそれを『不味いもの』でも見るように黙っている。
「ど、どうしたの? キリア。ほら、ほら。美味しいご飯がいっぱいあるよ? これぜんぶ食べていいんだよ? 夢のようじゃないか! この世の楽園。これが君の望む天国なんじゃないの?」
景は、応援のつもりで放った言葉だが。ピクッと少女は反応した。
「…………やっぱり、そう見られているのか……。私は……」
「え?」
「――いらない」
衝撃の一言が、キリアの口から飛び出した。
景は。大げさな表現でいえば、地球がひっくり返ったほどの衝撃を受けた。
あの、キリアが!
食い意地が張っていて。食べ盛りの高校生よりも食べ盛りをしていて。料理に文句つけたり、自分の皿と人の皿の量を見比べたり――。あげく夜食までして、『食』に関する問題行動ばかり起こす『竜』が――。
料理を、いらないといった。
「ちょ、ちょっとちょっと! 待ってよ! 本当に待ってよ! なんでだよ! 普段、あれだけ食材バキュームしてたじゃないか! なのに、なんだよ『いらない』って!」
「……私は、『モテるじょし』だからな」
ぷいっ。そっぽをむく。
おそらく意味も分かっていないだろう竜が、覚えたての言葉で景に反論した。そのくせ、腹はテーブルの中華料理の匂いによって『――ぐるるる』と密かに鳴っている。
これには、意味が分からない。
「……お、おい。景。やべえぞ! もうそろそろ後半戦の時間が切れそうだ! このままじゃ負けちまう!」
箸を猛烈に動かしながら、加土街が叫ぶ。
「ぐ。キリア! 食べてくれって!」
「お、お腹いっぱいだ。私は、大食いでがさつな女ではない! さっきドーナツを食べてきた! それで十分満足できる女なのだ!」
「…………ぐ。じゃあいいよ! もう僕たちでなんとかするから!」
どちらにせよ、振り出しである。景は加土街と並んでテーブルに落ち着き、それから苛立ちも込めて、油で光沢をもった『牛肉の細切り炒め』『酢豚』など、ボリュームのある中華料理をかき込んでゆく。
だが、それでも遅々として箸は進まない。フードマスター・里中は勝利を確信して爪楊枝を使い、「――北上君の知り合いにこんな美人がいるなんてなぁ。どう? この後、ボクチンと遊びに行かない?」とキリアに声をかけていた。
竜の少女は、ただ黙ってうつむいている。
はた目から見たら大人しそうな美人の女の子。でも、その腹にある欲求のカタマリは『……せっかく、美味そうな中華料理が目の前にあるのに……』と悲しそうにしていた。
と。そんな時。
『はーい。みなさーん。こちらは「午後☆ドキッ」の芸能リポート部です! 今日は、こちら。当テレビ局の食堂内で、超有名芸能人の皆さんにインタビューをしていきたいと思いまーす!』
午後の、間延びした声が響いた。
料理も作り終えた店主が、暇なので天井のテレビをつけたらしい。
「……?」
『はーい。では、こちらが、偶然たまたま発見した大ブレイク中の仲間由美子(なかまゆみこ)さん! 出演前の食堂でカツカレーをかき込んでらっしゃいましたが、女優さんでそれは色々アウトなんじゃないでしょうかー? どうですー?』
『――あ、はは。女性でそれはちょっと恥ずかしいですけど。でも、たくさん食べる女性って、昔から素敵だと思っているんです。私』
そのインタビューにピクッと反応したのは、テレビをつけた店主ではなく、悲しそうにうつむいていた少女だった。
まるで神様のお告げでも耳にしたように、迷える子羊の顔で見上げる。
インタビューされる女優は、大人な笑みで、
『もともと人間に必要なエネルギーを『食事』から得られるわけですし。お腹がすくってことは、それだけ体が頑張ったんだと思うんです。だから、正直に食べて、噓つかない人が好きかな。昔から』
『なるほどー。体に無理をさせるの、確かによくないですよね。さすが、日本を代表する女優さんです!』
スタジオも、納得した雰囲気でうなずき合っている。
キリアは、ハッとした顔になって。隣の景の袖を引っ張って。
「――わ、私は。大食いでがさつな、嫌われる存在だろうか……?」
と、思い切った疑問をぶつけた。
景は、はふはふ、料理を口に運ぶ、半ば鬱陶しそうな目を向けて、
「……んなこと、前から知ってるよ。だけどキリアは『竜』なんだから。仕方がないじゃないか。むしろ、自分を偽ってないところを認めてるんだよ」
ごくりと、水で流しこんで、
「――そりゃ食費だってかさむし、家計に与えるダメージだって大きい。子供みたいに欲しいお菓子は買いまくる。けど、だからって、それだけで『嫌い』になれるわけないじゃないか」
「…………」
「キリアは、キリアのままでいいよ。そういう竜だって前から知ってる」
景は、深く考えず口にしていたが。
竜は、不覚にも感動してしまった。
自分が真に受けてしまった『てれび』とは、また違うことをいってくれている。しかも普段から迷惑そうにされている大食いを否定するのではなく、受け入れてもらったことが嬉しかった。
そして、余談ではあるが。感動するとお腹が減る。
――ぐぎゅるるるるるるるるるる。
「……。ん?」
里中と、加土街が同時に周囲を見た。
なんだ、今の地響きのような音は? そんな顔。景も店内を見回して、この不気味すぎる音の発生源を突き止めようとする。
で、分かった。
この音の発生源は――。
「う、うがああああっ。もう我慢の限界だ! 景、私は大食いでがさつな竜になるぞ!」
両手を挙げて。
今までの大人しそうだった雰囲気から一転。食卓で大暴れするような、本来の食べっぷりを発揮する少女が現われた。
「なっ。どうしちゃったんだよこの子!?」
里中が叫び、料理を作った店主も驚いた目でこちらのテーブルを見つめる。
何かが取り憑いたんじゃないか!? という顔だったが、景に言わせるとこっちがいつも通り。平常運転である。
それからどんぶりを抱えたキリアは。がつがつ。あっという間に平らげていく。中華丼。皿うどん。チャーハン。エビチリ…………。よくもまぁ、その細い体に入っていくなと呆れる食べっぷりで、食卓の中華が消滅していく。
「ん。む。これで――最後か」
と。最後のタマゴスープを平らげ、エビの一尾を口に放り込んだときには――「う。うそだろ……」とフードマスターが絶句する中で、食卓という名の戦場から、喧噪が消えてしまっていた。
聖戦は、終わった。
食べた皿を数えなくても分かる。この勝負は景たちのチームの勝ちであった。
この中華街で新たなフードマスターの誕生である。
「ありがとう。キリア」
景は、加土街と別れた帰り道で、トコトコ横を歩く少女を見た。
夕暮れの帰り道。満足そうにお腹をさする彼女は、幸せそうな顔をしていた。
「おかげで勝つことができたよ。加土街も喜んでたし」
「むふ。そうだろう。そうだろう。普段から私のことを大食いとか、出費ばかりさせる竜だ……とか言っていたが、これで少しは、この私のことを見直す気にもなっただろう」
「いや、まったく」
「……私のこと、嫌にならない……。よな?」
ふと、立ち止まって。
そこだけ不安そうに。上目遣いに問いかけてくる。暮れゆくオレンジの光の中で、景は少しドキッとしてしまった。
「……う、うん。ならないよ」
正直な気持ちを、はき出す。
なるわけない。そう思った。景は理由があるからキリアと一緒にいるのではない。むしろ、普通の女の子としてはマイナスな要素が多い。
でも、それはキリアだから。彼女という特別な存在だから、許せることであった。
竜の少女は、「そうか」と。満足そうに追いついてきて、それから隣を歩いた。口元が少し緩んでいる。
「ところで、景よ。私はお腹がすいた」
「……は?」
「なあ。そこの店先を見てみろ! 『けーき』とやらが並んでいるぞ! こっちには饅頭のようなものも! 『ふるーつ』が入っているらしい! こっちはお前が先日買ってきた『どーなつ』ではないか!?」
「あの、ちょっと。キリア?」
すさまじく嫌な予感を覚えた景は、青くなりながら冷や汗を流す。
「…………もしかして、まだ食べ足りないの……?」
「当然だ! 私は気高く、高貴なる真祖の黒竜であるぞ! 人間がひれ伏すくらいの大食いを見せて、食べて食べて、食べ倒してやるからな!」
振り返った竜は、楽しそうに笑っていた。