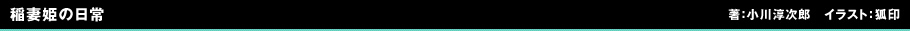コンテンツページ
ごぉっと荒々しい風が吹く丘。
雑草が生い茂り、様々な虫がぴょんぴょんはねている。
早朝、太陽が東の山から頭半分だけ覗かせたばかりの時間帯、一人の少女がそこにいた。
幼い顔立ちに青白い肌、真紅の瞳と唇がよく映えていて、かわいらしく美しかった。
肩で切りそろえた髪に金のカチューシャを着けて、白のワンピースに青いショールをまとっている。茶色いブーツを履いていた。
風体はどこかのお嬢様といったもの。だが、しかめっ面の表情からひどく不機嫌だと察せられた。
彼女は、自分の足元を見ている。そこには広々とした黒い布を敷いて、大の字になって寝ている男がいた。
大柄、巨漢、などという表現ではとても足りない大男であった。
少女が小柄だということを差し引いても、男は巨大だった。
背が高く、全身が分厚く、太い男だった。肥満体というわけではない。
全身のあらゆる箇所、足に腹に胸、肩と腕、そして首と、各部の筋肉が異様に発達した巨大な男であった。地面がわずかにめりこんでさえいた。
黒髪は耳にかからない程度に切りそろえられている。ごつごつとした顔立ちだが若い。肌にしわやひび割れはなく、シミもなかった。
それがすやすやと寝息を立てていて、鼻に蝶が止まっていても気づかないほど熟睡している。
「この……、この……、この……!」
少女は拳を握りしめてぶるぶる全身を震わせる。
すると――バヂッ、バヂヂッと、紫電がはじけた。
少女の全身、髪や背中などあらゆる箇所で紫電がはじけている。
少女が放っているのだ。
大男の鼻に止まっていた蝶は危機を察してひらひら逃げていった。
しかし、その男自身は未だにすやすやと眠っている。その動じなさも、山のようである。
少女は男に、文字通り雷を落とした。
「起きんか! デカブツ――――ッ!!」
「――あガガガガガガガガガ!」
少女は稲妻を放ち、男をしたたかに打ち据えた。
男は叫びながらビクビクビクと激しい痙攣をするも、黒焦げになったりはしなかった。
パチ、パチパチとまばたきをして、そして、
「……おやすみ」
ごろりと寝返りを打った。
「寝るなー!」
少女は反射的に蹴った。
ブーツのつま先で男の背中を蹴った。だが、悲鳴をあげたのは彼女のほうだった。
「いっ……! いっ、たーい!」
男の背筋はびくともしなかった。
岩肌のように硬く、重く、少女の足の指がぐちりと音をたててしまった。
「……っ、もう、起きろ! 起きろバカ! 仕事! 仕事でここにきてたんだよ! サボるなこのバカ!」
すーっと息を吸いこんで、再び紫電を全身からはじけさせた。
「起きろ神楽ー!!」
「あガガガガガガ!」
稲妻が再び男、亀楽神楽(かめらかぐら)を打ち据えた。
二度目の痙攣でようやく覚醒したか、彼はゆっくりと起き上がった。
地面を踏みしめ、大きく背筋を伸ばす。日光を完全に遮るほど高さがあり、横にも太い。立ち上がるだけで風が揺らめき、少女もたじろいでしまった。
「おい! 神楽! かがめ!」
「え?」
「いつも言ってるだろ! お前、でかすぎて私の首が痛くなるんだよ! 話しやすいように背中を曲げろ!」
「はいはい……」
勝手な物言いだったが神楽は文句も言わずに背中を曲げた。
少女は腰に手を当てて胸を張る。
「それでいいんだ! でかいんだから気を配れよ。ええと、何メートルだった、身長は」
「二メートル五〇センチ。体重は二二〇キロ。すごいだろ」
えっへんと胸を張る。
「だから背筋を伸ばすな。しかし、なんでそんなに眠いんだ。別に昨日、夜遅かったわけじゃないだろう」
「いやあ、確かにそうなんだけどなあ」
神楽はマット代わりにしていた布を拾い上げて身体にまとった。マントだった。手慣れていることから日頃から着用しているのだろうとわかる。
よく似合っていた。
「昨日、帰り際にドクがね、いいものをあげようって古い本を出してきて。いやー、それがおもしろくて」
「本って、お前はまだ“こっちの文字”を読めないだろ」
「迷い物、いや、迷い本だったんだなあ。日本からの」
「あー……。なんであいつがそんなの持ってるかは置いておいて、確かに、うん。読みたくなるか。“日本人のお前”にとったら」
「そうそう。しかもおもしろかったからなあ。内容もさることながら、その設定も。なにせ吸血鬼が題材なもんだから」
「吸血鬼が?」
少女はその単語に思わず食いついた。
「そ、吸血鬼。ただ、少々違っていたなあ」
神楽はあくびを繰り返しながら語った。
吸血鬼、ヴァンパイア、ドラキュラ。
姿形は人間とまったく一緒だが、獣のような牙が生えている。それで人間の喉や手首なんかに噛み付いて、血を吸い取る。
血を吸われた人間は同じ吸血鬼になる。それが彼らの繁殖方法。力は人より強く、霧や蝙蝠に変身することができる。しかも滅多なことでは死なない。
しかし、弱点は多い。
太陽の光に当たれば灰になる。
流水を越えることはできない。たとえば、海も。
あとは銀に弱く、木の杭で心臓を刺されたら死ぬ。
神楽が語ったのは大体、こんなところだった。
「――それは、ずいぶんと違うんだな。私たちと」
「そう。こっちの吸血鬼、アーニャ、お前たちと違うだろ」
神楽がふっと一歩だけ動いた。
すると、彼の身体で遮られていた日光が少女、アーニャを照らす。
別段、彼女は灰になったりはしない。苦しむ様子もない。しかし、彼女の口からわずかに姿を覗かせた鋭利な牙がきらりと光った。
「“帰ること”があれば作者にファンレターでも送るか。吸血鬼は、稲妻を出すのと長生きなの以外はふつーですよーって」
「帰りたいのか?」
「全然」
神楽はためらわずに否定した。
動揺はなく、彼はまたあくびをしてから言った。
「帰るところもなく、向かうところもなく、ゆえに『迷い人』、なんだろう? そのとおり、俺は帰りたいなんて特に思っちゃあいないよ」
ごほんっと気まずそうにアーニャは咳払いをした。
「ま、お前たちの地球にいく手段なんてわかってないしな。ほら、歩いてなにか落ちてないか探せ。人がいたらすぐ保護してやらないといけないからな」
「その保護の手段が血の交換なんての、ちょっと物騒だよなあ」
神楽は首をさすった。そこに二つ、小さな傷穴の跡があった。
ここへきたばかりのとき、神楽は強烈なめまい、吐き気に苛まれた。しかし、倒れていたらアーニャに首を噛まれ、神楽と彼女の血をわずかに交換させられた。するとすぐさま体調がよくなった。環境の違いがあるとのことである。
「あんときはビビったなあ」
「ビビられてもやめない。この、迷い人の丘の管理は絶対に手を抜いてはいけない大事な仕事だ」
「じゃあ、あれはどうするの。管理する?」
神楽は目をこすり、遠くを指さした。
アーニャも目を向けると、少し離れたところに黒い毛並みの丸々と太った獣がいた。
熊だ。様子をうかがっているのか、距離をとっている。しばらくすると、ふいっと背を向けて歩き出し、林の中に消えてしまった。
「……あれは私の管理とは外れてる」
アーニャが言った。
「おそらく、餌が一時的になくなったのでここまで下りてきたんだろう。猟師に伝えておこう。ほら、神楽。仕事をする。なにか落ちてないか探せ」
「はいはーい」
のんきな声で神楽は返事をし、アーニャと一緒にあたりの草をかき分けていった。
丘の上にはいくつか、ものが落ちていた。
ネジや写真、紙の箱に入っている薄く黒い円盤。
小物は懐に入れて、かさばるものはそのまま神楽が脇に抱えて二人はすべて回収していった。
どうやら落ちいてたものはすべて回収したようだとわかると、神楽は大きく背筋を伸ばし、あたりを見回した。
彼がいるのは草が生い茂る丘。
遠くには山。様々な木々が並んでいるが、一部、大きな土砂崩れでもあったのか、えぐれているところがあった。食べ物も吹き飛んだので、熊がこっちにやってきたのだろう。
そして丘の麓には、高い城壁に囲われた城郭都市があった。
とんでもない竜巻や台風にでも襲われたのか、城壁や街のあちこちが破壊されていて全面工事中だった。
神楽がぼんやりしていると、そばにいたアーニャも穏やかな視線で同じくその都市を眺めていた。うっすらと口元に笑みを浮かべ、どこか母のようであった。
彼女は神楽が見ていることに気づくと、その街に向かって歩き出した。
「帰るか。客は一人、必ずいるんだからな」
「はいはい」
そう神楽が返事をしたとき、ふっとアーニャは丘を振り返る。
「今日は、なし。迷い人なし。点検終了。アーニャ・リュボーヴィ、帰宅します」
神楽に告げるでなく、彼女はそう宣言して再び歩き出した。
帝国ロマノヴァ。古い歴史を持つ国。
そこに属する城郭都市モルニア。経済は豊かであり、人口は約三〇〇〇人。
街は派手に破壊されていたが住民は明るく笑いあいながら修復工事をしていた。男も女も特に辛そうではない。
神楽は、そんな彼らを『稲妻アーニャ・リュボーヴィ』と書かれた看板を掲げている店の表から眺めていた。
「カイジュウ! 今日は飲みにいくからな! 姫様に伝えててくれよ!」
名前は知らないがよく顔を合わせる若い男に言われた。
神楽は軽く手を振って了承の意思を伝えると、その男は仕事に戻っていった。倒壊した家を新たに建て直しているところだった。
「怪獣なあ」
神楽は小さくぼやいた。
彼がここにきて約一ヵ月。その間についた彼のあだ名であった。
亀楽神楽。彼は日本人。
生まれも育ちも二一世紀の日本であったが一七歳のある日、先ほどまでアーニャといた丘にいた。
なんでもそういう場所らしい。
物や獣、服や本、おもちゃ、そして人が迷いこんでくる。それがあの迷い人の丘の特徴であり、アーニャは昔から管理をしてきたという。そして、神楽のようなものを保護してきたのだという。
ほとんどはアーニャに感謝をして旅立っていったが、この世界では『恩返し』をしなければいけない。そのため神楽はこの街にとどまり、アーニャの店の手伝いをしていた。
彼以外にここにいる迷い人は、現在ただ一人であった。
その男は、彼方より走ってきていた。
「カグラくーん! カグラくん! カグラくん! カグラくーん!!」
何度も神楽の名前を呼んで、大きく腕を振っている。
白衣を着た、前頭部が禿げ上がった白髪の老人。そんな人物が目を大きく見開いたピエロのような満面の笑みで、全力で走ってきていた。
「いいっ、ひぅ、いいひ、こっとぉ、思いついたぞぉ! カーグラくぅーん!!」
「こわい」
「おごぉ!」
近づいてきた瞬間に神楽が放ったパンチが老人の鳩尾に入った。
力はこめてなかったが見事なカウンターになったので、老人は硬い地面の上に倒れてしまった。
そして満面の笑みで、口からコポコポ液体をこぼしながら起き上がる。
「いいゴボッ、ゴボゴボッ、いいこっ、おろろ、思いついたぞぉ! おろろ!」
「朝食をもどしながら迫ってくるな! ドク!」
迫りくる老人、ドクを神楽は必死で抑えこんだ。
力は大したことはないがその勢いに押されてしまう。この奇人がもう一人の迷い人で、アメリカ出身のドクである。鍛冶や医者で生計を立てている。
「あのな、いいこと、おもしろいことを思いついたのだ! やろう! カグラくん!」
「やろうと言われてもな……」
「さあさあ、まずは酒でも飲みながら話そうじゃないか。おーい、稲妻姫。炒り豆の盛り合わせと蒸留酒を一本頼むぞー」
稲妻姫とはアーニャのこと。ドクは店に入ろうとするが、がっちり神楽はその巨体で行く手を塞いだ。
「むむっ!? なにかね、神楽くん。なぜ通してくれんのだ?」
「来客中だからな。なんか、相談事だとかなんとか。アーニャは街一番のおばあちゃんだからなあ、助言がほしいんだと」
「そうか。ならばしかたあるまい。国一番のご老公だからな!」
「そう、世界で一番の、えーと、ババアってのはちょっとひどい言い方だからな。なんかあるか?」
「生き字引。おっと、一番合っているじゃないか。ハッハッハ」
などとドクが笑っていると、扉が開いた。
入り口に紫電をはじけさせているそのアーニャがしかめっ面で立っていた。次の瞬間に自分の身に起こることが、神楽は予知できた。
「うるさいわ小僧ども!!」
「「――あガガガガガガッ!!」」
神楽とドク、そろってしびれた。
朝食を食べ終えているからか、元気な稲妻であった。しかし、このドクという老人はそんなことではへこたれなかった。
稲妻で白髪がちりちりになっていたが、微塵も勢いを落とさずアーニャに詰め寄った。
「稲妻稲妻稲妻姫! 稲妻姫! なあなあ、私の話を聞いてくれ!」
「ちっとは弱らんか! 来客中だからあとにしろ! 神楽!」
「わかってるよー」
神楽はドクの首根っこをひっつかんで持ち上げた。
ばたばた暴れているが、宙に浮かんでいたらどこにも進むことはできない。ほっとして、アーニャは店の扉を閉めた。
神楽はドクを店から少し離れたところに下ろした。
「というわけで、もうちょっと待ってろ」
「ふむ。仕方ないな。彼女にとっても実のある話だったのだが…………いたい。いたたたたた、鳩尾がいたい! ふぉぉぉ!!」
ドクは胸を押さえてうずくまった。
「悶絶するのが十秒遅いなあ。それで、なんの話だったんだ?」
「あいたた。ちょっと待て。ふぅ――っ、ふぅ――っ、よし。話はな、いわば慰安を兼ねたちょっとした催しなのだ。見たまえ、この街の惨状を」
ドクは青ざめた顔のまま工事中の街を指さした。
硬い石畳の地面があちこち陥没していたり、多くの家が半壊、全壊していた。瓦礫は片付けられているが、修復はまだ半分も進んじゃあいない。
地べたに座り込んだままドクは話を続ける。
「カグラくん。工事している彼らは、みないい笑顔だろう」
「そうだなあ……」
神楽は気まずそうに頭をかいた。
「しかし、しかしだよカグラくん! 彼らのその笑顔、明るさ、あれらは言ってしまえば一時的に正気を失っているだけにすぎないのだ!」
「こら。せめて声を小さくしろ」
「おおっと失敬失敬。だぁが、これは事実だ」
ドクはぎょろりと蛇かカエルのように目を見開いて神楽を見上げてくる。
「正気であればこのような事態になれば嘆く、怒る、悲しむ。あんなふうに馬鹿話をしながら仕事をしたりはしない。なにせ、彼らの多くは未だに野ざらしで暮らしているのだからな。一応、テントやなんやとあるが、正常な社会とは切り離されてしまっている」
「耳が痛いことをおっしゃる」
神楽は実際に耳を押さえて辛そうに顔を歪めた。まるで彼自身が街の惨禍に関与したような言い方であった。
「しかし、悪いと言っているわけではないぞ、カグラくん。正気を失ったこの異常な状況、いわば夢現。これを覚ますことはない。覚めるのは、みなが家を取り戻したときでいい。それまではあらゆる手段を講じてハイハイテンションにしておくべきなのだ」
「そのために、えーと、催しをするのだってことか」
悪くない話だと神楽も思った。
まだ日本にいたころ多くの災害を見聞きした。
インターネットで、テレビで、そして彼自身の目と耳で。
災害直後はまだなんとかなる。元の暮らしにすぐ戻れるという楽観的な空気がどこか漂っていた。しかし、時が過ぎるにつれてそういう空気はすぐに霧散し、鬱屈がたまっていく。
「慰安。いいなあ、それ」
神楽もうなずいたとき、店の扉が開いた。
今度出てきたのはアーニャではなく若い女だった。黒髪を三つ編みにしている。赤い服の上にマントを羽織っていて、背筋がピンと伸びていた。
ドクがひょこっと立ち上がった。
「おや、ツェツィ嬢ではないかね。来客は君か。どうした」
「金の無心でございます。朝早くから悪かったでありまする。用件はすみましたので、それでは失礼致しまする」
その女、ツェツィは神楽とドクに頭を下げて店から離れていった。
見送っていると、ドクに引っ張られた。
「さあさあ中に入ろうではないか! まずは蒸留酒! それとつまみだ! 飲みながら熱く話しあおう!」
「飲みか話か、どっちが主役かわからん――あだっ!」
神楽は頭をドアの梁に打ち付けた。
いつもながら、体をぎゅっと縮こまらせなければ扉を通れないのは面倒だった。
アーニャの店。店主である彼女は喫茶店と言っているが実情は居酒屋である。
昼間から酒とツマミを出している。というか、それ以外はほとんど出ない。米もパンもあるにはあるが、酒に合うように調理されたものばかりが注文される。
この日も稲妻で薪に火をつけ、竈でせっせと一番注文される炒り豆の盛り合わせを作っていた。
「ほらよ、食え」
できあがると、大皿に移して神楽とドクが座るテーブルに持ってきた。
「うむ。いつもの味、いつもの手抜き、それといつもの酒。朝を実感するなあ!」
ボリボリボリボリ、ハムスターのようにドクは豆を食べていく。
陶器のコップに入った蒸留酒で食べかすを喉に流し込んで大きなゲップ。アーニャは顔をしかめながらも話を詳しく聞いた。
「慰安そのものについては文句ない。しかし、問題がある。飯がない」
「……え、どういうこと?」
神楽が首を傾げた。彼は一段と低い椅子に座っているので視線の高さはほかの二人と合っている。
アーニャは豆を一粒摘んで答えた。
「慰安ってことは、なにがしか祭りでもするってことだろう? その場合、食い物や酒の消費量が格段に上がる。実のところ、いまでも食料の値段を下げて、常時お祭りのような気分にさせているんだ。これ以上となると厳しい」
「ちょっとちょっと、待ちたまえ。なぜだ。このまえのあれで大変だったとはいえ、備蓄はまだまだあるだろう? 交易だってどことも途絶えたわけじゃなかろうに」
ドクがまくしたてるように言ったが、アーニャは渋い顔で否定した。
「いや、途絶えてる。それがさっきのツェツィの用件だった」
アーニャは苛立ちを消すように酒を飲んだ。
アルコール臭がきつく、神楽にしたら小さな子がぐびぐび飲んでいるというのは少々違和感がするものだった。
「知ってのとおり、ツェツィの実家、ツポーレ商会はでかい。その力を使って今回の件ではあちこち手を回して食料、建材を融通してもらった」
「ありがたいなあ」
うんうんと神楽もうなずく。
「それで、小さな村にもいったんだ。少しずつかき集めればなんとかなる。しかし、ある村にいった商人がいまだ帰らず、連絡もない。なにかがあった」
「なにか、なにかって……なに?」
「わからんからツェツィがここにきてたんだ。私にその村に出向いて調査してくれって。あいつは手伝いで忙しいからな。と、いうわけだ、ドク。祭りはできん」
話を聞いて、ドクはむすっと頬をふくらませた。このいやに子どもっぽいしぐさ、常時こんなものなので神楽も慣れてしまった。
「ん~、つまらん。だが、仕方あるまい。どのみち、私としては慰安にかこつけてカグラくんの身体能力を調べたかったのだしな」
「だろうな」
アーニャは豆を一粒かじった。
「そんなわけで神楽、明日にでも出発するぞ」
「はあ、どこに?」
「山一つ向こうだ」
出発はまだ日が昇っていない時間帯からだった。
風は冷たく、マントをしっかり羽織っていないと凍えてしまう。草や木々は夜露をたらし、鳥が高い声で鳴いている。
そんななか、神楽は険しく狭い山道を歩いていた。
木々が鬱蒼と茂っていて人っ子一人見当たらない。山菜なんかは生えているが、おそらくモルニアの山菜採りもなかなかこないのだろう。手付かずだった。
明らかに交易路ではない。
神楽はひいこら歩きながらぼやいた。
「せめて、馬でもあれば、なんとか、楽なのに……」
「馬はお前を乗せれば潰れる。馬車はここを通れない。もう一つ、うちで飼ってるあいつなら問題ないが、その場合相手を無意味に萎縮させる。だから、徒歩しかない」
「……わかってる。わかってる。でも、二つ気になることがある」
神楽は若干歩みを遅くし、呼吸を整えてアーニャに尋ねた。
「一つは、この道、正しいのかってこと……。ていうか、どんどん狭くなって、道とも呼べなくなってるんだけど……」
神楽の正面、木々がないのでどうにか進む方向がわかる程度だ。緑で覆われて、いつ物陰から蛇やイタチが飛び出てきてもおかしくない。
「大丈夫、正しいとも」
アーニャは一切迷わず答えた。
「この道は、私が開拓したんだ」
「え、どういうこと?」
「そのまま。私がこの道を抜けて、村や街を発見した。そのときは帝国の領土でもなかった。ずいぶん古いことだしな。後に、街道も整備されたが、そっちは距離が遠い。今回は拙速じゃないとダメなんだ」
「なるほど、わかった。じゃあ、あと一つ」
神楽は立ち止まって深く息を吸い込んだ。
歩きづめで足が疲れている。荷物は携帯食料といざというときのキャンプ用具くらいだが、余計なものがもう一つある。神楽は背後を振り向いた。
「なんでアーニャは俺の背中に乗ってるんだ」
「ちゃーんと出発するときに説明しただろう。必要なことなんだ」
「わざわざ椅子まで用意するほどのことかあ?」
神楽はがっくりと肩を落とした。
彼の背負う荷物、その後ろに椅子が括りつけられていて、アーニャが座っていた。
「俺はお前に保護された。身分は奴隷。だから荷物持ちはする。でも、主人持ちってのはどうよ。おばあちゃん。三〇〇歳を越えて足が弱ったかい?」
「三〇〇歳以上ってのは否定せんが、おばあちゃんと言うな」
バヂッとアーニャの稲妻が神楽を打ち据えた。
「――あガガッ! い、稲妻撃つなよ! 荷物がダメになるかもしれないだろう!」
「出力は弱めてる。あのなあ、これも言っただろう。身分差は、明確にしないといけないんだ」
「十分明確だろう。荷物持ちだけで」
「足りない。私は主人としての格、お前は奴隷としての格を見せつける必要がある。そのために、私の靴が汚れていてはならないんだ」
神楽はため息をついた。
「なんか、騙されてる気分」
いまいち納得しきれずに神楽は歩みを再開した。
途中、休憩をはさみながら進んでいくと昨日の熊が様子を窺っているのが見えた。アーニャが稲妻で追い払い、事なきを得たが、しつこくついてきていた。
「えさがないのかも。ほら、このまえのあれで」
神楽は振り返らずに歩いている。
「ああ。でもそうするしかなかったからな。すまんな熊くん。多分、ヒグマだが」
アーニャの稲妻。火花が山に移らないように、音だけを激しくさせていた。
そうこうして昼を過ぎたころ、ようやく神楽たちは山を越えた。
眼下に広がる光景を見て、神楽はため息がこぼれた。
「おぉー、海だ。海だ海」
さあっと風が吹くと潮の香りがした。
開けた視界、遠くに青い海が見える。空には白い雲が並んでいて、夏になれば海水浴で楽しむことができるだろう。沖には船も浮かんでいる。
「そういや、こっちきてから魚を食ってなかった。村で刺身とか出るかな」
「あまり期待するなよ。その村でなにかがあったのかもしれんのだからな」
「はいはい。んで、どっち?」
「あっち」
アーニャに背後から指示され、神楽は山を降りていった。
難所を越えたからか、神楽は少し楽しみになっていた。海は好きだし、魚も好物だ。まさか邪険に扱われることもないだろうから、そこそこ豪勢な食事が用意されるはず。
しかし、アーニャの懸念は見事的中していた。
食事どころではなかった。
村の名前はタケマ。アーニャとは関係ない迷い人が開拓した村だという。元々の土着民族とは諍いが絶えなかったが、自立を守ってきた。
その村が、危機に陥っていた。
海沿いにあるタケマの村。神楽はそこを見下ろせる高台にいた。アーニャも自分の足で立って、厳しい目で睨んでいた。
その村は、なんらかの集団に囲まれていた。長期間滞在できるようにか天幕まで張っていた。
「なにが起こっている」
アーニャの顔に怒りはない。状況の把握に努めようと冷静だった。
神楽は荷物からドクに渡された双眼鏡を取り出し、アーニャに渡した。
「お、すまんな。どれどれ……」
アーニャはすぐ観察。神楽も自分のぶんを取り出し、眺めてみた。
その集団、一〇〇人には満たない。七〇から八〇ほどだ。
装備がよかった。鎧や剣、盾をしっかり備えていて、槍もたくさん用意されている。これは兵隊だ。しかし、村のほうは日本の着物のような服に剣だけと、貧相である。
兵隊の規律はよくないのかあちらこちらで雑談をしていて、緊張感がない。
「即席の兵隊だな。私兵隊とでもいうか」
アーニャはすぐに看破した。
続けて観察していると、一番立派な天幕から一人の男が出てきた。精悍な顔つきで、眼力がある。一人だけマントを羽織っていてえらそうだ。
「――まいった」
アーニャが双眼鏡を外してため息をついた。
「どうした?」
「ああ、どこのどいつか知らんが、争っているなら近くの大きな都市の人間に仲裁してもらおうとしたんだが、兵隊率いてるのがその都市のやつだ」
「あらまあ」
「しかも想像通り、商人は村の中で足止め食らってる。どうにかしないとまとめて殺されるな」
「商人がいなかったら放っておいたの?」
返事はげんこつだった。
「私をみくびるな。バカモン」
「冗談だよ。うちのご主人様、口調がキツイけどやさしいからね」
「お前は口の利き方を直せ!」
照れ隠しの蹴り。あんまり痛くはない。
「で、話を戻すけど、どうするの? まさか俺に蹴散らせってんじゃないよね」
神楽は軽く拳を握り、こんこんと打ち鳴らした。アーニャは渋い顔で否定した。
「どっちとも交流があるのにそんなことはできん。可能な限り穏便に、双方が納得できる落としどころを探りたいが……」
「滅ぼすつもりじゃないの、あれ」
神楽は率直に言った。アーニャもうなずく。
「そうだろうな。そうしてもかまわないって態度だ。ただ、商会の人間がいることが障害になっている。ツェツィの家、ツポーレ商会はあちこちの都市に顔が利く。そこの人間を殺したなんてことになったら……」
アーニャはふうっとため息をついた。
神楽が続きを聞く。
「戦争になったり?」
「そこまではいかんが、流通が遮断されるだろうな。ろくなことにならん」
「じゃあ、ゆっくりできる余地が……あるの?」
「ないから困ってるんだよ。でもここでじっとしてるわけにもいかない。いくぞ、神楽」
アーニャは急ぎ、高台を駆け下りていった。
「おんぶしなくていいのー?」
「してる場合じゃない!」
「はいはい。でも荷物は持つんだよなあ」
よっこいしょと神楽は荷を背負って駆け下りていった。椅子は捨てた。
急ぐアーニャ。追い抜かず、そのあとについていく。
穏便に事がすめばそれでいい。神楽もそう思っているが、このままいけばまずいこともわかっていた。
「アーニャ、スピード落として」
「落とさん! 急げ! 急げ! 遅れるな!」
「いやあ、急いだらまずいんだよなあ」
「のんきに言うな! 急いで話をつけないといかんだろ!」
まったくもって正論だ。のんびりしていて戦争が始まったら乱入するしかない。
それは神楽も望まないことだが、アーニャは気づいていない。
亀楽神楽。彼の体格は異常である。
身長、二メートル五〇センチ。体重、二二〇キロ。
巨人である。そんなのが走ってきたらどうなるか。
「――ば、化け物だあ!」
こうなる。
兵隊は一気に騒然となり、武器を構えた。腰が引けているのでなにかあれば逃げ出すだろう。
「日本にいたときから慣れてるけど、凹むなあ」
神楽はふてくされた。アーニャも気まずそうに振り返る。
「ご、ごめん……」
「いいよお。とにかく話をしにいこう。うん」
走るのをやめると兵隊たちも落ち着いた。
わかりやすい上下関係を示すために神楽は深く背を曲げ、アーニャの三歩後ろをついていく。
顔の判別ができるほど近くなると、アーニャは仁王立ちになり大きく呼びかけた。
「ナヴァリナのボリス! レオンチェフ家当主、ボリス! 事情を説明しろ!」
毅然とした態度、強く威厳のある発声。ただの少女ではないというには十分だ。
ざわめいていたが、双眼鏡で見た男が前に出てきた。
「……お久しぶりでございます」
太い声だ。
男は神楽よりも年上で三〇代だろう。胸を張って立っている。一見、堂々とした姿だがチラチラ神楽に視線を向けてきている。アーニャも気づく。
「私を見ろ。奴隷ではなく、私を見ろ。ボリス」
「失礼いたしました、稲妻姫」
稲妻姫というと、兵隊も騒ぎ出した。
アーニャは有名だ。迷い人の丘の管理を任されたのは大昔らしいが、いまでも帝国皇室と繋がりがあり、それに、彼女が保護したものは様々な業界で功績を残している。
たとえば神楽がいま着ている服。皇室御用達の職人が製作したのだが、その人物はアーニャがかつて保護したものの子孫である。そこの服は一種のステータスであり、目の前のボリス、彼のマントも一目で同じ製作者のものであるとわかった。
「して、稲妻姫、なに用でございましょうか。ここはモルニアよりも遠く、あなたの管理下の丘とも違いますが」
「なに用ときたか。質問しているのは私だぞ、小僧。二度目だ。事情を説明しろ」
アーニャの言葉に合わせ、ゆっくり神楽が背筋を伸ばす。
それだけで兵隊が揃って一歩後ろに下がった。
「威嚇するな、神楽」
アーニャに注意される。
「ボリス。答えろ。あのタケマの村も帝国の臣である。そこをこのような兵を率い攻め入るというのは、正当な理由があるはずだな」
「理由、理由ですか、稲妻姫。ありますとも。これは、私たちの街、ナヴァリナを発展させるための行為です」
いまさら神楽はナヴァリナというのが街のことだと気づいた。
アーニャは眉間にしわを寄せて鋭く問い詰める。
「ナヴァリナとこのタケマの村は親交が深かったはずだぞ」
「はい。確かに。しかし、私には港湾都市ナヴァリナを大きくする使命があります。そのためには、このタケマの村を取り込まなくてはなりません」
「取り込む? 殲滅ではないのか?」
「応じてもらえなければそうなります」
悪びれずにボリスは言った。
背後からでも、神楽はアーニャの機嫌が悪くなっていることに気づいた。
比べてボリスは会話を重ねていくほどに落ち着いていく。目の奥にある光が輝きを増しうっすらと笑みも浮かんでいる。
「一方的すぎる話だな。私の街、モルニアはナヴァリナと交流があるがタケマの村とも交流がある。はいそうですかと見過ごすわけにはいかない」
「参りましたな、これは」
おどけたようにボリスは頭を掻いた。
「では、こうしましょう。私としてもなるべく穏便にすませたい。本心ですよ。なので、交渉の場を設けていただきたい」
「恫喝ではなく、だな」
「もちろん」
白々しい。
「ああ、ですが、そちらの奴隷は置いていってもらいたい。見た目から、その、一騎当千はありそうです。肩入れされたら、どうしようもありません」
ボリスは神楽を見上げてきた。
背丈では明らかに神楽が上だが、ボリスには妙な自信がある。かけらもおそれていない。
アーニャは数秒ほど間を置いてから答えた。
「いいだろう。こいつを置いていく。神楽、おとなしく待っていろ」
そう言われた神楽は、そっとアーニャの耳元に近づき、小声で少し話をする。
「さっさとぶちのめしたほうが話がはやい」
「できない。同意するが、その場合、モルニアとナヴァリナとの間で戦争が起きる可能性がある。復興も遅れる。ただ、合図をしたら、やれ」
「……合図って、これ?」
神楽はとんとんと自分の喉を叩いた。
アーニャは小さくうなずき、ボリスに向き直る。
「話し合いは終わった。こいつを置いていく。不安なら縄で縛るなり即席の牢屋に突っ込むなり好きにしろ」
「はい。それではどうぞ、いってらっしゃいませ」
アーニャはふんっと鼻を鳴らし、神楽の荷から村長への贈り物だけを持って村へと向かった。
神楽はその背中を見送り、どっしりとその場に座る。
「どうする? ポリスさん」
「ボリスだ。おい、厳重に縛っておけ。何重にもだ。見張りは二人だ」
ボリスが命令すると、神楽はそそくさと兵隊に全身簀巻きにされてしまった。
過小評価しない。しっかり怖がっているようである。
「はてさて、どうなるかなあ」
神楽はのんきにつぶやき、ごろんとその場で横になった。
「ほら、天幕にでもどこにでも運べー。なにもしないぞお」
実際、神楽はなにもしなかった。
そのため、ボリスの兵隊は五人がかり天幕に運ばなければならなかった。地味な嫌がらせである。
アーニャが村に向かった。
門前では剣を構えた多くの村人が警戒していたが、近づいていくと驚きとともに迎え入れられた。
「姫様! 姫様ではございませぬか!」
年老いた男がともを連れ、慌てた様子で駆け寄ってきた。
ボリスとは違いすぐさまその場に両膝をついて頭を下げる。
「せ、せっかくのご来訪でありますのに、申し訳ございませぬ。状況が状況ゆえ、歓待の宴もできず……」
「いらぬ。顔を上げろ。宴の準備などせんでいい」
「は、はい……。ひ、姫様、それで、どうされたのでしょうか。このようなときに訪れるなど……」
機嫌をうかがうように見上げてくる。怖がっていた。
アーニャは安心させるように自らも膝をつき、やさしく村長の肩に手を置いた。
「こういうときならばこそだろ。元々の理由はここで足止め食らってる商人がうちのものだからだがな。どこにいる?」
「それならば、あちらに」
村長が示した先にこの村とは違う衣服の男がいた。彼も駆け寄ってきて深々と頭を下げてくる。
「連絡できずに申し訳ありませんでした、姫様」
「かまわん。事情が事情だ。むしろ、一人で逃げ出さないことを立派に思うぞ。私はお前の雇い主ではないがな。村長、詳しい話を頼む」
「ははっ、かしこまりました。それではこちらへ」
アーニャは村の集会所に案内された。
そこで村長を始めとする年寄りたちから事情を聞き、事の全貌、というほどでもなかったが、だいたいのことが判明した。
要は、あのボリスという男に野心が芽生えたのだ。
ナヴァリナとは港湾都市であり、海の向こうには隣国の港がある。ボリスが生まれるよりはるか以前はそこと戦争をしていて、ナヴァリナも取られては取り返しと、いわば最前線だった。しかし、戦争が終わって帝国の都市になってからは平穏だった。
それがボリスにはつまらなかったか。はたまた先祖返りで武官の血が目覚めたか。彼は都市拡大という夢を見た。
「で、お前たちに恭順することを迫ったと」
アーニャは呆れながら言った。
村長も困った顔をしている。
「はい。土地の保障はするから、我らに兵隊になり、ともに鍛えよと。ですが、むちゃくちゃです。ボリス、かのものの目指す先は英雄。帝国と戦うつもりなのです。そんなのはわしらもとても賛同できません」
「そしたら、ああやって恫喝にきたと」
アーニャは交渉とは言わなかった。
「あいつもバカではないから、多分、勝ち目があると判断したのだろうな。どこかから援助があるとか。まあ、そこのところはどうでもいい。村長、戦えるものはどれくらいだ」
「少々無理をすれば、三〇人ほどは」
「では、無理をするな」
アーニャの言葉は予想外だったか村長たちは呆気にとられた。
互いが顔を見合わせてから、おそるおそるたずねてきた。
「無理をするな、とは」
「戦うなということだ。ボリスに従属しろということでもない」
アーニャは集会所のなかを見渡した。窓の外にいるものたちにも向けて宣言する。
「私はどちらか片方に与するつもりはない。事を穏便に治めるつもりである。無論、非がどちらにあるかはわかる。しかし、私は仲裁を目的としている」
「ですが、交渉もなにもできませぬ! 連中は……」
「わかっている。ボリスめ、実戦訓練としてお前たちを見ている。村長、天気はどうだ」
脈絡もなくアーニャはそんなことをたずねた。
困惑していたが、村長はちゃんと答えた。
「深夜になれば雨が降るかと……――まさか!」
「まさかだ。ボリスは雨と一緒に襲撃をしかけてくる」
アーニャは確信を持っていた。
村長とそのほかの面々も否定しなかった。
彼らも知っている。ボリスも知っている。
雨こそがアーニャの、吸血鬼の最大の弱点であるということを。
「あのバカは野心にとらわれている。わかりやすく名をあげるため、私の首を狙ってくる」
風が吹いた。集会所の外から潮の香りがした。それに混ざった雨の匂いも。
それからアーニャは村にとどまり、軽く食事をいただいた。
不安げな村人たちに、いくども心配ない、大丈夫だと繰り返し、ただじっと待っていた。
そうして深夜、普段は寝静まっている時間帯、雨が降ってきた。
雨音とともにアーニャは外に出た。
ここへくるときは汚れを嫌っていたが、いまは進んで泥濘るんだ土の上を歩いた。
村人たちには離れていてもらい、一人だけで門前に立った。すると前方からアーニャの言ったとおり、ボリスが隊を引き連れてやってきた。
「止まれ、小僧」
静かだが怒気をはらんだ声をアーニャは発した。指先から稲妻をはじけさせている。
ボリスは、ゆうゆうと歩いてきて、止まったのはアーニャの目の前でだった。
「まだ交渉の場は設けられていない。そもそもこんな時間帯にくるな。戻れ」
「お断りします、稲妻姫」
獣を真似たような笑みをボリスは浮かべた。
「長引けば長引くほど我々に疲労がたまり、不利になる。そもそも、あなたにその気があるのですか?」
「まだ一日、いや、半日と経過していないぞ。そんな早く意見がまとまるか」
「まとまらないのならば、それは彼らが自ら選んだ、ということでしょう。優柔不断な、滅びへの道を。どいてください、稲妻姫」
「どいてたまるか」
アーニャは仁王立ちになって門を塞ぐ。
ボリスは待ってましたとばかりに剣を引き抜いた。
「ならば仕方ありませんな。あなたを殺し、この村を滅ぼすまで。命、もらいます」
ボリスの剣がアーニャの首に襲いかかる。
しかし、刃は届かない。
アーニャの右手にいつのまにか『青い鎖』が現れ、剣を止めていた。
「んっ……! くっ、それは……!」
「この世界に生きるものなら知ってるだろう。契約の鎖。奴隷の鎖。保護したものと保護されたもの、私と神楽とをつなぐものだ。バカが!」
アーニャは空いている左手でボリスの剣に触り、稲妻をはじけさせた。
「――ぐあっ!」
ボリスは咄嗟に剣を捨てたが、電気が流れて指先をしびれさせていた。
アーニャは右手を空に振った。すると、そこから鎖は消えてしまう。
「バカガキめ。図体ばかり大きくなって、私に敵うと思ったか。姫様、姫様と私にだっこをせがんできたガキが、なにを図に乗っている。恥を知れ! 小僧!」
「やかましい! 稲妻がなんだというか! 知っているぞ! 稲妻姫、あなたたち吸血鬼は、雨に弱いと! 稲妻を放ってみろ! 撃ってみろ! できないだろう!」
アーニャは指先でバヂッ、バヂヂッと稲妻をはじけさせたが、それ以上はない。
神楽にやっていたように飛ばすことができない。雨という水の壁に触れた瞬間に霧散する。
ボリスは安堵すると、足元に落ちていた石を取って投げつけた。
アーニャは避けられなかった。手で受けたが出血してしまう。
「それ見たことか! 進め! 破壊しろ! 稲妻姫など恐れるに足らん!」
兵は呼応し、弓を取り出した。一斉に矢を放たれたらアーニャはどうしようもない。
しかし、彼女は寂しそうに一度笑うと、子どもに言い聞かせるような声音でこう言った。
「勝ったつもりか小僧」
ビクッとボリスは身を竦ませる。
アーニャは言葉を続けた。
「得意気になったガキが、それで勝ったつもりか。私の武器が、稲妻だけだと思ったか。私が、なんでわざわざ交渉の場を設けるなどということを引き受けたと思っている」
「……な、なに?」
追い詰められているはずのアーニャには覇気があった。
ボリスも兵隊もうろたえ、じっと話を聞いていた。
「いいか、ボリス。お前はまだ、これが港湾都市ナヴァリナとタケマの村の争いだと思っているんだろう。そうじゃあない。仲裁役を引き受けた私をお前が攻撃したことで、もはやこれは私とお前の私闘に成り下がったのだ。つまり、これから私がお前をどうしようと、誰も、お前の親も、帝国皇室も関与することはなくなったのだ」
「な、な、な、なにがいいたい!」
「もう一度言おう! 私の武器が稲妻だけだと――――――――――――思ったか!!」
そのときだった。
ふっと雨が弱まった。空気が揺らめいた。
そんな錯覚をその場の全員が感じた直後。
「ヴォォォォ――――――――――ッ!!」
破壊的な咆哮が響いた。
音としてではなくほとんど物理的な暴力である。腰を抜かすか、つんのめって倒れるものまで出た。
発生源はボリスたちの後方。
天幕の一つが崩れ、そこから巨人がせり上がってきた。
大きかった。太かった。
まるで、山だった。
亀楽神楽だった。縄で縛られていたはずが、彼は簡単に引きちぎってしまっていた。見張りも倒れている。
「背筋を伸ばしただけであんなに背が高くなるものなのか!?」
ボリスがうろたえている。
その疑問はある種、正鵠を射ているものだった。
アーニャが混乱するボリスたちに向けて言った。
「さっきの鎖が合図だ。あいつの名前は亀楽神楽。日本という国からの迷い人。それでいて、もう一つ名前がついた」
ボリスたちの目は神楽に集中しているが、耳はアーニャに集中していた。
「怪獣王カメラカグラ。拘束しようとしても無意味だ。やれ! 考えうる限りのおそろしい手段で、全員を無力化しろ!」
アーニャの指示に従い神楽は歩き出した。
背筋を伸ばして一歩、二歩と進む。ただそれだけで恐怖が伝搬し、悲鳴があがった。
ボリスは焦りながらも指示を出した。
「落ち着けい! でかいだけだ! それだけだ! 矢を放てぇ!」
ボリスの威厳が消えたわけではない。震えながらも兵隊は神楽に矢を放った。
神楽は、避けなかった。盾もないので矢はその身に刺さった。
肩に胸に、腹に、大きいのでほとんどが刺さった。
そして、変わらぬ歩みで進んだ。
「なな、なあ、なんでだ! なんでだよ! どうすんですかボリス様!」
隊の混乱は治まらない。もう誰もアーニャのことなど気にとめていない。
「や、やり、槍を構えろ! 全員で、串刺しに!」
「……まーだ気づかんか」
アーニャがそう言ったが、誰の耳にも入っていなかった。
ボリスを含め、全員が槍を持って神楽に向かう。
彼らは止まらず、たった一人を殺すために一斉に槍を突き刺そうとし、できなかった。
「……た、た、た、い、ちょう」
「たいちょう、たい、ちょう」
「たいちょう。たいちょう。ボリス様ぁ、槍が、槍が、」
泣いているものもいた。
ボリスの兵隊は槍を神楽の腹や足に刺したが、骨どころか肉にも届かない。
槍の穂先は神楽の皮膚で止まっていた。
かわいそうになってきたのでアーニャはネタばらしをした。
「ボリス、私が保護したものは、私の影響を受ける。迷い人は環境が合わないため血を交換して身体を変える必要があるからな。モルニアにいるドクという迷い人は計算力が飛躍的に向上した。そしてそいつは、」
神楽は、両拳をぎゅっと握りしめた。
力を入れた。そうすると筋肉が膨張する。人間誰しもだ。
神楽も膨張するが、すべてだった。
腕に肩、首、胸に背中、腹、腰、両足、さらには頭まで膨張した。
亀楽神楽は、巨大化した。
「それが、神楽の特性」
神楽は右腕を大きく振るった。
その一動作で、自分に刺さっていた槍をすべてなぎ払ってしまう。
そして、手近な兵の胸ぐらをつかんで持ち上げる。
それから、ぶん投げた。
神楽は鎧を着た成人男性を片手で投げた。
まるで石ころのように人が飛ぶ。跳ね、転び、動かなくなる。
そこからは阿鼻叫喚だった。
「いやあ! いやあ! 助け、助けてー!」
「ごめんなさい! ごめんなさい! 許してください!」
「お、俺じゃない! 悪くない! 俺じゃない!」
「ゆるしてくれええええ!」
神楽はぽんぽん人を投げ飛ばした。
彼ら一人一人の重量は、八〇キロはあるはずだ。
そんな重さを片腕であっちこっちへ投げて投げて投げて投げて、投げまくる。
死にはしないが、恐怖もあって誰も起き上がってこなかった。
半数は逃げていったが戦いは終わった。
戦意を持っているものはいなくなってしまった。
「全員武器を捨て、鎧も脱いで村に入るんだ。倒れているやつも運んでやれ。放置するにはかわいそうだからな。さて、ボリス!」
アーニャは事の原因を呼んだ。
返事はなかった。気絶しているのかと思ったがそうではない。
彼はここにはいなかった。
ボリスはほうほうの体で逃げ出していた。
脇目もふらず、追ってこられないように山のなかにかき分けて入っていった。
わずかな月の光もここには届かない。仮に犬並みの嗅覚を持っていたとしても、雨で体臭は消えてしまっている。
大丈夫。ボリスは自分に言い聞かせた。
大丈夫。まだまだ再起できる。
自分はこんなところで終わらない。もっと大きく、名を知らしめるのだ。
こんなもの、他人が聞けば妄執、妄想のたぐいと切って捨てるだろう。しかし、彼はまだ夢想していた。
息を潜め、膝を抱えて丸くなり、ひたすら時間が過ぎていくのを待つ。
ガサガサと、草を踏み荒らす音がした。
誰かがいる。一人だけのようだ。
多分、神楽。ここまで探しにきたのだ。
ボリスの心臓はバクバクと激しい鼓動を繰り返すが、決して声を漏らさない。岩のようになって静かにしている。
ところが、彼はある可能性を忘れていた。
山は生物の宝庫である。草があり、木があり、虫がいて、そして、獣がいる。
彼が気をつけなければいけないのは、最後、獣だった。
「フウ――、フウ――、」
ボリスの呼吸ではない。
妙に大きい、神楽の呼吸。
いいや、違う。神楽ではない。
「フウ――」
背後、ボリスのすぐそばに迫ってきていたので、ボリスもこれが人の呼吸ではないとわかった。
彼が振り向くと、そこには毛むくじゃらの獣が立っていた。
「く、く、」
ボリスは絶叫した。
「クマ――――――ッ!!」
ヒグマだった。
ボリスは逃げた。逃げたが、ヒグマは獣。人間より速い。
斜面を駆け下りてもすぐに追いつかれる。
力勝負。そんなのは無意味。ヒグマの体重は四〇〇キロを超えるのだ。
人間はなすすべもなく食われる。ただ、人間でなかったら話は別。
「こっち」
ぐんっと腕を強く引っ張られた。
その力も尋常じゃなく、ボリスは軽々持ち上げられた。
そんなことができるのは一人。
神楽だ。
神楽はボリスを地面に捨てて、駆けてくるヒグマと向き合った。
人とヒグマ。かないっこない。
しかし、怪獣とヒグマであれば、逆転する。
「ぬああっ!」
神楽は、張り手をヒグマの顔面にぶちかました。
その一発でヒグマはひっくり返った。
さすがに四〇〇キロと太いだけあって死ぬことも気絶することもなかったが、襲ってくることはなかった。
神楽は虫を払うように腕を振る。すると、ヒグマはすごすごと山の奥に帰っていった。
「おーい、無事かー?」
ボリスに声をかけると、震えながらもうなずいた。
暗闇でも青ざめていることがわかった。
神楽はボリスを持ち上げ、肩に担ぐと山を降りていった。
「ま、残念でした。あんたの野心は終了。お疲れさま。それともまだやる?」
ボリスは弱々しい声で答えた。
「……もういい。もう、もうなにもしたくない」
「無難だろうなあ。あ、そうだ」
「ん?」
神楽はピタリと足を止めた。
「アーニャに、けつでも叩いてこいって言われてた。悪さしたんだからおしおきだって」
「ま、待て、待ってくれ……! お、お前がやるのか!?」
「手っ取り早いし。はい、歯を食いしばってー」
神楽は容赦なく平手をお見舞いする。
野太い悲鳴が山にこだました。
翌日の昼、神楽はアーニャと一緒に元きた道を戻っていた。モルニアに続く、狭く険しい山道である。
今回はアーニャも自分の足で、神楽の前を歩いている。見栄を張る必要もないからだ。
「……馬車で帰りたかった」
歩きながら神楽が愚痴をこぼす。
「馬車を借りるなら、しばらくはお詫びの宴会やらなんやらに捕まっていたからな。しかたない。商人の馬車には荷がいっぱいで、お前は乗れなかった。諦めろ」
「わかってるよぉ。で、俺は寝てたけど、結局どうなったの。村と、都市との関係は」
「朝方にも説明したが、私とボリスの個人的私闘に成り下がった。表沙汰にはならないから、ボリスの家になんの影響もない」
ああ、と、神楽は理解した。
「それもあってあんな回りくどいことをしたのか。村だけじゃなく、ボリスの家を守るために」
「そうだ。とはいえ、ボリス本人は隠居だ。その後は父が当主として復帰し、村長の息子を娘婿として引き入れる。そういうことになるだろう。あんなことがないようにということで、結びつきを強くするためにな。詫びもあるから、それが落としどころだな。ボリスの妹はおしとやかで、村長の息子もいいやつだ。悪くならんだろう」
そこまで話すとしばらく無言になった。
歩いていく。
木々の間に、ふと昨日張り手をかました熊の姿が見えたが、追ってこなかった。
神楽はアーニャを見つめながら言った。
「でも、よかったなあ」
「なにがだ?」
「村人もボリスも、誰も死なずにすんだんだから」
「――、そうだな」
アーニャはほっとしたように笑った。
「私の記憶は鮮明だ。ボリスの幼いときのことも覚えている。あいつが私の足にしがみついてきたときのこと、あいつが私にほほえみかけてきたときのこと、あいつが私の子守唄で眠ったこと、覚えている」
「そっか。そうか」
風が吹く。
アーニャの横顔が見えた。彼女は、懐かしむように笑っていた。
一瞬だけ目が合うと、ぷいっと顔を背けた。
「そうなんだ。だから神楽、――がとう」
急に声が小さくなったので聞こえなかった。
「え? なんていったんだー? よく聞こえなかったなあ」
「……ありがとう」
「え? なんですってー?」
「ありがとうと言ったんだよ! 聞こえてるだろ! このバカ!」
真っ赤な顔で振り返って、蹴ってきた。
稲妻を出さないのは感謝もあってだろう。
「いやあ、一度目は本当に聞こえなかったなあ。なんで照れてるの」
「~~~~ッ! 本当に、よかったって思ったからだよ!」
スネを蹴られた。
頑丈なので、神楽はちっとも痛くない。
「バカバカバカ!」
「う~ん、すげえ顔真っ赤」
「――も、もう許さん! 許さん! 直接接触しての、高出力だ!」
神楽が逃げるのを許さんとばかりに、アーニャは肩に飛び乗ってきた。
肩車の形だ。
「しびれろ、バカ――!」
アーニャは全身から稲妻をはじけさせた。
「――あガガガガガガガガガッ!」
激しい痛みとしびれが神楽を襲うが、慣れているので安心もする。
身体が変わったからかなあと考えながらモルニアに向かって歩いていく。
「あのな、奴隷なんだからな! いい加減、口の利き方をわきまえろ! いいな!」
「わかったよ、おばあちゃん」
「……そういうところだ、このバカ――!」
また稲妻だった。